ネットゼロとは?物流領域において押さえておくべき基礎知識を解説
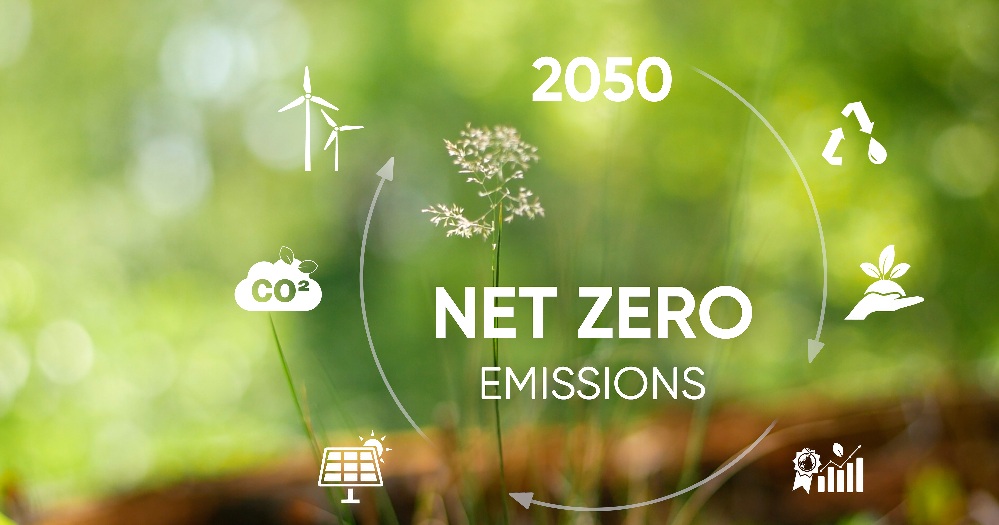
脱炭素化がグローバルに進む中、「ネットゼロ」という言葉を耳にする機会が増えてきました。温室効果ガスの排出を限りなくゼロに近づけるこの取り組みは、製造業などあらゆる産業に波及しています。
本記事では、「ネットゼロとは何か?」という基本から、物流領域における具体的な対応施策、導入時の課題、そしてネットゼロ実現に向けたステップなどについて物流DXパートナーのHacobuが解説します。
目次
ネットゼロの基本知識
気候変動対策の一環として、世界中で注目されているのが「ネットゼロ」という考え方です。カーボンニュートラルとも関連するこの言葉は、環境対策に積極的な企業の取り組みや政府の政策にも頻繁に登場するようになってきました。特に製造業や小売業においても、持続可能なビジネスを実現するうえで無視できないキーワードとなっています。
ネットゼロとは
ネットゼロとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにすることを指す概念です。これは単に排出をゼロにするのではなく、どうしても排出されてしまう分を、森林による吸収やカーボンクレジットの活用などで相殺することによって、実質的な排出量をゼロにするという考え方です。地球温暖化の主な要因である二酸化炭素(CO2)をはじめとした温室効果ガスの濃度をこれ以上増やさないためには、社会全体の排出構造を見直し、エネルギーの使い方や輸送手段、産業活動の在り方を根本から変革していく必要があります。特に物流領域では、トラック輸送による化石燃料の使用が大きな排出源とされており、ネットゼロ実現の鍵を握ります。
国際的な潮流と日本政府・企業の対応方針(2050年目標など)
世界的には、2015年に採択されたパリ協定を契機に、「2050年までにネットゼロを実現する」という目標が多くの国で共有されるようになりました。EUをはじめとした先進国を中心に、再生可能エネルギーの導入や電動化の推進、排出量取引制度の整備が進められています。日本もこの流れに沿って、2020年に「2050年カーボンニュートラル宣言」を打ち出し、政府全体で脱炭素社会の実現に向けた取り組みを本格化させています。
具体的には、グリーン成長戦略の中で電力部門の再エネ比率の引き上げや、電動車の普及、CO2排出量の多い産業へのイノベーション支援などが盛り込まれています。物流領域でも、EVトラックや水素燃料トラックの導入、モーダルシフト、共同輸配送などが推奨されており、企業単位でも中長期的な排出削減目標を掲げる動きが活発化しています。ネットゼロの実現には国の政策だけでなく、企業の自発的な取り組みと技術革新が不可欠です。物流領域も例外ではなく、持続可能な輸送モデルの構築が急務となっています。
なぜ物流領域にネットゼロ対応が求められるのか
ネットゼロへの取り組みは、もはや一部の業界のある部門に限られた話ではなく、あらゆる業界のあらゆる部門が当事者として対応を迫られています。中でも物流領域は、サプライチェーン全体に関わる重要なポジションにあることから、その責任の重さが年々増しています。ここでは、なぜ物流領域がネットゼロに取り組む必要があるのか、その背景を具体的に見ていきましょう。
サプライチェーン全体での排出責任が問われている
近年、温室効果ガスの排出は企業単体の問題ではなく、製品やサービスが生まれてから消費者に届くまでのサプライチェーン全体における排出量が問われるようになっています。たとえば製造業では、自社工場の排出だけでなく、原材料の調達や製品の輸送段階まで含めて、環境負荷の総量を評価するのが一般的になりつつあります。こうした背景の中で、物流も「排出源の一部」としての責任を免れなくなっており、ネットゼロ実現に向けた対応が求められています。
Scope3の削減要求
このようなサプライチェーン全体の排出削減を進めるうえで、近年注目されているのが「Scope3」と呼ばれる間接排出の管理です。Scope3とは、企業が直接コントロールできない範囲、つまり原材料の調達や輸送、販売、使用、廃棄などに関わる温室効果ガスの排出を指します。多くの荷主企業がこのScope3削減に真剣に取り組み始めており、輸送や保管といった物流過程での排出量についても、具体的なデータ提供や削減の取り組みが求められるようになっています。これにより、物流事業者も単なる委託先ではなく、環境対応のパートナーとしての役割が期待されています。
Scope3 カテゴリー4とは?上流の輸送・配送におけるCO2排出の可視化と対策
気候変動対…
2025.12.22
Scope3 カテゴリー9とは?対象範囲から算定・削減方法までわかりやすく解説
企業のサス…
2025.12.22
ネットゼロ対応が今後の取引条件・競争力に直結する
加えて、ネットゼロへの取り組みは単なるCSRの一環ではなく、今や事業継続や競争力に直結する要素となりつつあります。環境への配慮が取引先選定の条件に含まれるケースが増え、脱炭素への具体的な方針や行動を示せない企業は、サプライヤーとして選ばれにくくなるリスクが生じています。また、投資家や金融機関からのESG(環境・社会・ガバナンス)評価においても、排出削減の進捗が重視される時代です。物流領域にとっても、こうした流れを受けてネットゼロ対応を進めることは、将来的な取引機会の拡大やブランド価値の向上にもつながる重要な経営課題といえるでしょう。
ネットゼロに向けた物流領域の施策
ネットゼロの実現に向けて、物流領域でもさまざまな取り組みが進められています。トラックの排出ガス削減はもちろん、輸送手段の見直しやエネルギー源の転換など、多角的なアプローチが求められます。ここでは、具体的にどのような施策が取り入れられているのか、代表的なものを見ていきましょう。
EV・FCV導入による走行時の排出削減
まず注目されるのが、配送車両の電動化です。従来のディーゼル車に比べて、EV(電気自動車)やFCV(燃料電池車)は走行時にCO2を排出しないため、都市部でのラストワンマイル配送を中心に導入が進められています。また、自治体によってはEV導入に対する補助金制度が用意されており、初期投資のハードルが下がりつつある点も後押しとなっています。将来的には長距離輸送への対応も視野に入れた車種開発が進められており、業界全体での電動化が加速しています。
輸送のモーダルシフト(鉄道・船舶活用)
長距離輸送においては、CO2排出量の少ない鉄道や船舶への切り替え、いわゆるモーダルシフトの推進が有効とされています。とくに鉄道貨物はトラック輸送に比べてエネルギー効率が高く、温室効果ガスの排出量を大幅に抑えることができます。近年では、大手物流事業者を中心に鉄道との接続拠点を整備したり、輸送スケジュールを鉄道に合わせて最適化したりする動きが活発化しています。都市間や港湾エリアを結ぶルートでは、モーダルシフトがネットゼロ実現の重要な選択肢となっています。
ルート最適化・積載効率向上による排出削減
車両の運行効率を高めることも、排出削減に直結します。最新の配車システムを活用することで、最短ルートの自動算出やリアルタイムでの配送指示が可能となり、不要なアイドリングや遠回りを防ぐことができます。また、積載効率を高めることも大切で、空車率を下げる工夫や、共同輸配送の仕組みづくりなどが各社で進められています。これらの工夫により、走行距離や稼働車両数を抑えながら、より少ないエネルギーで多くの荷物を運ぶことができるようになります。
再エネ電力への切り替え(倉庫や充電設備)
走行時の排出削減だけでなく、物流拠点となる倉庫や配送センターで使用する電力の見直しも重要です。再生可能エネルギー由来の電力を活用することで、施設運営に伴う間接排出(Scope2)の削減が可能となります。特にEVの充電ステーションや大型冷蔵倉庫など、電力消費が大きい設備においては、太陽光発電やグリーン電力への切り替えが進められています。エネルギーの地産地消や自家消費型の設備投資も注目されており、施設運営と環境対策を両立させる新たな物流モデルの構築が求められています。

ネットゼロ実現に必要な「見える化」と「仕組みづくり」
ネットゼロを本気で目指すには、「どこでどれだけ排出しているのか」を正確に把握し、それに基づいて削減策を設計・実行していく必要があります。つまり、排出量の「見える化」と、それを支える社内外の「仕組みづくり」が不可欠です。特に物流領域では、輸送手段や荷物の流れが複雑である分、独自の工夫が求められます。ここでは、実現に向けた基盤づくりのポイントを見ていきましょう。
GHG排出量の可視化と算定方法(物流特有のポイント)
まず最初のステップとなるのが、温室効果ガス(GHG)排出量の可視化です。物流領域では、走行距離、燃料消費量、荷物重量、配送ルートなど、多くの変数が排出量に影響します。これらを正確に算定するには、国や業界団体が定めた算定ガイドラインを参照しながら、実態に合ったデータ収集体制を整える必要があります。協力先の物流事業者にデータ収集を含めることが求められるため、サプライチェーン全体での協力が重要になります。
GHGプロトコルとは?目的や背景、算定方法、報告の手順、Scope1~3の算定方法、影響を解説
GHGとは「Greenhouse G…
2025.12.22
Scope1〜3への対応と優先順位の整理
排出量を把握する際には、「Scope1(自社からの直接排出)」「Scope2(購入電力などの間接排出)」「Scope3(他社活動に由来する間接排出)」という3つの分類に基づいて整理するのが一般的です。物流においては、自社車両による排出がScope1、倉庫などの電力消費がScope2、協力会社を通じた輸送がScope3に該当します。Scope3は把握が難しい反面、排出量全体の中で大きな比率を占めることが多く、早期からの取り組みが欠かせません。まずはScope1と2の削減策を優先しつつ、徐々にScope3まで範囲を広げていく段階的な対応が現実的です。
PLM・IoT・運行管理システムを使ったデータ活用
こうした可視化や管理の基盤を支えるのが、テクノロジーの活用です。たとえばPLM(Product Lifecycle Management:製品ライフサイクル管理)やIoTセンサー、運行管理システムを組み合わせることで、走行ルートや積載状況、アイドリング時間などをリアルタイムで把握することが可能になります。これにより、無駄の発見や改善点の特定が容易になり、具体的な削減アクションにつなげることができます。また、収集したデータを社内で共有・分析する体制を整えることで、現場と経営層が一体となってネットゼロ実現に向けたPDCAを回していくことができます。
ネットゼロ達成に向けたステップ
物流領域でネットゼロを達成するためには、単発の施策ではなく、戦略的かつ継続的な取り組みが求められます。現実的なゴール設定から、日々のオペレーション改善、そして関係者との連携に至るまで、多層的に物事を進めていく必要があります。ここでは、実際に企業が取り組むべきステップを順を追って見ていきましょう。
中長期目標の設定と社内コミットメントの明確化
まず重要なのは、いつまでにどの程度の排出削減を目指すのかという中長期的な目標を明確にすることです。これにより、社内の方針が一本化され、具体的な計画や予算配分にも説得力が生まれます。また、トップマネジメントによるコミットメントの表明は、現場の意識改革や社内文化の醸成にもつながります。単なるスローガンではなく、日々の業務に落とし込まれる実行可能な目標設定がカギとなります。
削減→効率化→代替手段→オフセットの順で取り組む
ネットゼロへの道筋は、排出の「削減」を起点とした段階的なアプローチが基本です。まずは無駄な排出を減らすことから始め、次に輸送効率やエネルギー効率の向上を目指します。そのうえで、電動車や再エネといった代替手段への切り替えを検討し、どうしても削減しきれない分はカーボンクレジットなどで相殺するという順序が理想的です。この流れに沿って取り組むことで、コストと効果のバランスを取りながら、実効性のあるネットゼロ経営が可能になります。
カーボンオフセットとは?物流領域に求められる脱炭素対応を解説
気候変動対…
2025.06.23
ステークホルダー(物流事業者・行政・地域)との連携がカギ
荷主が自社単独でネットゼロを実現するのは困難であり、物流事業者、行政、地域社会などとの連携が不可欠です。物流事業者との間では、輸送ルートの見直しや配送車両の電動化などを通じて排出削減の協力体制を築くことが求められます。また、地方自治体との連携によりEV充電インフラの整備や補助金活用が進み、地域住民への理解や協力を得ることで、持続可能な物流ネットワークの構築が可能になります。ネットゼロは業界全体、社会全体で進めるべきテーマであり、そのための対話と協働の姿勢が成功の鍵を握ります。
ネットゼロ導入のハードルと現場での課題
ネットゼロに向けた取り組みが加速する一方で、実際に現場で対応を進めるには多くの障壁があるのも事実です。輸送を依頼する物流事業者では、コストや人材、既存設備の制約など、さまざまな現実的な課題に直面しています。ここでは、現場レベルでよく挙がる課題とその対応策の方向性を確認していきましょう。
車両・設備更新にかかるコスト
もっとも大きな課題のひとつが、物流事業者におけるEVやFCVといった環境対応車両の導入や、自社・委託先倉庫における再エネ設備の導入にかかる初期投資の大きさです。従来の内燃機関車に比べて、電動車両は購入価格が高く、充電インフラの整備も必要です。また、再エネ導入に向けた倉庫や施設の改修にも多額のコストがかかることから、中小規模の事業者にとっては負担が大きく、計画的な導入が求められます。経済的な制約は、ネットゼロ推進のスピードに直結するため、事業継続とのバランスをとりながら進めることが不可欠です。
ドライバーや現場の運用負荷と教育
設備や車両を入れ替えただけでは、ネットゼロは実現できません。実際にそれを使いこなす現場のドライバーや作業スタッフの理解と対応力が不可欠です。たとえば、EV特有の運転感覚や充電のタイミング、ルート計画における制約など、新たな知識が求められる場面は少なくありません。また、IoT機器やデジタルツールを活用した運行管理を取り入れるには、一定のITリテラシーも必要となります。こうした変化に対応できるよう、教育体制の整備や、現場目線でのオペレーション改善が求められます。
補助金や支援制度を活用した段階的導入の考え方
すべての取り組みを一度に導入するのは現実的ではありません。そこで有効なのが、行政や自治体が提供する補助金・助成制度を活用した段階的な導入です。たとえばEV車両の導入補助や、再エネ設備への支援金、共同配送拠点への設備投資支援など、地域や施策によってさまざまな制度があります。これらを活用することで、初期投資のハードルを下げながら、リスクを抑えて徐々に脱炭素化を進めることが可能になります。また、支援制度の活用をきっかけに、経営層の理解を促進したり、社内での優先順位を明確にしたりする効果も期待できます。
まとめ
ネットゼロは、環境保全だけでなく、今後の企業価値や競争力にも直結する重要なテーマです。物流領域においても、排出量の可視化、電動化や輸送手段の見直し、さらにはデータ活用やステークホルダーとの連携など、取り組むべき領域は多岐にわたります。一方で、導入にはコストや人材の課題も伴うため、現場のリアルな状況に即した段階的な取り組みが必要です。
環境と経済性の両立という難しいテーマに向き合いながらも、一歩ずつ具体的な行動に移していくことが、業界全体の持続可能性を高め、次世代につながる物流の形をつくることにつながります。企業ごとの規模や課題に応じたアプローチを模索しつつ、長期的な視点でネットゼロを目指していくことが、今後ますます重要になっていくでしょう。
なお、Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流DXツールMOVO(ムーボ)と、物流DXコンサルティングサービスHacobu Strategy(ハコブ・ストラテジー)を提供しています。
MOVOは燃費法を用いて、Scope3のカテゴリー4(上流の輸配送)・カテゴリー9(下流の輸配送)の可視化が可能です。
トラック予約受付サービス(バース予約システム) MOVO Berth
MOVO Berth(ムーボ・バース)は、物流拠点におけるトラックの入退場を管理するシステムです。
入退場の予約時に出荷元住所を入力することで、出荷元→納品先(自拠点)までのトラックの走行距離を把握できます。入荷車両は出荷元が手配することが多いため、一般的にカテゴリー4の可視化は難しいですが、MOVO Berthの活用によって走行距離の実績からCO2排出量を計算いただけます。
動態管理サービス MOVO Fleet
MOVO Fleet(ムーボ・フリート)は、運送を委託している会社の位置情報や走行ルートを可視化・分析できるシステムです。
「走行履歴」画面の下部に実際に走行したルートのCO2排出量が表示されます。日報機能にて、一日分の走行距離から算出されるCO2排出量をダウンロードすることも可能です。店舗配送などのカテゴリー9可視化におすすめです。
配車受発注・管理サービス MOVO Vista
MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、運送を委託している会社への配送依頼をデジタル上で行うシステムです。
配送依頼時に出荷元→納品先の住所を入力することにより、走行距離とCO2排出量が算出されます。幹線輸送などのカテゴリー9可視化におすすめです。
また、CO2排出量の削減には、Hacobu Strategyがお力添えできます。
物流DXコンサルティング Hacobu Strategy
共同輸配送やバックホールの活用など、トラックのシェアリングを行うことで、カテゴリー4・9の削減が可能です。共同輸配送やバックホールを実行するには、データの分析や戦略の立案など、物流における専門知識が必要になります。Hacobu Strategyは、物流DXの戦略、導入、実行まで一気通貫で支援します。
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主
























