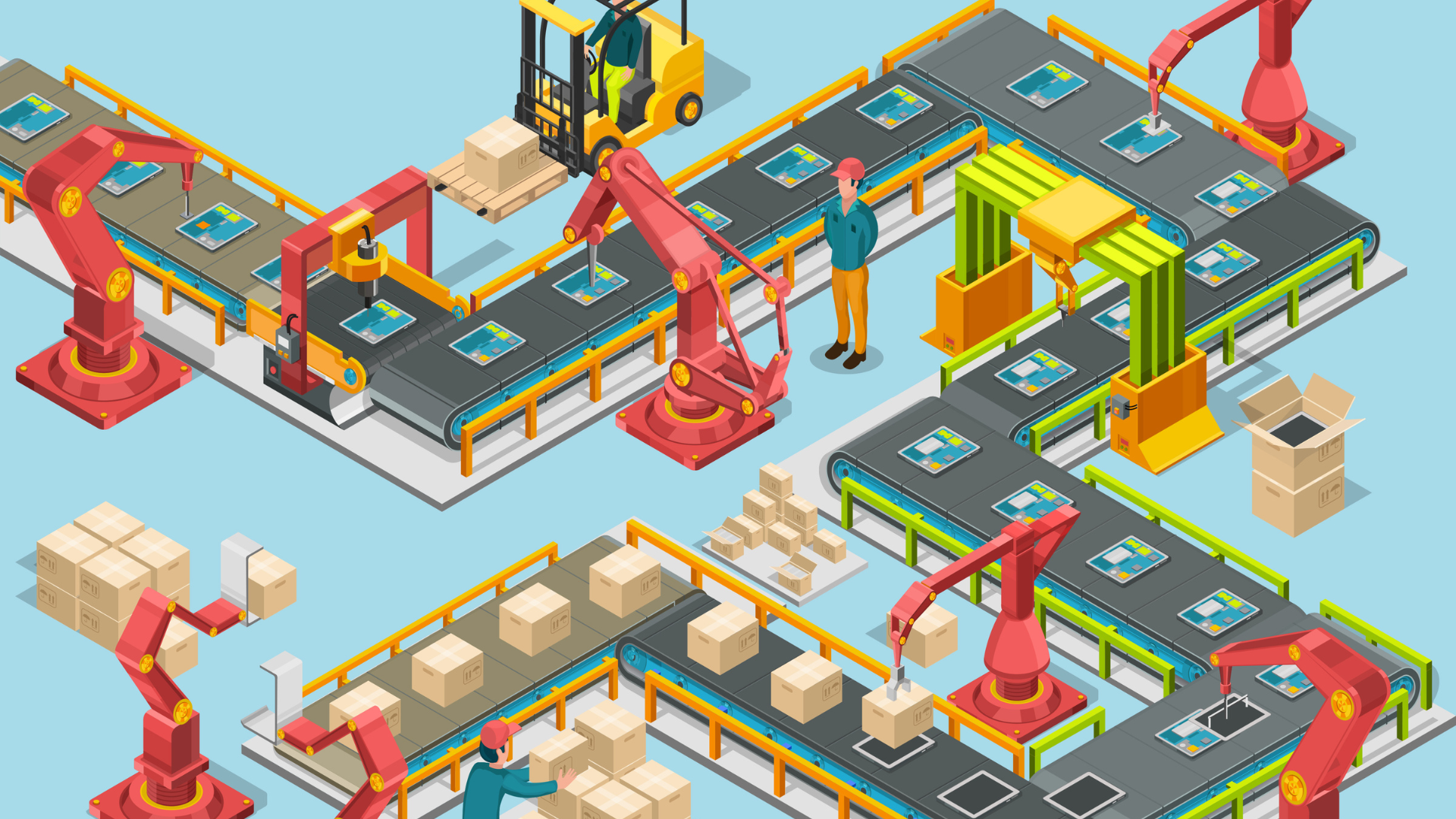Scope3 カテゴリー9とは?対象範囲から算定・削減方法までわかりやすく解説

企業のサステナビリティ推進が求められる中で、「温室効果ガス排出量の見える化」は多くの企業にとって喫緊の課題となっています。特に注目されているのが、サプライチェーン全体にわたる排出量を対象とした「Scope3」の取り組みです。その中でも「カテゴリー9」は、製品の輸送に関する排出量を扱う重要な領域であり、物流を含む多くの領域で具体的なアクションが求められています。
本記事では、Scope3 カテゴリー9の定義や対象範囲から、排出量の算定方法、そして削減に向けた実践的な取り組みなどについて、物流DXパートナーのHacobuが解説します。
目次
Scope3 カテゴリー9とは
企業が持続可能な社会に貢献するうえで避けて通れないのが、温室効果ガス(GHG)の排出量管理です。中でもScope3 カテゴリー9は、製品の輸送・配送に伴う排出を扱う項目として、物流やサプライチェーンを抱える多くの企業にとって重要な指標となっています。本章では、Scope3 カテゴリー9の基本的な考え方と、その意義について詳しく見ていきます。
温室効果ガス排出の3つのスコープとScope3の役割
企業の温室効果ガス(GHG)排出量は、主に「Scope1」「Scope2」「Scope3」の3つに分類されます。Scope1は自社が直接排出する温室効果ガス、Scope2は購入した電力や熱などの使用による間接排出です。そしてScope3は、自社の活動に関連するが、自社以外のところで発生する間接排出を指します。
Scope3はさらに15のカテゴリに細分化されており、その中でも「カテゴリー9」は製品が消費者に届けられるまでの輸送・配送過程における排出量を対象としています。サプライチェーン全体の最適化が求められる現在、Scope3の把握は企業のサステナビリティ戦略において不可欠な要素です。
Scope3とScope1・Scope2との違い
Scope1・Scope2は、自社の管理下にある排出源を対象とするのに対し、Scope3はサプライチェーン全体、つまり自社の外で発生する排出までを含みます。この違いにより、Scope3の算定や管理は難易度が高くなる傾向がありますが、それだけに環境インパクトへの影響も大きく、近年ではより注目が集まっています。
たとえば、自社工場から排出されるガスはScope1、購入した電力による排出はScope2に分類されます。一方、製品を運ぶ外部の物流業者による排出などはScope3に該当します。Scope3を適切に把握することで、企業はバリューチェーン全体を通じた排出削減の施策を打ちやすくなります。
カテゴリー9は「消費者向けの輸送」
Scope3 カテゴリー9は、企業が販売した製品を消費者のもとに届けるまでの輸送・配送によって発生する排出量を対象としています。具体的には、外部の配送業者や物流パートナーを通じて行われるトラック、鉄道、航空などの輸送活動が該当します。
このカテゴリーでは、製品が企業の倉庫を出てから小売店や消費者の手元に届くまでの「下流物流」が対象です。たとえば、製造業の倉庫から3PL(サードパーティ・ロジスティクス)を通じて小売業の物流センターに輸送されるケースや、ECサイトで販売された商品が個人宅に配送されるケースなどが代表例です。
Scope3 カテゴリー9が注目される理由
近年、ラストマイル配送の需要増加や、EC市場の拡大に伴い、製品の配送過程で発生するGHG排出量が企業の環境負荷に占める割合を大きくしています。これにより、Scope3 カテゴリー9の排出量管理は、持続可能な物流の実現において重要性を増しています。
また、消費者や投資家の環境意識の高まりにより、サプライチェーン全体の排出量を開示する企業が増えてきました。Scope3 カテゴリー9はその中でも比較的取り組みやすく、改善効果が目に見えやすいため、ESG経営を進めるうえでも初期のアクションポイントとして注目されています。
カテゴリー4とカテゴリー9の違い
Scope3の中にはカテゴリー4「上流の輸送・配送」も存在します。これは、原材料や部品などを調達する際の輸送過程で発生する排出量を指します。一方、カテゴリー9はその逆で、製品が完成してから最終消費者に届くまでの「下流の輸送・配送」を対象とします。
この2つは対象範囲が似ているため混同されやすいのですが、「どの地点からどの地点までか」を明確にすることで区別できます。カテゴリー4は調達・仕入れの輸送、カテゴリー9は販売後の輸送という位置づけです。それぞれの排出源を正しく分類することが、正確なGHG算定には欠かせません。
Scope3 カテゴリー9の対象範囲
Scope3 カテゴリー9を正確に理解・算定するには、どのような輸送・配送活動が対象に含まれるのか、また含まれないのかを明確にしておくことが重要です。ここでは、カテゴリー9に該当するケースと、該当しないケースを具体的に解説します。
カテゴリー9に当てはまるケース
Scope3 カテゴリー9に該当するのは、主に製品が完成した後、企業の施設や倉庫を出発し、顧客や消費者の手元に届くまでの輸送・配送活動です。これには、外部の物流事業者を活用した輸送が含まれ、トラック、鉄道、航空便、船舶などを利用するケースが想定されます。
たとえば、個人宅への配送にトラックを用いるケースや、幹線輸送に鉄道を用いるケース(モーダルシフト)は、すべてカテゴリー9の対象となります。
カテゴリー9に当てはまらないケース
一方で、Scope3 カテゴリー9に当てはまらないケースとしては、自社が所有・運用している車両による輸送活動が挙げられます。これらは企業の直接排出にあたるため、Scope1として扱われます。また、製品の原材料や部品を調達する際の輸送はカテゴリー4に分類されるため、カテゴリー9には含まれません。
加えて、企業の施設内で行われる製品の移動や、製造工程内の内部搬送などもカテゴリー9の対象外です。Scope3 カテゴリー9では「販売後の外部向け輸送」に限定されるため、活動範囲をしっかり見極めることが重要です。
Scope3 カテゴリー9の算定方法とポイント
Scope3 カテゴリー9における排出量の正確な算定は、削減施策の実効性を高めるうえでも欠かせません。ここでは、基本的な算定手法から、輸送手段別のガイドライン、さらには実務で見落としがちなポイントまで解説します。
基本算定式「トンキロ法」とその使い方
Scope3 カテゴリー9の排出量を算定する基本的な方法として広く採用されているのが「トンキロ法」です。これは、輸送された貨物の重量(トン)と輸送距離(キロメートル)を掛け合わせ、その値に排出係数を掛けることで排出量を求めるシンプルな方法です。
この方法は比較的計算が容易で、特に大量輸送を行う企業にとって実用的です。ただし、正確な輸送距離や貨物重量の把握が必要となるため、事前のデータ収集と記録の整備が算定精度を左右します。
輸送シナリオ構築と冷媒漏えい対策のポイント
実際の輸送環境は一律ではなく、さまざまなルートや手段が組み合わさっています。そのため、排出量の算定には現実に即した「輸送シナリオ」の構築が重要です。たとえば、複数の輸送手段を組み合わせた場合は、それぞれの輸送区間ごとに個別に算定し、合算する必要があります。
また、冷凍・冷蔵輸送を行っている場合には、冷媒の漏えいも見逃せない排出源となります。特にフロン類は温室効果が高いため、使用量やメンテナンス状況に応じた排出量の加算が必要です。冷媒に関するデータも、シナリオと合わせて整理しておくと算定の抜け漏れを防げます。
輸送手段別の排出量算定ガイドライン(トラック・鉄道・航空など)
輸送手段によって排出特性が異なるため、それぞれに適した算定方法を選ぶことが求められます。たとえば、トラック輸送では燃料消費量が主要な指標となりますが、鉄道輸送では電力使用量、航空輸送では飛行距離や搭載率が算定に影響を及ぼします。
環境省や国際的な算定ガイドラインでは、これらの手段ごとに推奨される排出係数や計算式が提示されています。こうしたガイドラインを参照しながら、自社の輸送実態に即したアプローチをとることが、実効性の高い排出量把握につながります。
排出係数と燃料使用量の扱い方
排出量を計算するうえで欠かせないのが「排出係数」です。これは、特定の燃料やエネルギー源が使用された際に排出されるCO2の量を示す指標であり、正確な係数を使用することが算定の信頼性を高めるポイントになります。
燃料使用量については、輸送手段ごとに異なる記録形式や単位が使われていることが多いため、事前にフォーマットを統一するか、単位換算のルールを整えておくことが重要です。また、データが不足している場合には、業界平均や標準値を活用することもできますが、その際は仮定条件を明示し、改善の余地があることを認識しておくとよいでしょう。
Scope3 カテゴリー9における排出削減の取り組み
Scope3 カテゴリー9の排出量を正しく把握したあとは、具体的な削減アクションに取り組むフェーズに入ります。このセクションでは、企業が実際に取り組むことのできる排出削減施策について、視点別に紹介していきます。
効率的な輸送手段とエコ配送
輸送手段の選定を見直すことで、Scope3 カテゴリー9の排出量を大幅に削減できるケースは少なくありません。たとえば、従来トラックで行っていた中長距離輸送を鉄道や船舶に切り替える(モーダルシフト)ことで、単位あたりのCO2排出を抑えることが可能になります。また、ハイブリッド車や電動車両の活用など、燃費効率の良い輸送手段へのシフト(エコ配送)も効果的です。
積載率向上や再生エネルギーの活用
配送ルートの最適化や、荷物の集約によって積載効率を向上させることで配送回数を削減する企業も増えています。パレット積みや梱包設計の工夫、共同輸配送などによって無駄なスペースを減らす工夫が求められます。
さらに、倉庫や物流センターにおける再生可能エネルギーの活用も、Scope3排出量の削減に貢献します。たとえば、倉庫での積み替えや一時保管の際に使用する電力を太陽光発電などでまかなう取り組みは、間接的に物流全体の環境負荷を軽減します。
排出量の見える化とデータ活用による改善
削減を実現するためには、まず現状を把握することが前提となります。そこで重要になるのが排出量の「見える化」です。物流工程における各ステップの排出量を可視化し、どこに削減余地があるのかを分析することで、最適な対策を講じることができます。
最近では、CO2排出量をリアルタイムでトラッキングするシステムや、ブロックチェーンを活用して輸送データの信頼性を高める仕組みなども登場しています。こうしたテクノロジーを活用することで、定量的なモニタリングとPDCAサイクルの高速化が可能となり、継続的な改善活動につながります。
Scope3 カテゴリー9の排出量削減事例
ここでは、Scope3 カテゴリー9において先進的な取り組みを実施している企業の事例を紹介します。(記事公開時点の情報です。)
佐川急便|モーダルシフトによるCO2排出量の大幅削減
佐川急便は、環境負荷の低減とトラックドライバーの労務改善を両立する施策として、輸送手段のモーダルシフトを積極的に推進しています。具体的には、2018年から東京〜苅田(福岡県)間でフェリーを活用した海上輸送を導入し、従来のトラック輸送から大きく転換しました。さらに2021年からは横須賀〜新門司間の新たな航路も活用し、より広範囲なモーダルシフトを実現しています。
この取り組みにより、2020年度の東京〜苅田間では約361トン(約55%)のCO2排出削減を達成。横須賀〜新門司間においても、わずか2カ月間で約372トン(約49%)の削減効果が確認されました。これらの成果により、佐川急便は「モーダルシフト取り組み優良事業者賞(有効活用部門)」を受賞しています。
また、モーダルシフトによって輸送時間の短縮も実現し、営業所への到着時間の前倒しなどリードタイムの短縮にもつながっています。環境対策だけでなく、BCP(事業継続計画)や業務効率化の観点からも高く評価されている事例です。
【佐川急便】第8回モーダルシフト取り組み優良事業者賞 有効活用部門にて「モーダルシフト取り組み優良事業者賞」を受賞
キリンビバレッジ|共同輸送と再エネ活用によるScope3削減の実践
キリンビバレッジは、2050年までにバリューチェーン全体でGHG排出量ネットゼロを目指す中、物流領域でもScope3削減に向けた具体的な施策を進めています。特に、他社との共同輸配送やモーダルシフトの導入によって、輸送効率の向上と排出削減の両立を実現しています。
たとえば、他飲料メーカーと連携し、北海道や北陸エリアでの鉄道コンテナを使った共同輸送を展開。この取り組みによって、年間でおよそ1万台分のトラック輸送を代替し、CO2排出量を約2,700トン削減する効果が確認されています。
さらに、物流拠点における再生可能エネルギーの活用も積極的に進めています。キリンビールのすべての工場・営業拠点では、購入電力の100%を再エネ由来の電力に切り替えており、物流施設の屋根を利用した太陽光発電の導入も進行中です。
これらの多面的な取り組みによって、キリンビバレッジはScope3カテゴリー9の削減にとどまらず、バリューチェーン全体での脱炭素化を推進しています。
MCアグリアライアンス|排出量の可視化と削減の第一歩
MCアグリアライアンスは、三菱商事とJA全農によって設立された農業資材・肥料の専門商社です。国内外に広がる複雑な物流網を抱える中、Scope3を含む排出量の可視化に課題を感じていました。そこで排出量可視化ツールの導入により、MCアグリアライアンスでは自社のGHG排出量を構造的に把握することが可能となりました。特に、従来はブラックボックスになりがちだったカテゴリー9を含む物流由来の排出量についても、輸送距離や手段、荷姿に応じてデータを分解・分析できるようになり、削減の優先順位を明確にすることができました。
このような可視化に基づき、同社では今後、より効率的な輸送手段への切り替えや、共同輸送などの具体的なアクションを進めていく予定です。可視化から改善への道筋を描くMCアグリアライアンスの取り組みは、Scope3 カテゴリー9対応をこれから始める企業にとっても参考になる事例といえます。
スコープ3の算定が難しい理由とは?Terrascopeの解決策・企業事例
まとめ
Scope3 カテゴリー9は、製品の配送に伴う温室効果ガス排出を対象としたカテゴリであり、サステナビリティ経営においてますます重要性を増しています。
本記事では、その定義や範囲、排出量の算定方法、削減に向けた具体的な取り組みまでを紹介しました。特に、輸送手段の見直しや積載率の改善、排出量の可視化といった施策が効果的であり、すでに多くの企業で成果が見られています。
Scope3 カテゴリー9の対応は、環境対策であると同時に、業務の効率化や競争力向上にもつながる重要な取り組みです。物流の現場を見直す第一歩として、ぜひ本記事の内容を活用してみてください。
なお、Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流DXツールMOVO(ムーボ)と、物流DXコンサルティングサービスHacobu Strategy(ハコブ・ストラテジー)を提供しています。
MOVOは燃費法を用いて、Scope3のカテゴリー4(上流の輸配送)・カテゴリー9(下流の輸配送)の可視化が可能です。
トラック予約受付サービス(バース予約システム) MOVO Berth
MOVO Berth(ムーボ・バース)は、物流拠点におけるトラックの入退場を管理するシステムです。
入退場の予約時に出荷元住所を入力することで、出荷元→納品先(自拠点)までのトラックの走行距離を把握できます。入荷車両は出荷元が手配することが多いため、一般的にカテゴリー4の可視化は難しいですが、MOVO Berthの活用によって走行距離の実績からCO2排出量を計算いただけます。
動態管理サービス MOVO Fleet
MOVO Fleet(ムーボ・フリート)は、運送を委託している会社の位置情報や走行ルートを可視化・分析できるシステムです。
「走行履歴」画面の下部に実際に走行したルートのCO2排出量が表示されます。日報機能にて、一日分の走行距離から算出されるCO2排出量をダウンロードすることも可能です。店舗配送などのカテゴリー9可視化におすすめです。
配車受発注・管理サービス MOVO Vista
MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、運送を委託している会社への配送依頼をデジタル上で行うシステムです。
配送依頼時に出荷元→納品先の住所を入力することにより、走行距離とCO2排出量が算出されます。幹線輸送などのカテゴリー9可視化におすすめです。
また、CO2排出量の削減には、Hacobu Strategyがお力添えできます。
物流DXコンサルティング Hacobu Strategy
共同輸配送やバックホールの活用など、トラックのシェアリングを行うことで、カテゴリー4・9の削減が可能です。共同輸配送やバックホールを実行するには、データの分析や戦略の立案など、物流における専門知識が必要になります。Hacobu Strategyは、物流DXの戦略、導入、実行まで一気通貫で支援します。
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主