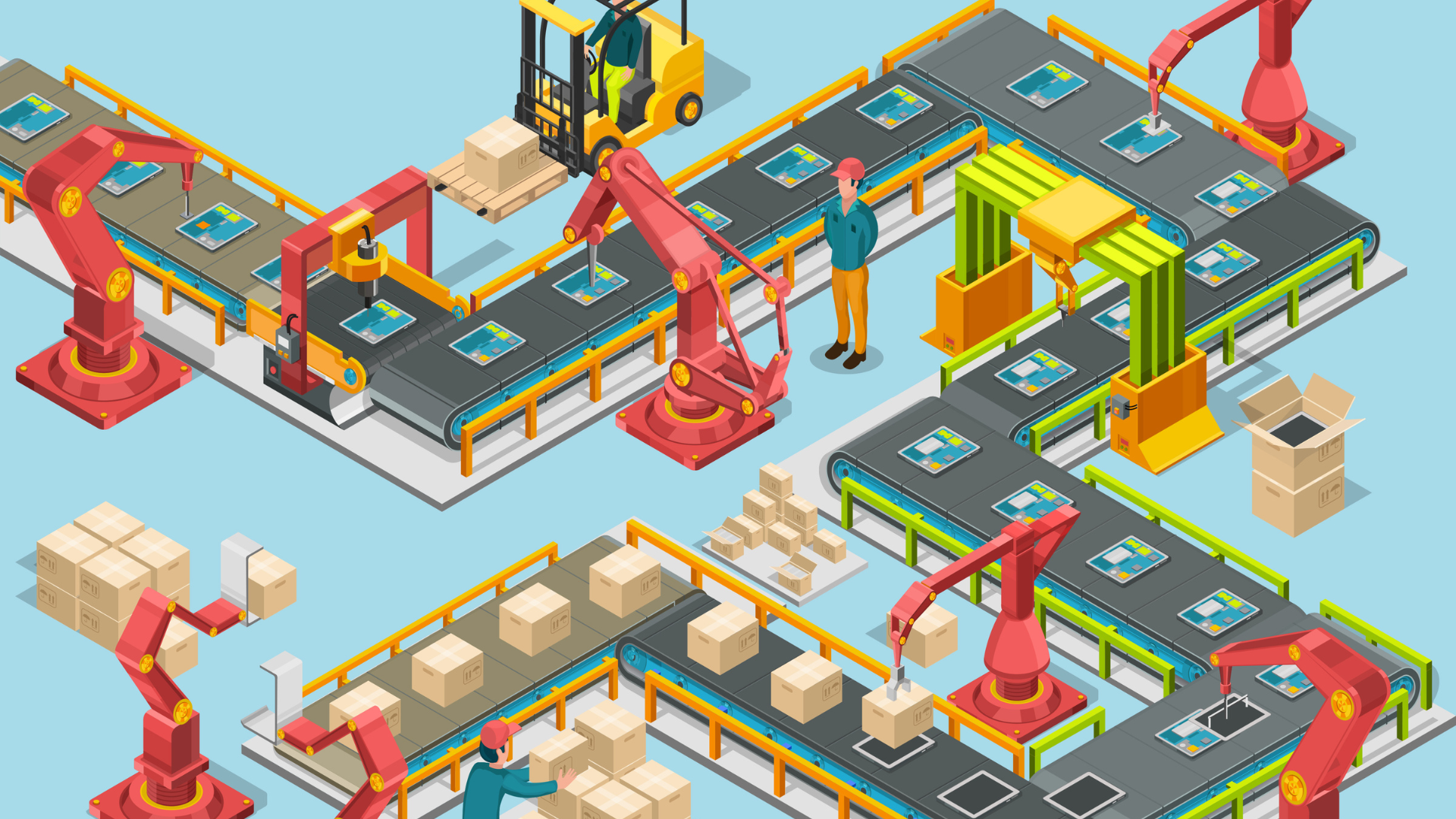稼働率とは?悪化する原因や向上させる対策やポイントを解説。物流における稼働率の経済を理解しよう

物流領域において「稼働率」は非常に重要な指標です。トラックや倉庫、労働力などのリソースを最大限に活用して効率的に運用できれば、企業のコスト削減や収益向上に直結します。こうした「稼働率の向上によってコストが低減し、利益が増大する」という原則を「稼働率の経済」と呼ぶことがあります。
本記事では、稼働率の経済の基本概念から、物流領域における具体的な適用例、そして企業がどのように稼働率を最適化するとよいかについて、物流DXパートナーのHacobu が解説します。
なお、Hacobuでは物流DXの戦略、導入、実行まで一気通貫で支援する物流DXコンサルティング Hacobu Strategy を提供しています。物流業務の改善にお悩みがありましたら、以下をクリックしてご覧ください。
目次
稼働率の経済とは
稼働率とは
稼働率とは、設備や車両、労働力などのリソースが実際にどれだけ稼働しているかを示す指標です。一般的には「稼働可能な時間のうち、実際に稼働している時間の割合」を指し、物流領域ではトラックの積載効率、工場や倉庫の設備使用率、作業員の稼働状況といった観点で重要視されます。
稼働率の経済とは
稼働率の経済とは、設備や労働力、輸送能力などのリソースを最大限に活用し、固定費の相対的な負担を下げることでコスト効率を高める考え方です。
物流領域における稼働率の経済の例
たとえば、1台のトラックが半分の積載効率で運行する場合と、満載で運行する場合を比較すると、車両リース代や人件費などの固定費に大差はありません。しかし、輸送量が増えれば固定費の1単位あたりの負担が減り、コスト効率が向上します。
これは工場や倉庫でも同様です。24時間稼働する倉庫と日中のみ稼働する倉庫では、固定費の回収効率に大きな差が出ます。より高い稼働率を維持できれば、物流コストを削減し、利益率を高めることが可能です。
規模の経済との違い
稼働率の経済とよく混同される概念に規模の経済があります。
規模の経済とは、生産量や取扱量を増やすことで単位あたりのコストを下げる効果を指します。一方、稼働率の経済は、既存の設備やリソースを最大限活用することでコストを下げるという点が特徴です。
| 稼働率の経済 | 規模の経済 | |
| 定義 | 既存のリソースの活用率を高めてコストを下げる | 生産・取扱量の増加によってコストを下げる |
| 主な手段 | 稼働時間の延長、積載率の向上、ダブルシフトなど | 物流拠点の統合、大量仕入れ、設備の大型化など |
| 具体例 | トラックの積載効率向上、倉庫の稼働時間延長 | 大規模物流センターの活用、発注ロットの増加 |
稼働率と生産性の違い・関係性
「稼働率」と「生産性」は混同されることが多いですが、実際には異なる視点の指標です。
- 稼働率:設備やリソースが「どれくらいの時間、動いているか」を示す
- 生産性:ある一定のリソース・時間から「どれだけの成果を生み出せるか」を示す
稼働率が高いからといって、生産性も高いとは限らない
たとえば、A工程とB工程に能力差がある場合、A工程がフル稼働していてもB工程がボトルネックなら、全体としての生産性は上がりません。逆に、稼働率は低くても、限られた時間で高付加価値を生み出せれば生産性は高いと言えます。
両者をバランスよく高めるためには、工程やリソース配分を俯瞰し、「どこが真のボトルネックか」を見極め、的確に対策することが重要です。
稼働率向上のために押さえておきたいKPI・指標
稼働率を改善するには、稼働率そのものに加え、複数のKPIを並行してモニタリングすると効果的です。代表的な例を挙げます。
タクトタイム (Tact Time)
製造ラインや作業ラインで「1つの製品・作業を完了するまでに必要な時間」を指します。ボトルネック工程の特定に欠かせない指標です。
スループット (Throughput)
一定時間内に処理(生産・配送)できる量を示す指標です。稼働率と併せてモニタリングすることで、稼働時間の“質”を把握できます。
在庫回転率・WIP (Work In Process) 水準
工場や倉庫でどれだけ在庫や仕掛品が滞留しているかを表します。過剰在庫がある場合は、工程能力のミスマッチなどが疑われます。
稼働時間当たりの生産量・処理量
稼働している時間1時間あたりの生産・配送量をチェックすることで、稼働率と生産性の関係をより立体的に分析できます。
設備総合効率 (OEE:Overall Equipment Effectiveness)
製造業でよく使われる指標で、稼働率・性能効率・品質率を掛け合わせて総合評価します。単に稼働時間だけでなく、品質や性能面も含めて確認できるのが特徴です。

稼働率が悪化する5つの原因と対策
現場で稼働率を意識していても、さまざまな要因が重なり合い、思うように上がらないことがあります。ここでは代表的な5つの原因と対策を解説します。
需給予測のミス
需要予測が外れると、設備や人員に余剰または不足が生じます。AIやデータ分析を活用し、繁閑差を平準化するスケジュールを組むなどの対策が有効です。
工程間の能力ギャップ
A工程とB工程で大きな能力差がある場合、ボトルネックが生じます。ラインバランシングの徹底や、ボトルネック工程への集中的な投資・人員強化が求められます。
設備故障やメンテナンス不足
設備トラブルが頻発すると稼働停止が増えます。定期メンテナンスや老朽設備の早期更新、IoTを活用した予兆保全などで対策しましょう。
作業者のスキルギャップ
多能工化が進んでいない、熟練者が不足しているなどで稼働が滞るケースがあります。作業教育や訓練、マニュアル整備、人員ローテーションなどが有効です。
情報共有・指示系統の遅延
手作業や紙ベースの連絡によるロスが大きいと、機会損失が生まれます。デジタルツールやシステム連携によるリアルタイム情報共有が欠かせません。
稼働率とコスト管理:固定費・変動費をどう捉えるか
稼働率を高める最大のメリットは「固定費の回収効率が上がる」点です。製造・物流いずれの業界でも、大半のコストは稼働量に関係なく一定発生する固定費であり、そこに燃料費や人件費などの変動費が加わります。
- 固定費の例:設備のリース代、倉庫・工場建屋の賃料、保険料、定額人件費など
- 変動費の例:原材料費、輸送における燃料費の一部、超過勤務人件費など
赤字ラインと適切なキャパシティ
稼働率が高いほど、同額の固定費を多い生産量・輸送量に分散できるため、単位あたりコストが下がります。逆に、稼働率が低いと固定費を回収しきれず赤字になるリスクがあります。
ただし、稼働率を上げようと過剰投資や過剰残業を行うと、変動費が急増して利益を圧迫する恐れもあります。固定費と変動費のバランスを見ながら、適切なラインキャパシティを設定することが重要です。
物流領域における稼働率の経済の具体例
トラックの積載率向上
トラック輸送では、積載率(車両の積載能力に対する実際の積載量)を高めることで、輸送コストを削減できます。たとえば、共同輸配送で複数の荷主の商品をまとめて運ぶなどの工夫が有効です。
工場ラインの稼働率向上
工場では生産ラインを複数シフトで24時間稼働させたり、ボトルネック工程を強化して遊休時間を減らしたりすることで、同額の設備投資からより多くの生産量を確保できます。
帰り便(回送トラック)の活用
トラックの帰り便が空荷(回送)だと、実車率が低下しコスト効率も悪化します。帰り便に荷物を積む仕組みを整えるだけでも、運行全体の稼働率が大きく向上します。
倉庫内スペースの最適化
倉庫のスペース利用率を高めると、1㎡あたりのコストを下げられます。AIを使った在庫配置の最適化やパレット管理の徹底などにより、デッドスペースを減らす施策が効果的です。

「稼働率の非経済」:ライン全体の最適化が重要
稼働率の経済を目指していても、実際には「一部の工程だけ稼働率が高い」「別の工程は低い」といったアンバランスが起き、全体が非効率になるケースがあります。
A工程・B工程の能力不一致の例
工場の生産ラインの例
たとえば、工場の生産ラインを考えてみましょう。
- A工程: 時間あたりの処理数が100
- B工程: 時間あたりの処理数が50
B工程の能力が50にとどまるなら、A工程がいくら100の能力を発揮しても、全体のキャパシティは50に制限されます。結果としてA工程の稼働率が高くても、ボトルネック解消にはならず、余剰生産による在庫コストが増える可能性もあります。
物流現場の入荷作業の例
倉庫の入荷作業をフォークリフトが1時間で100パレット処理できても、棚入れ担当が1時間で50パレットしか作業できなければ、入荷待ち在庫やフォークリフトのアイドルタイムが発生します。見かけ上は「フォークリフトが動いている」ようでも、実際の稼働率が十分活かされていない状況です。
どこに「非経済」が生まれるのか
設備・人員コストの無駄
A工程が稼働できるはずの時間や人員が遊休状態になります。
在庫・仕掛品(WIP)の増加
A工程が必要以上に生産すると、B工程で処理待ちの仕掛品が増え、在庫コストやスペースコストがかさみます。
改善投資の見誤り
「A工程は稼働率が高いし、問題ない」と誤解してボトルネックであるB工程の改善が後回しになり、全体効率が改善されない場合があります。
稼働率向上に向けたラインバランシングとボトルネック対策
以下のように稼働率の向上のためには、以下のように「部分最適の稼働率」ではなく、「全体最適の稼働率」を意識することが重要です。
ボトルネック工程の特定
各工程の処理能力やタクトタイムを計測し、どこがネックになっているのかを可視化します。
設備投資・工程改善
処理能力が不足している工程にピンポイントで設備投資や人員増強を行い、ライン全体のバランスを整えます。
作業の再分配・並列化
作業者を増やして並行処理を行う、工程を分割して複数ラインに振り分けるなど、全体負荷を均一化します。
余剰能力の有効活用
どうしても余剰が出る場合は、メンテナンスや試作などに時間を充て、遊休コストを下げる工夫が大切です。
稼働率の経済を活かすためのポイント
業務のデジタル化・自動化
人が行っていた手作業や連絡作業をデジタル化・自動化すると、アイドルタイムや伝達ロスが減り、稼働率を高めやすくなります。API連携やクラウドシステムなど、リアルタイム共有を可能にする仕組みも効果的です。
データを活用した可視化
デジタル化によって稼働率やタクトタイム、アイドルタイムなどを把握しやすくなります。可視化したデータをもとに、どこにボトルネックがあるのか、どの工程を改善すればよいのかを判断しましょう。
シェアリングの活用
共同輸配送のように、他社とリソースをシェアすることで空き時間を減らし、稼働率を向上させる方法があります。生産ラインや倉庫の一部を他社に貸し出す・共同利用するといった取り組みも注目されています。
AIの導入
AIによる需要予測を活用すれば、リソースを適切に割り当てやすくなり、稼働率が上がります。需要変動を見越して生産・物流計画を立てることで、過剰なライン負荷や不必要な仕掛品を抑えることが可能です。
まとめ
稼働率の経済は、物流領域におけるコスト削減と利益向上を実現するうえで、非常に重要な概念です。既存のリソースを最大限活用することで、規模の経済とは異なるアプローチで効率化が進められます。
- 稼働率と生産性の違いを理解し、部分最適に陥らないよう留意する
- 複数のKPI(タクトタイム、在庫回転率、OEEなど)を組み合わせて分析する
- 需給予測ミス、工程能力ギャップ、設備故障、スキル不足、情報共有の遅延など、稼働率を下げる原因を的確に把握して対策を講じる
- 固定費・変動費のバランスを意識しつつ、過剰投資や赤字ラインを回避する
- ボトルネック解消とラインバランシングにより、全体の稼働率を最適化する
物流領域では、トラック積載率向上や回送トラックの有効活用、倉庫スペースの最適化などが代表的な施策といえます。製造業でも、ボトルネック特定や工程能力の差を是正するラインバランシングが鍵を握ります。
単に稼働率を上げるだけを目指すのではなく、部分最適ではなく全体最適を考慮することが、本質的なコスト削減と利益拡大につながるポイントです。データ活用やシェアリング、自動化などの手法も積極的に取り入れながら、より高度な効率化を目指してみてはいかがでしょうか。
なお、Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流DXツールMOVO(ムーボ)と、物流DXコンサルティングサービスHacobu Strategy(ハコブ・ストラテジー)を提供しています。物流現場の課題を解決する物流DXツール「MOVO」の各サービス資料では、導入効果や費用について詳しくご紹介しています。
トラック予約受付サービス(バース予約システム) MOVO Berth
MOVO Berth(ムーボ・バース)は、荷待ち・荷役時間の把握・削減、物流拠点の生産性向上を支援します。
動態管理サービス MOVO Fleet
MOVO Fleet(ムーボ・フリート)は、協力会社も含めて位置情報を一元管理し、取得データの活用で輸配送の課題解決を支援します。
配車受発注・管理サービス MOVO Vista
MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、電話・FAXによるアナログな配車業務をデジタル化し、業務効率化と属人化解消を支援します。
物流DXコンサルティング Hacobu Strategy
Hacobu Strategyは、物流DXの戦略、導入、実行まで一気通貫で支援します。
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主