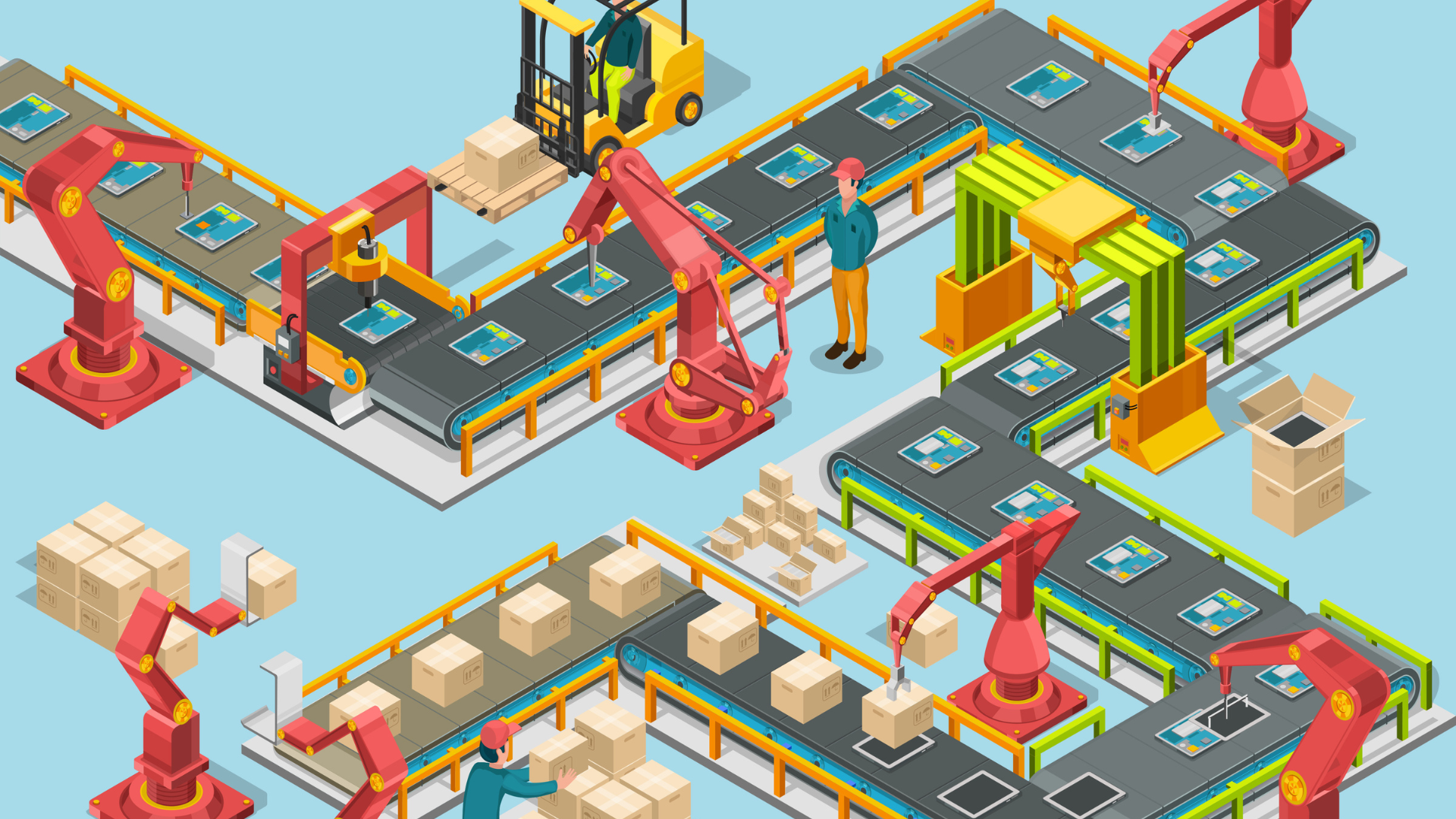Scope3 カテゴリー4とは?上流の輸送・配送におけるCO2排出の可視化と対策

気候変動対策への取り組みが企業経営に欠かせない要素となる中、サプライチェーン全体の温室効果ガス(GHG)排出量を把握し、削減する動きが加速しています。中でも注目されているのが「Scope3」に分類される間接排出の領域です。特にScope3の「カテゴリー4(上流の輸送および配送)」は、調達先からの原材料や製品を自社に届けるまでの物流に伴うCO2排出量を対象としており、多くの企業にとって可視化と対策が難しい一方で、大きなインパクトをもたらす領域です。
本記事では、物流DXパートナーのHacobuがScope3 カテゴリー4の概要を整理しながら、なぜ企業の物流・調達部門にとって重要なのか、どのように排出量を可視化し、実効性のある対策を講じていくべきかを解説します。
目次
Scope3 カテゴリー4とは
温室効果ガスの排出量を削減する動きが世界中で加速するなか、企業の気候変動対応において「Scope3」の重要性が高まっています。Scope3とは、自社の事業活動に関連するが、自社の直接的な管理下にはない排出量を指し、原材料の調達から製品の使用、廃棄に至るまで、サプライチェーン全体が対象になります。
そのScope3は15のカテゴリーに分類されており、業種やビジネスモデルに応じて影響の大きい領域が異なります。その中でも、特に多くの企業にとって重要となるのが「カテゴリー4:上流の輸送および配送」です。サプライヤーからの輸送や倉庫への配送といった、原材料や製品が自社に届くまでの物流に伴う排出量が該当し、物流・調達部門にとって無視できない領域となっています。
企業の脱炭素対応におけるScope3の重要性
気候変動への対応がグローバルで加速するなか、多くの企業が自社の温室効果ガス(GHG)排出量を把握し、削減目標を設定するようになってきました。その中核をなすのが「Scope1・2・3」と呼ばれる排出量の区分です。特にScope3は、サプライチェーン全体に関わる排出量を対象としており、自社の活動だけではなく、調達先や物流、さらには製品使用後の排出量までもカバーするため、管理が難しい一方でインパクトの大きい領域です。
Scope3は15のカテゴリーに分類されており、それぞれが異なる排出源を示しています。中でも多くの企業にとって対応が求められているのが、調達・物流に関連するカテゴリです。自社の直接排出であるScope1や、購入した電力に伴うScope2に加えて、より広い視野での排出量管理が、今後の脱炭素経営の鍵を握っています。
カテゴリー4が物流・調達部門に関係する理由
Scope3カテゴリー4は、「上流の輸送および配送」を指します。これは、製品や原材料などが自社に届くまでの間に発生する輸送・配送に関わる排出量です。たとえば、仕入先から倉庫へのトラック輸送や、港湾での積み替えに伴う配送などが該当します。
このカテゴリが注目される理由のひとつは、多くの企業が外部の物流事業者を利用しており、自社では見えにくい排出源になっている点です。取引先との間でどのような輸送手段を使い、どのルートを通り、どれだけの燃料を使っているかといった情報がブラックボックスになりがちですが、その中に多くの排出要因が潜んでいます。
また、グリーン調達やESG評価の観点からも、サプライチェーン上流の排出量を適切に把握し、対策を講じている企業は市場や投資家から高く評価される傾向にあります。調達・物流部門にとってScope3カテゴリー4は、単なる環境対策の一環ではなく、経営戦略上の重要なテーマになりつつあります。
Scope3の全体像とカテゴリー4の位置づけ
Scope3カテゴリー4を正しく理解するためには、まずScope全体の構造を把握することが大切です。Scope3は企業活動の外側、つまりサプライチェーン全体にわたる排出量を対象としており、カテゴリー4はその中でも物流に関係する重要な項目です。以下では、Scope1〜3の違い、Scope3の15カテゴリの概要、そしてカテゴリー4の具体的な位置づけについて解説していきます。
Scope1〜3の違いとは?
温室効果ガス排出量は、企業の活動範囲に応じてScope1・2・3に分類されます。Scope1は、自社が直接排出する分(例:工場の燃料燃焼)、Scope2は、購入した電力や熱に伴う間接排出、そしてScope3は、自社以外のサプライチェーン活動に伴う間接排出です。
この中でもScope3は、取引先や顧客、物流業者など、企業の外側にある排出源を対象としているため、影響範囲が広く、対応には他部門やパートナーとの連携が欠かせません。
Scope3の15カテゴリと概要
Scope3は、全部で15のカテゴリに分類されています。これには、購入した製品やサービス、資本財、燃料やエネルギー関連活動、輸送・配送(上流・下流)、事業活動に伴う出張、販売した製品の使用や廃棄など、サプライチェーン全体のライフサイクルにわたる排出源が網羅されています。
カテゴリごとに排出要因やデータの入手方法が異なるため、自社の業態やビジネスモデルに即した優先順位付けが重要です。特に製造業や小売業など、物流に多く依存する業種では、カテゴリー4(上流の輸送・配送)の排出量が無視できない割合を占めています。
カテゴリー4「上流の輸送・配送」の定義
カテゴリー4では、製品や原材料がサプライヤーから企業の拠点に届けられるまでの間に発生する物流関連の排出量を対象としています。これは、自社で管理していない場合でも対象となるのが特徴です。
たとえば、外部の物流会社が手配した輸送手段であっても、Scope3のカテゴリー4として算入する必要があります。具体的には、トラック、船舶、鉄道、航空などの輸送手段が使われた距離や重量、燃料の種類などに応じて排出量を算出することになります。
Scope3カテゴリー4で排出されるCO2の実態
Scope3カテゴリー4で対象となるのは、原材料や製品などが自社に届くまでに発生する輸送・配送に関わるCO2排出です。これらは通常、外部委託された物流サービスの中で行われるため、自社での管理が難しく、見えづらい排出源となっています。しかし、企業がサプライチェーン全体の排出量を正しく把握し、削減に取り組むためには、このカテゴリー4に含まれる排出の実態を理解することが不可欠です。
対象となる物流活動の具体例
カテゴリー4でカウントされる排出量は、主にサプライヤーからの輸送活動に起因するものです。たとえば、部品メーカーから自社工場へ向かうトラック輸送や、複数の仕入先から倉庫への海上輸送などが該当します。これらの輸送は、企業が直接コントロールしていないケースが多いため、取引先や物流会社との情報共有が鍵となります。
また、仕入先が複数の中間業者を経由している場合、その過程での配送もカテゴリー4の対象です。つまり、調達元から自社拠点に至るまでのすべての物流経路がScope3カテゴリー4に含まれるという認識が必要です。
排出が発生する要因(距離・手段・積載率など)
排出量は、さまざまな要因によって左右されます。特に影響が大きいのは輸送距離と使用する手段です。長距離輸送ほど排出量が増えやすく、また航空輸送や小型トラックなどは単位あたりの排出量が大きくなります。
さらに、積載率も重要な要素です。たとえば、同じ車両を使っていても、積載量が50%か100%かによって、実質的な排出効率は大きく変わります。こうした要因を総合的に見て、効率的な輸送設計ができるかどうかが、排出量削減の鍵となります。
排出量の計算方法の基本(Activity × Emission Factor)
Scope3カテゴリー4の排出量は、基本的に「活動量(Activity)」と「排出原単位(Emission Factor)」を掛け合わせて算出します。活動量とは、たとえば輸送された貨物の重量と距離をかけた「トン・キロ(t・km)」などが使われます。
排出原単位は、輸送手段ごとに定められており、国や業界団体が公表しているデータをもとに選定します。たとえば、トラック輸送1t・kmあたりに何kgのCO2が排出されるかという数値がこれにあたります。こうしたデータをもとに計算することで、見えづらい排出量を定量的に把握し、削減のアクションにつなげることができます。
Scope3カテゴリー4に対応する目的と企業メリット
カテゴリー4への対応は、単なる環境対応ではなく、企業の競争力向上や持続可能な経営にも直結します。ここでは、企業がカテゴリー4に取り組むことで得られる主なメリットを見ていきましょう。
サプライチェーン全体の最適化
輸送・配送にかかわる排出量を可視化することで、どこに無駄があるのか、どこを効率化できるのかを把握しやすくなります。たとえば、積載効率の向上、ルートの見直し、共同輸配送の導入といった施策を通じて、物流の効率化と排出量削減を同時に実現できる可能性があります。
このような最適化は、コスト削減や納期短縮といったビジネス面でのメリットにもつながるため、Scope3対応は単なる負担ではなく、経営改善のきっかけとして捉えることができます。
取引先や顧客からの評価向上
現在、ESGやサステナビリティを重視する企業は、取引先の環境対応にも目を光らせています。カテゴリー4の排出量に向き合い、削減に努めている企業は、そうした取引先や顧客からの信頼を獲得しやすくなります。
特に大手企業との取引においては、Scope3排出量の報告や削減の取り組みが選定基準に含まれるケースも増えており、将来的には「対応していること」が参入条件になることも十分考えられます。
各種開示制度(CDP、TCFD、CSRD等)への対応
Scope3の排出量は、CDP(気候変動開示プラットフォーム)やTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)、さらにはEUのCSRD(企業持続可能性報告指令)といった、各種情報開示制度でも重視される項目です。
とくにカテゴリー4のような上流工程の排出量は、開示の透明性や網羅性を高めるうえで不可欠な要素とされています。早い段階から正確なデータを収集・管理できていれば、将来的な法規制や開示義務にもスムーズに対応することが可能になります。
Scope3カテゴリー4の排出量を可視化する方法
排出量の削減に取り組むためには、まず現状を「見える化」することが出発点です。ここでは、Scope3カテゴリー4における排出量をどのようにして把握するか、その実務的なポイントについて解説します。
データ収集のポイント(自社輸送・外部委託)
まずは、どの輸送がカテゴリー4に該当するのかを洗い出し、必要なデータを収集することから始まります。自社が契約する物流会社が明確であれば、輸送ルートや使用車両、燃料の種類などをヒアリングしやすいですが、間接的な取引や複数業者を介するケースでは、データ取得が難航することもあります。
そのためには、調達部門と連携して、仕入先との情報共有を進めたり、物流会社に対して排出データの提供を依頼するなどの地道な取り組みが重要です。企業によっては、情報提供を契約条件に組み込む動きも見られます。
活動量データの例と取得方法
排出量を算出するための活動量データには、貨物の重量、輸送距離、使用した車両の種類などが含まれます。たとえば、1回の輸送で何トンの荷物を、何キロメートル運んだかを記録しておくことで、排出量のベースとなる数値が得られます。
輸送管理システム(TMS)や物流会社からの納品データなど、既存の業務システムを活用すれば、比較的スムーズに収集できる場合もあります。自社で管理できる範囲を明確にし、どこから先が委託先の情報かを整理しておくことが、正確な可視化につながります。
排出原単位の活用と参考資料
排出量の計算に必要な排出原単位は、環境省や国土交通省などが公開しているガイドラインやデータベースを活用するのが一般的です。たとえば、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」や「エコレールマーク」の資料には、輸送手段ごとの平均的な排出係数が掲載されています。
業種や輸送手段に合わせて、最も現実に近いデータを選ぶことが求められます。また、継続的に改善を進めるためには、自社の実績に基づいた独自の排出原単位を整備していくことも有効です。
Scope3の排出量削減に向けたアプローチ
カテゴリー4の排出量が可視化できたら、次に重要なのはそれをどう削減していくかです。企業の物流や調達に関する業務は日々の業務に直結しており、現場の効率化と環境対策の両立が求められます。ここでは、実務的かつ効果的に取り組める代表的なアプローチを紹介します。
積載率の向上や共同配送の推進
積載率が低いまま運行されるトラックは、CO2排出量の効率が悪くなります。輸送計画を見直し、できるだけ積載率を高めることが、もっとも基本的かつ効果的な対策です。また、同一エリアに納品先が集中している場合、他社との共同配送を行うことで、トラック台数そのものを削減でき、排出量の削減につながります。
こうした取り組みは、コスト削減にも直結するため、環境面・経済面の双方でメリットがあります。特に中小企業にとっては、物流コストの最適化とScope3対応を同時に進めるための有効な一手です。
モーダルシフトの活用
長距離輸送をトラックから鉄道や船舶へ切り替える「モーダルシフト」も、CO2排出量を大きく削減できる手段です。鉄道や船はトン・キロあたりの排出量がトラックに比べて少ないため、特に大規模な物量を扱う企業では高い効果が期待されます。
もちろん、時間や積み替えの手間といった課題はありますが、うまく活用すれば、安定的で環境負荷の少ない輸送体制を構築することが可能です。政府や自治体も補助金や制度でモーダルシフトを後押ししており、導入しやすい環境が整いつつあります。
脱炭素型輸送(EV・バイオ燃料など)の導入
輸送手段そのものを見直すというアプローチもあります。たとえば、EV(電気トラック)やバイオディーゼル燃料を活用した車両の導入により、化石燃料への依存を減らすことが可能です。
特に近距離輸送においては、EV車両の導入ハードルが下がっており、自治体による補助金の活用やリース契約などで初期費用の負担を軽減することもできます。これにより、輸送時の直接的な排出量を大きく削減することが期待されます。
輸送計画・物流DXの活用による効率化
物流業務のデジタル化(DX)は、排出量の削減にも直結します。輸送ルートの最適化、積載計画の自動化、リアルタイムの配送状況管理など、さまざまなツールを活用することで、輸送のムダを削減し、排出量も同時に抑えることが可能です。
近年では、GHG排出量を自動で可視化・レポート化できるクラウド型サービスも登場しており、企業規模にかかわらず導入しやすい環境が整ってきています。物流DXは、環境対応の手段であると同時に、業務効率の向上や品質改善にも寄与するため、多面的な価値を持つ施策と言えるでしょう。
Scope3 カテゴリー4に取り組む企業事例
Scope3カテゴリー4への対応は、企業ごとの業種や体制によってアプローチが異なりますが、共通して言えるのは「見える化」と「継続的な改善」が重要であるということです。ここでは、実際に取り組みを進めている2社の事例を紹介します。(記事公開時点の情報です。)
株式会社ファンケル
ファンケルは、長期的な視点での事業戦略「VISION 2030」に基づき、Scope3排出量の算定と削減に積極的に取り組んでいます。Scope3の中でも特にカテゴリ1(原材料の購入)、カテゴリ4(上流の輸送・配送)、カテゴリ11(製品の使用)の3つで排出量の大半を占めていることから、それらを重点的に管理しています。
上流の輸送に関しては、トンキロ法を活用して輸送重量と距離からCO2排出量を算定。再配達削減を目的に「置き場所指定」や「ポストサイズ梱包」といった取り組みも導入しています。サプライヤーとの連携を深めることで、排出量の実態把握と精度向上も図っており、環境配慮型製品や広告の効率化も合わせて進めています。
株式会社ファンケル|グリーン・バリューチェーンプラットフォーム 取組事例 2022年度
株式会社タムロン
光学機器メーカーのタムロンでは、全社的な環境負荷の把握を目的にScope3排出量の算定を実施。特にカテゴリ1とカテゴリ4の排出割合が大きく、今後も削減の可能性を継続的に検討していくとしています。
カテゴリ4については、輸送重量と距離に基づきトンキロ法で算出。輸送経路の把握や、海外拠点を含む物流網の可視化が課題として挙げられています。社内ではISO部門が中心となって関係部門からデータを収集し、算出結果をCSR報告書などで社外に開示。環境負荷の大きい分野を特定し、重点的に削減を進める基礎資料として活用しています。
株式会社タムロン|グリーン・バリューチェーンプラットフォーム 取組事例 2020年度
Scope3カテゴリー4対応の第一歩は「見える化」から
Scope3カテゴリー4、つまり「上流の輸送・配送」に伴うCO2排出は、多くの企業にとって見えづらい存在でありながら、その影響は決して小さくありません。だからこそ、まずは現状の排出量を正しく「見える化」することが出発点です。
データ収集や算定は一見ハードルが高く感じられるかもしれませんが、物流パートナーやサプライヤーとの連携を強化することで、少しずつでも対応が進められます。そして、一度可視化ができれば、次は最適化や削減といった具体的なアクションへとつなげていくことが可能です。
Scope3への対応は、環境対策としての側面だけでなく、企業の競争力強化や信頼向上にも寄与する取り組みです。まずはカテゴリー4の見える化から、脱炭素経営の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
なお、Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流DXツールMOVO(ムーボ)と、物流DXコンサルティングサービスHacobu Strategy(ハコブ・ストラテジー)を提供しています。
MOVOは燃費法を用いて、Scope3のカテゴリー4(上流の輸配送)・カテゴリー9(下流の輸配送)の可視化が可能です。
トラック予約受付サービス(バース予約システム) MOVO Berth
MOVO Berth(ムーボ・バース)は、物流拠点におけるトラックの入退場を管理するシステムです。
入退場の予約時に出荷元住所を入力することで、出荷元→納品先(自拠点)までのトラックの走行距離を把握できます。入荷車両は出荷元が手配することが多いため、一般的にカテゴリー4の可視化は難しいですが、MOVO Berthの活用によって走行距離の実績からCO2排出量を計算いただけます。
動態管理サービス MOVO Fleet
MOVO Fleet(ムーボ・フリート)は、運送を委託している会社の位置情報や走行ルートを可視化・分析できるシステムです。
「走行履歴」画面の下部に実際に走行したルートのCO2排出量が表示されます。日報機能にて、一日分の走行距離から算出されるCO2排出量をダウンロードすることも可能です。店舗配送などのカテゴリー9可視化におすすめです。
配車受発注・管理サービス MOVO Vista
MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、運送を委託している会社への配送依頼をデジタル上で行うシステムです。
配送依頼時に出荷元→納品先の住所を入力することにより、走行距離とCO2排出量が算出されます。幹線輸送などのカテゴリー9可視化におすすめです。
また、CO2排出量の削減には、Hacobu Strategyがお力添えできます。
物流DXコンサルティング Hacobu Strategy
共同輸配送やバックホールの活用など、トラックのシェアリングを行うことで、カテゴリー4・9の削減が可能です。共同輸配送やバックホールを実行するには、データの分析や戦略の立案など、物流における専門知識が必要になります。Hacobu Strategyは、物流DXの戦略、導入、実行まで一気通貫で支援します。
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主