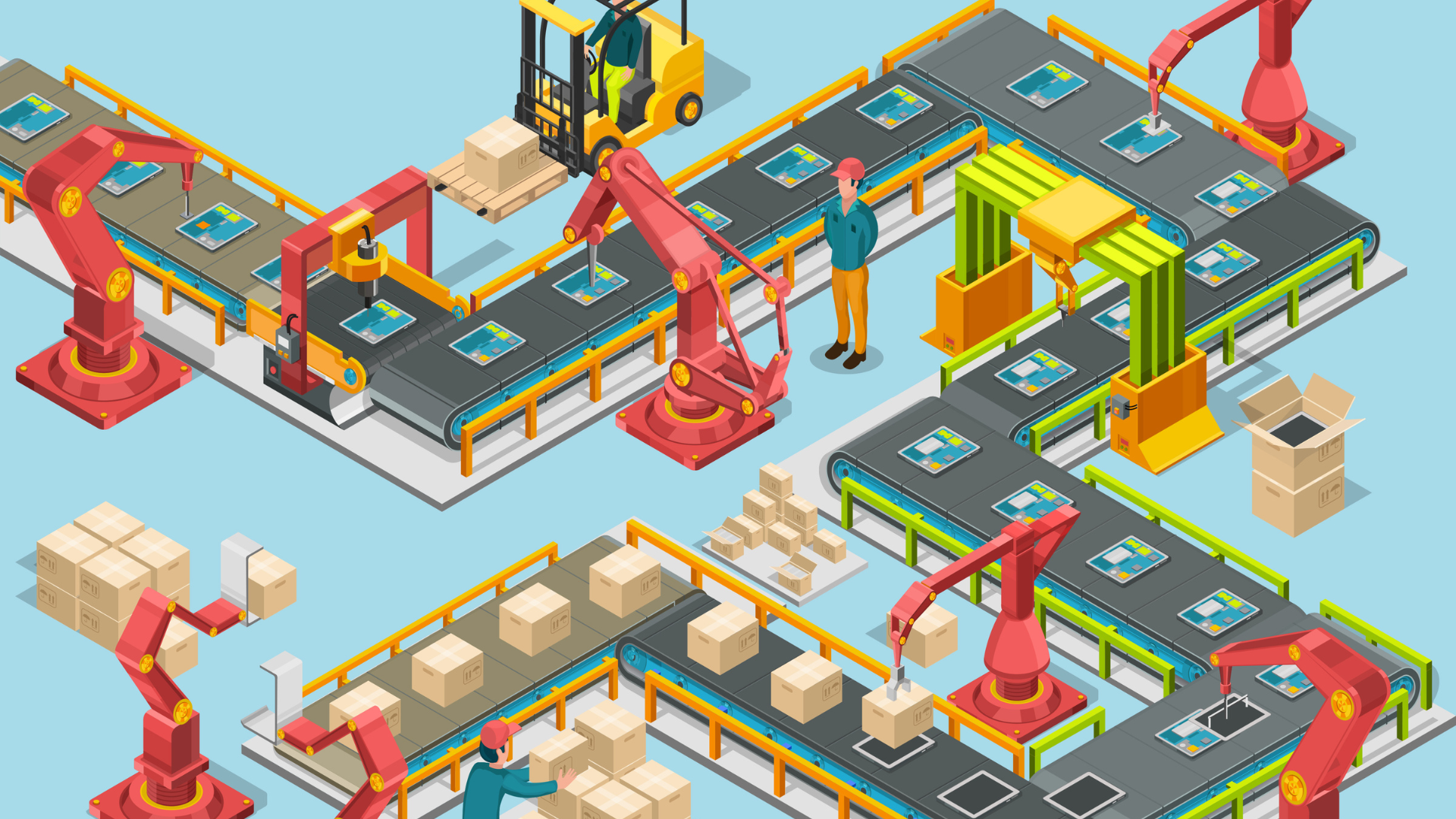ESGスコアとは?評価項目・算出方法・物流領域の課題と改善策を解説

ビジネスを取り巻く環境が大きく変化する中で、「ESG」という言葉を耳にする機会が増えてきました。持続可能な社会の実現が求められる今、企業の経営判断においても環境や社会への配慮、透明性のあるガバナンスが重要視されています。こうした背景の中で注目されているのが「ESGスコア」です。本記事では、ESGスコアの基本的な意味や評価項目、算出方法、物流領域が抱える課題とその改善策について、物流DXパートナーのHacobuが解説します。
ESGスコアとは
ESGスコアとは、企業がどれだけ環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮した経営を行っているかを評価する指標です。企業活動がもたらす社会的・環境的なインパクトに注目し、長期的な視点での健全な成長性やリスク耐性を見極めるために用いられています。
このスコアは、企業の財務情報だけでは見えにくい非財務的な側面を可視化するもので、主に投資家や金融機関などが投資判断の材料として活用しています。企業にとっても、ESGスコアを意識することは単なる評価対策にとどまらず、信頼性の向上やブランド価値の強化、さらには中長期的な経営戦略の立案において重要な役割を果たすようになっています。
ESGスコアが注目される背景
近年、ESGスコアが注目されている背景には、地球温暖化をはじめとした環境問題や、労働環境の多様化、企業不祥事に対する社会的な厳しい目線の高まりがあります。従来のように利益や成長率だけを重視する経営姿勢では、社会的信頼を得られにくくなってきており、企業にはサステナビリティへの対応が強く求められています。
また、投資の世界でも大きな変化が起きています。国内外の金融機関や投資家がESG要素を組み込んだ「ESG投資」に積極的に取り組むようになっており、ESGスコアが高い企業に対して資金が集まりやすくなっています。特に欧米を中心とした海外の投資家からの要求水準は高く、グローバル展開を志向する企業にとっては無視できない要素となっています。
日本国内でも、東京証券取引所によるコーポレートガバナンス・コードの改訂や、金融庁の情報開示ガイドライン整備などにより、ESGに関する情報の開示や取り組みの強化が求められています。これにより、上場企業だけでなく中堅企業やスタートアップにおいても、ESG対応が競争力の一部として捉えられるようになってきました。
社会の価値観が変わる中で、ESGスコアは単なる「企業評価のための数字」ではなく、企業の信頼性や将来性を測るための重要な指標として存在感を増しています。
ESGスコアの評価項目
ESGスコアは、その名の通り「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」という3つの視点から、企業の取り組みを多角的に評価します。各分野には具体的な評価項目が設けられており、それぞれの分野での姿勢や実行力がスコアに反映されます。ここでは、それぞれのカテゴリごとにどのような項目が評価対象となるのかをご紹介します。
環境(E:Environment)
環境分野では、企業がどのように地球環境に配慮した経営を行っているかが評価されます。温室効果ガスの排出削減から、エネルギーの使い方、資源循環の仕組みまで、幅広い観点が対象となります。
気候変動対策
企業の温室効果ガス排出量の削減目標や、その達成に向けた具体的な取り組みが問われます。たとえば、製造工程の見直しや物流の最適化、カーボンオフセットの導入などが該当します。国際的な目標である「1.5℃目標」への貢献度も、今や重要な評価指標となっています。
再生可能エネルギーの活用
化石燃料に依存せず、太陽光や風力、バイオマスといった再生可能エネルギーを積極的に活用しているかどうかも評価の対象です。再エネの導入は単なるコスト削減ではなく、企業の環境責任を果たす上でも大きな意味を持ちます。
廃棄物・資源管理
事業活動で発生する廃棄物の適切な処理やリサイクルの推進、限られた資源の有効活用が評価されます。製品のライフサイクル全体を通じて、いかに環境負荷を抑えているかが問われる点も特徴です。
社会(S:Social)
社会の項目では、企業が従業員や取引先、地域社会といったステークホルダーに対して、どれだけ健全な関係を築いているかが評価されます。特に近年は、労働環境の改善や多様性の推進が重要なテーマとなっています。
労働環境・人権尊重
働きやすい職場づくりや安全衛生管理、長時間労働の是正、ハラスメント対策といった取り組みの有無が評価されます。また、サプライチェーン全体での人権尊重、特に強制労働や児童労働の排除に関する姿勢も重要な評価要素です。
ダイバーシティ&インクルージョン
性別や年齢、国籍、障がいの有無などにかかわらず、多様な人材が活躍できる職場環境を整えているかが問われます。特に、管理職や経営層における女性や外国人の登用状況が、ダイバーシティの進捗を測る指標とされることが増えています。
コミュニティへの貢献
企業が地域社会や環境への貢献をどのように実践しているかも、社会面での評価対象です。地元雇用の創出、災害支援、教育支援活動など、直接的な経済的利益を超えた社会的な価値の創出が求められます。
ガバナンス(G:Governance)
ガバナンス分野では、企業経営の透明性や公平性、そして持続的な成長を支える統治体制の強さが評価されます。企業不祥事の防止や株主との信頼関係構築において、極めて重要な項目です。
コーポレートガバナンス
経営陣の意思決定プロセスが公正かつ健全であるかが問われます。社外取締役の設置、監査体制の整備、株主の意見を経営に反映させる仕組みなど、企業の統治能力が評価されるポイントとなります。
透明性・コンプライアンス
財務・非財務情報の開示の充実度や、法令遵守、倫理的行動に関するガイドラインの整備状況が対象です。特にESG情報については、投資家やステークホルダーにとっての重要性が増しており、透明な情報開示は企業の信頼性に直結します。
取締役会の構成
取締役会の多様性や独立性も評価のポイントです。意思決定機関としての機能が適切に働いているか、また社外の視点を取り入れたバランスの良い構成になっているかどうかが注目されます。これにより経営の健全性や持続可能性への信頼が左右されます。
ESGスコアの算出方法
ESGスコアは、企業の環境・社会・ガバナンスに関する取り組みを客観的に評価するために、さまざまな観点から情報を収集し、数値として算出されます。しかし、その方法は一律ではなく、評価機関ごとに異なるアプローチが取られています。このセクションでは、主な評価機関や評価手法の特徴、そして企業側がスコアをどのように活用しているのかについて解説します。
代表的な評価機関
ESGスコアの評価は、専門の評価機関によって行われています。代表的な評価機関には、MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)、S&Pグローバル、FTSEラッセル、Sustainalyticsなどがあり、それぞれ独自の基準とアルゴリズムを用いて企業を評価しています。
たとえば、MSCIは業界特有のリスクと機会に着目した評価手法を採用しており、S&Pグローバルは企業への詳細なアンケートを通じて数百項目にわたる情報を収集しています。国内では、日経ESGや大和総研、格付投資情報センター(R&I)などもESG評価を行っており、グローバルとローカルの両面からの視点が必要とされています。
企業によっては、複数の評価機関からスコアを取得しているケースもあり、それぞれの評価結果が異なることも少なくありません。こうした背景から、ESGスコアの「相対性」や「評価のばらつき」についても、理解しておくことが重要です。
定量・定性評価の組み合わせ
ESGスコアは、単純な数値データだけで評価されるわけではありません。一般的に、定量評価と定性評価の組み合わせによって総合的に判断されます。
定量評価では、CO2排出量や女性管理職の比率、法令違反件数など、数値で把握できるデータが用いられます。一方、定性評価では、企業がどのような方針を掲げ、どのように実行しているかといった内容が重視されます。たとえば、環境方針の明確さや、ガバナンス体制の構築状況、サプライチェーンマネジメント(SCM)の方針などが対象です。
さらに、外部から入手できる情報だけでなく、企業による自己申告や公開資料、インタビュー結果なども評価に反映されることがあります。そのため、企業側が発信する情報の整備や開示姿勢も、スコアに大きな影響を与えると言えるでしょう。
企業がスコアを活用する場面
ESGスコアは、単に投資家のためだけの指標ではありません。企業自身がこのスコアを戦略的に活用するケースも増えています。
たとえば、サステナビリティレポートや統合報告書において、自社のESGスコアや第三者評価を開示することで、企業としての信頼性や透明性を高めることができます。また、スコアの結果を社内で共有し、ESGに関する課題を可視化することで、改善活動の方向性を明確にする役割も果たします。
さらに、取引先や採用候補者との関係構築においても、ESGスコアはプラスに働くことがあります。社会的価値を意識した企業文化を打ち出すことで、価値観の合うパートナーや人材とのマッチングがスムーズになるからです。
このように、ESGスコアは企業の対外的なアピールだけでなく、社内の意識改革や経営判断の指針としても活用されるようになってきています。
ESGスコアの課題
ESGスコアは企業の持続可能性を可視化する上で有効な指標ですが、課題がまったくないわけではありません。評価の信頼性や客観性が求められる中で、いくつかの懸念点が指摘されています。ここでは、現在のESGスコアをめぐる代表的な課題を取り上げます。
評価基準の不統一性と透明性の問題
ESGスコアの大きな課題のひとつが、評価基準の不統一性です。前述のように、ESGスコアは複数の評価機関によって算出されていますが、それぞれが異なる評価軸や重みづけを採用しているため、同じ企業でもスコアが大きく異なるケースが少なくありません。
このバラつきは、投資家や企業担当者にとって混乱を招く要因となっています。どのスコアを基準にすればよいのか判断が難しく、ESG対応の優先順位をつけづらいという声もあります。
また、評価プロセスの透明性が十分でないことも課題です。なぜこのスコアになったのか、具体的にどの項目が評価されたのかが明示されていない場合、企業側も改善の方向性を見定めにくくなります。今後、ESG評価の国際的な標準化や、透明なスコア設計への取り組みが進むことが期待されています。
グリーンウォッシュ(見せかけのESG対策)リスク
ESGへの関心が高まる中で、企業が「いかに良く見せるか」に偏ってしまうケースも見られます。これがいわゆる「グリーンウォッシュ」と呼ばれるもので、実態が伴わないESG施策を打ち出すことで、あたかも環境や社会に配慮しているかのように見せかける行為です。
たとえば、再生可能エネルギーの導入計画を発表しながらも、実際の導入率は極めて低いままになっていたり、一部のポリシーだけを強調して全体の取り組みを誇張したりするケースが該当します。こうした表面的な取り組みは、一時的には評価につながるかもしれませんが、長期的には企業の信用を損なうリスクがあります。
評価機関としても、グリーンウォッシュを見抜くために情報の正確性や実行力の裏付けを求める傾向が強まっています。企業側も、数字や実績に裏打ちされた誠実な情報開示が求められる時代に入っているといえるでしょう。
データ収集・開示の難しさ
もうひとつの大きな課題は、ESG評価に必要なデータの収集と開示のハードルの高さです。特に非財務情報は、定量的に測定するのが難しい項目も多く、現場に散らばった情報を統合して一元的に把握するには、相応のリソースと仕組みが必要になります。
たとえば、温室効果ガスの排出量を正確に把握するには、自社の活動だけでなく、サプライチェーン全体のデータを集める必要があり、これは多くの企業にとって簡単なことではありません。また、人権や労働環境といったテーマについても、定性的な内容が多いため、統一的な基準で開示するのが難しいという声があがっています。
さらに、開示した情報が正確であることを証明するためには、第三者の監査やレビューが求められる場合もあり、その体制を構築すること自体が企業にとって負担となることもあります。
こうした課題を乗り越えるためには、社内でのデータ管理体制の強化や、ESGに対応した情報開示フレームワーク(たとえばGRIやSASBなど)への理解と導入が求められます。
物流領域におけるESGの重要性
物流は、私たちの暮らしを支えるインフラとして重要な役割を果たしており、サプライチェーン全体の中でも中核的な存在です。一方で、物流センターの運営やトラック輸送に代表されるように、温室効果ガスの排出量が多く、エネルギー消費や人手不足といった社会課題とも深く関わっています。
そのため、物流におけるESGへの取り組みは、単なる企業評価にとどまらず、物流領域全体の持続可能性を左右する重要なテーマといえます。ESGスコアの向上は、環境負荷の軽減や労働環境の改善、経営の透明性強化といった側面で領域全体に良い影響をもたらすだけでなく、今後の事業継続や競争力の源泉にもつながります。
政府のカーボンニュートラル目標や、企業間でのESG情報の開示要請が広がる中で、物流領域としても自らの取り組みを見直し、スコア向上に向けた具体的なアクションが求められています。
物流領域におけるESGスコア改善の課題と対策
物流領域がESGスコアを向上させるためには、現場の実情を踏まえたうえで、環境・社会・ガバナンスそれぞれの視点から課題を捉え、実効性のある対策を講じていく必要があります。また、DXの活用によって、業務効率と持続可能性を同時に高めるアプローチも欠かせません。
環境(E)への対応
課題:CO₂排出量・エネルギー使用の高さ
トラック輸送を中心とした物流領域は、他の業種と比べてもCO2排出量が多く、燃料消費による環境負荷の高さが長年の課題とされてきました。また、施設や倉庫における電力使用量も少なくなく、エネルギー効率の見直しが求められています。
アクション:モーダルシフト、エコドライブ、再生可能エネルギーの活用
この課題に対しては、輸送手段を鉄道や船舶に切り替える モーダルシフト が有効です。長距離輸送を環境負荷の少ない手段へ移行することで、CO2排出を大幅に削減できます。
加えて、エコドライブの徹底や燃費性能の高い車両への更新も、現実的な対策として進められています。
倉庫や拠点では、再生可能エネルギーの導入が注目されています。太陽光パネルの設置やグリーン電力の活用により、施設運営における環境負荷の低減が図られています。
社会(S)への対応
課題:長時間労働・人材不足・職場環境
物流領域では、ドライバー不足や高齢化が深刻な課題となっており、特に長時間労働や恒常的な荷待ち、休憩の取りづらさなどが、労働環境の悪化を招いています。また、女性や若年層の参入が進みにくいという点も、持続的な人材確保の妨げとなっています。
アクション:働き方改革、ダイバーシティ、職場安全対策
このような社会的課題への対応としては、労働時間の適正化や休暇取得の促進、トラック予約受付システムや運行管理システムの導入など、働き方改革に向けた取り組みが広がっています。さらに、女性や高齢者、外国人など多様な人材が活躍できる職場づくりも求められています。
加えて、安全運転支援技術の導入やヒューマンエラーの低減に向けた教育など、職場の安全性向上に関する取り組みも、ESGの社会面における重要な評価対象となります。
ガバナンス(G)への対応
課題:荷主起因による運送会社の法令違反
運送会社の過労運転・過積載といった法令違反が、荷主の無理な到着時間設定や急な貨物量増加、長時間の荷待ち指示などに起因し、それが常態化している場合は現場の問題ではなく企業統治力を欠くガバナンス不全と考えられます。違反原因行為を放置すれば、荷主勧告制度で社名が公表され、取引先・投資家の信頼を失う重大な経営リスクを招きます。
荷主勧告の可能性がある、荷主の主体的な関与の具体例としては以下のような行為が考えられます。
- 荷待ち時間の恒常的な発生
- 非合理な到着時刻の設定
- やむを得ない遅延に対するペナルティ
- 重量違反等となるような依頼
アクション:運送会社への指示内容を定期監査
荷主として勧告を避けるには、法令遵守の社内教育を強化し、運送会社への指示内容を定期監査して是正することが第一歩です。非合理的な到着時間設定や急な貨物量変更、遅延ペナルティといった慣習的フローを洗い出し改善し、さらに荷待ち時間をデータで把握し削減策を講じることで、違反原因行為を根本から断ち、勧告リスクを低減できます。
荷主勧告制度とは?荷主勧告を受ける荷主の行為、企業に求められる対応などを解説
荷主勧告制…
2025.12.26
DXによる全体最適化
課題:アナログ運用による情報分断
多くの現場が電話やFAXに頼るオペレーションでは、拠点ごとに情報が分断され、本社がリスク兆候を把握できずガバナンスが空洞化します。たとえば下請け事業者に対する3条書面未交付や長時間の荷待ち常態化、過積載強要など法令違反の芽が埋もれ、違反原因行為として行政処分や社名公表に直結する危険性が急速に高まります。DXの遅れが全体最適化を阻む典型例と言えるでしょう。
アクション:本社主導による物流DXの推進
全体最適化の鍵は物流DXによるデータ一元化です。適正な書面交付や荷待ち時間などを全拠点統一のオペレーションで管理し、本社のコントロールタワーが定期的に監査し、アラートと是正指示を即時発信すれば、法令違反の芽を早期に摘み取り、統治責任を果たしながら効率化とコスト削減を同時に実現できます。
まとめ
ESGスコアは、企業の環境対応力や社会的責任、ガバナンス体制を測るための重要な指標として、今後ますます存在感を増していくでしょう。特に物流業界では、環境負荷の高さや人手不足、業務の非効率性など、ESGに直結する課題が数多く存在します。
だからこそ、スコア向上に向けた取り組みは単なる評価対策ではなく、業界全体の未来を見据えた戦略的なアプローチといえます。ESGスコアを起点に、自社の課題を可視化し、ひとつひとつ改善を重ねていくことで、より強く、持続可能な組織づくりにつながっていくはずです。
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主