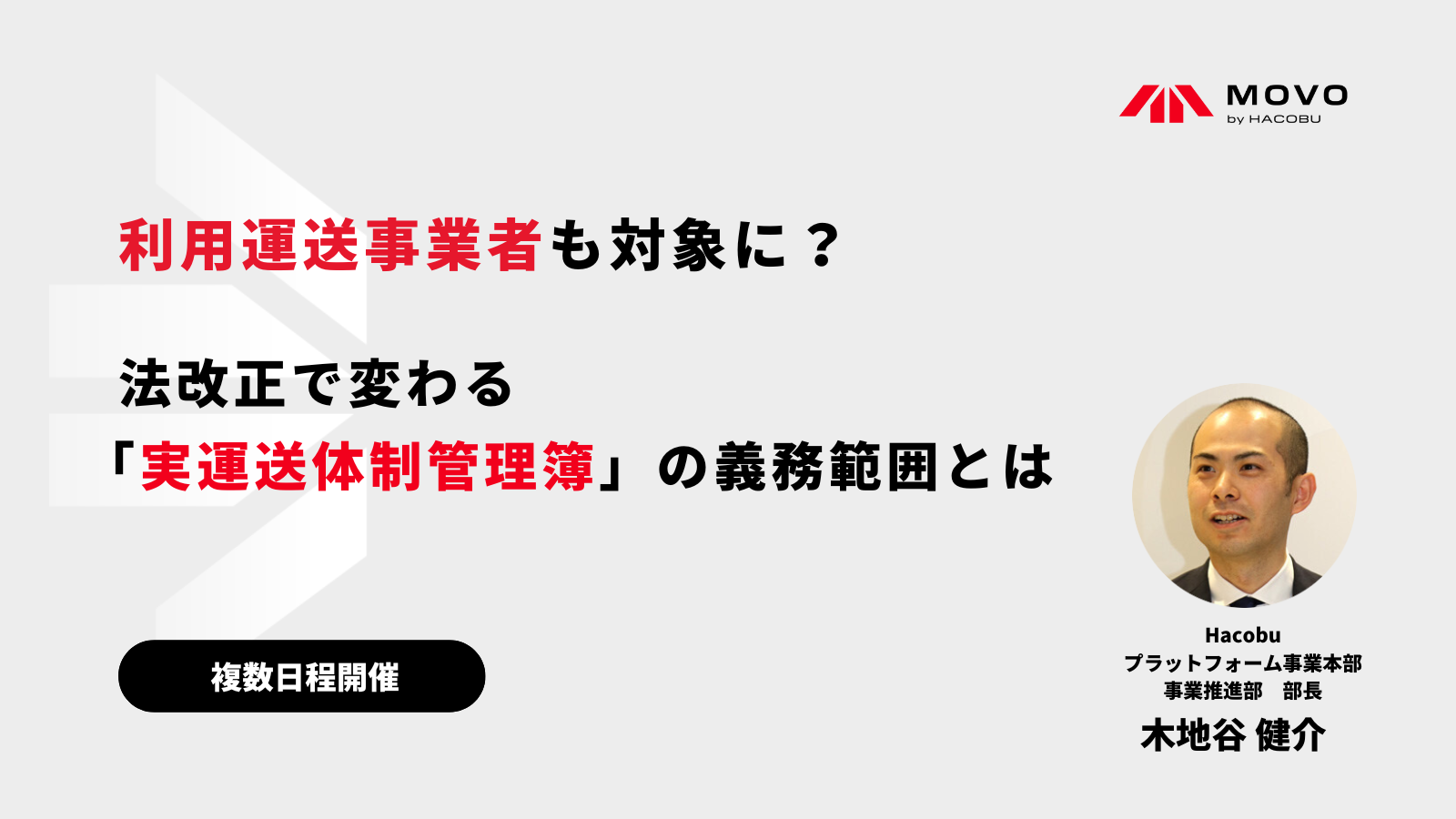【最新】デジタコは義務化されるのか?タコグラフ装着義務の背景や対象範囲、処分、行政の動向などを解説

物流領域においてドライバー不足や労務規制強化が進むなか、「デジタコの装着は義務化されるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、デジタコの基本だけでなく、タコグラフ装着義務の背景、対象範囲、行政処分、そして行政の動向などについて、物流DXパートナーのHacobuが解説します。
デジタコとは
タコグラフとは、トラックやバスなどの商用車に取り付けられる「運行記録計」で、走行時間や速度の変化を記録し、グラフとして表示することで車両の運行状況を把握できる装置です。道路運送車両法に基づく保安基準では、型式認定を受けた機器を使用することが定められています。
その中でも「デジタコ(デジタルタコグラフ:デジタル式運行記録計)」は、速度・走行距離・運転時間に加え、急加速や急ブレーキといった運転挙動をデジタルデータとして正確に記録します。データはSDカードやクラウドに保存でき、クラウド型であれば管理者がリアルタイムに状況を把握することも可能です。
アナタコとの違い
従来のアナタコ(アナログタコグラフ)は円盤型のチャート紙に記録する方式で、視覚的に確認しやすい反面、精度や改ざん防止の面に課題がありました。一方で、デジタコはデジタルデータとして保存できるため、客観性と信頼性が高く、労務管理や監査対応、経営改善に直結するツールとしての価値が高いのが特徴です。
デジタコの目的と重要性
デジタコの目的は、ドライバーの労働時間を正確に把握し、安全運転を支援することにあります。加えて、蓄積された運行データを活用することで、効率的な配車や経営改善にもつながります。こうした幅広い効果を持つことから、国土交通省もデジタコを物流革新の重要施策の一つに位置付けています。その背景には、労務規制の強化や深刻化するドライバー不足に対応し、労働環境の改善と安全性の確保を同時に実現する狙いがあります。
デジタコ導入によって期待できる主な効果は以下の通りです。
- 運行管理の効率化:速度・走行距離・位置情報を自動で取得し、配車計画や稼働状況をリアルタイムに把握。
- 安全性の向上:急加速・急ブレーキなどの危険挙動を検知し、安全指導や事故防止に活用。
- 労務管理の強化:運転時間や休憩時間を自動集計し、過労運転防止や監査対応を容易化。
- 経営改善:燃費やアイドリング時間を分析し、コスト削減・環境対策・経営戦略の立案に活用。
このように、デジタコは単なる法令遵守のための装置ではなく、企業の競争力を高める経営資源としての役割も果たします。
法定三要素の記録義務
デジタコが重要視されるのは、労務管理や安全性の向上だけではありません。運送事業者には法令で定められた記録義務があり、その遵守にデジタコが大きな役割を果たします。
具体的には、貨物自動車運送事業では特定の自動車について、瞬間速度・運行距離・運行時間(いわゆる法定三要素)をタコグラフで記録し、1年間保存することが義務付けられています。
デジタコの種類と機能の違い
デジタコは搭載される機能によって、大きく4つのタイプに分かれます。
単機能型デジタコ
単機能型のデジタコは、運行管理に最低限必要とされる基本的な機能だけを備えたシンプルな機器です。主に「速度」「距離」「時間」という3項目を記録する仕様で、複雑な操作を必要とせず直感的に使えるのが特徴です。導入コストをできるだけ抑えたい方や、初めてデジタコを使う方に適しています。多機能モデルと比べて価格も安く、必要不可欠なデータを確実に記録・管理したい場合に選ばれるケースが多い製品です。
標準型デジタコ
標準型のデジタコは、基本機能である「速度」「距離」「時間」の記録に加えて、ドライブレコーダーとの連携機能を持つモデルです。単機能型と多機能型の中間に位置し、性能とコストのバランスに優れているのが特徴です。 万が一事故が発生した際には、ドライブレコーダーと連動して映像を残せるため、安全対策やトラブル解決に役立ちます。さらに、日報作成や帳票出力といった運行管理業務を効率化する機能も搭載されており、多くの事業者にとって導入しやすい仕様となっています。
多機能型デジタコ
多機能型デジタコは、標準モデル以上の機能を備えたハイスペックなタイプです。速度・距離・時間の記録に加え、燃費の詳細分析やドライバーのアルコールチェック機能などを搭載しており、業務効率の向上や安全性の強化に大きく寄与します。 また、ドライバーの体調管理や運行状況の可視化にも役立つため、輸送品質の向上につながる点が魅力です。ただし、価格は比較的高く、機種によっては数十万円規模になるケースもあるため、導入の際はコスト面を十分に検討する必要があります。
次世代多機能型デジタコ
多機能型デジタコの中でも最上位クラスにあたるモデルは、幅広い連携機能を備えており、詳細な運行データを一括管理したい事業者に最適です。クラウド対応やドライブレコーダー一体型が一般的で、アルコールチェックとの連携はもちろん、居眠り検知、車線逸脱警告、荷室内の温度管理、タイヤ空気圧のモニタリングなど、多様な安全支援システムと連動可能です。 さらに、豊富な画面表示や帳票出力によって運行管理の効率化が進み、対応機器も今後拡大していくことから、将来的な拡張性にも優れている点が大きな魅力です。

デジタコ義務化の最新動向
本章では、デジタコ装着の義務化について動向を解説します。
貸切バス:2025年4月からの義務化対象
2022年に静岡県で発生した貸切バスの事故を契機に、2025年4月からは貸切バスにおいてデジタコの装着義務化が適用されました。これは安全管理を強化する第一歩として位置付けられ、人命を扱う旅客輸送分野において先行的に導入されたものです。
参考:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000601.html
トラック:普及率に対する目標の設定
貨物輸送分野に対するデジタコ装着の義務化は、現状はありません。
現行の制度では、タコグラフの設置義務があるのは「車両総重量7トン以上、または最大積載量4トン以上の事業用普通自動車」など、一部の車両に限定されています。また、機器の種類については特に規定がなく、アナログ式・デジタル式いずれのタコグラフでも認められています。
一方で、政府が打ち出した「物流革新に向けた政策パッケージ」を受けて設置された「デジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会」では、デジタコの義務化を視野に入れた議論が進められており、今後の制度改正により義務化される可能性があります。
この検討会ではこれまでに3度の会合が行われ、その中で以下のように「普及目標」と「普及策の設定」が提示されました。
- デジタコの装着率を高めるための施策を実施し、2027年度には装着率85%を達成する
- その後さらに取り組みを進め、装着率100%を目標とする
ただし、現行の制度と対照車両に変更は予定されていません。
参考:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001758508.pdf

デジタコ装着が推進される背景と目的
前述のとおり、デジタコのさらなる普及は、国土交通省が推進する「物流革新」の重要施策の一つとして検討が進んでいます。本章では、なぜ国土交通省がデジタコの装着を強力に推進しているのかを解説します。
ドライバー不足と物流危機
運送業界では深刻なドライバー不足が続いており、2030年には国内の荷物の約3割が運べなくなる可能性が指摘されています。このままでは物流が滞り、経済活動そのものに深刻な影響を及ぼしかねません。こうした「物流の危機」を食い止めるためには、限られた人材で効率的かつ安全に運行できる仕組みが不可欠です。その解決策の一つとして、デジタコの装着が位置付けられています。
事故防止と安全対策
ドライバー不足の中で一人ひとりの安全を守り、事故を未然に防ぐことは最優先課題です。デジタコは速度や急ブレーキなどの運転挙動を自動的に記録・分析でき、客観的なデータに基づいた安全指導を可能にします。その結果、事故率の低下や企業の安全体制強化につながり、社会全体の交通安全にも寄与します。
働き方改革と労務管理
さらに、「物流の2024年問題」に象徴されるように、時間外労働の上限規制が導入されました。従来のアナログ管理では労働時間を正確に把握することが難しく、過労運転の防止にも限界がありました。デジタコを導入することで、運転時間や休憩時間を高精度に自動記録できるため、労働時間の適正管理が可能となります。これにより、ドライバーの健康を守るだけでなく、持続可能な働き方を実現し、業界全体の労働環境改善にも直結します。
タコグラフ装着義務の対象車両
タコグラフ装着の義務は、すべての商用車に一律で適用されるわけではありません。
事業用自動車の対象範囲
現在、タコグラフの装着が義務化されている車両は大きく4つのカテゴリに分けられます。
事業用トラック
まず1つ目は事業用トラックです。ただし前述のとおり、すべてのトラックが対象ではなく、車両総重量が7トン以上、もしくは最大積載量が4トン以上の事業用トラックに限定されています。
タクシー・ハイヤー
2つ目はタクシーやハイヤーです。こちらも条件があり、対象となるのは大都市圏で稼働する法人タクシーや法人ハイヤーに限られます。そのため、個人タクシーや地方で営業する法人タクシー・ハイヤーは対象外です。
貸切バス
3つ目は貸切バスです。こちらについては2024年4月からデジタルタコグラフの義務化が始まりました。新車は2024年4月1日以降に新規登録された車両が対象となり、既存車両については2025年4月1日から義務化されました。
路線バス
最後の4つ目は路線バスです。他の車種のような条件はなく、基本的に全ての路線バスが義務の対象となります。
このようにまとめると、緑ナンバーで運行される車両は、原則としてタコグラフ(デジタル・アナログ問わず)の装着が義務付けられているといえます。
白ナンバー車両の取り扱い
白ナンバー車両(自家用車)は監査や行政処分の対象にはなりませんが、車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上の場合にはタコグラフの装着が必要とされています。この条件に該当する車両では、タコグラフが装着されていなければ車検を通過できないと言われています。
参考:https://www.tohosvc.co.jp/blog/438/
また、義務対象外の車両であっても、社用トラックやバンを業務利用している企業ではデジタコを自主的に導入するケースが増えています。背景には、安全管理や労務管理を強化したいというニーズがあります。ドライバーの勤務実態を「見える化」することは、労災リスクの低減やコンプライアンス体制の整備に直結します。さらに、事故発生時に「安全配慮義務を尽くしていなかった」と判断されるリスクを抑える効果も期待できます。
義務違反時の罰則と影響
タコグラフ装着は単なる推奨ではなく、法的義務として定められています。そのため、未装着や記録不備などがあった場合には、事業者対して行政処分や反則金などのペナルティが科される可能性があります。
タコグラフに記録しなかった場合の行政処分
たとえば、タコグラフを搭載すべき車両に未装着のまま運行した(すべて記録なし)場合、初違反では30日間の車両使用停止処分が科される可能性があります。さらに再違反時には最大60日間まで延長される可能性があり、事業継続に直結する重大なリスクとなります。
参考:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_k110.pdf
不備・故障などに伴う反則金
デジタコを含むタコグラフを装着していても、SDカードの未挿入、故障を放置したままの運行、データ記録漏れなどがあれば違反となります。行政処分はありませんが、道路交通法における「運行記録計不備違反」となり、大型・中型車では6,000円、普通車では4,000円の反則金が科される可能性があります。
記録不備は、監査対応や労務管理の信頼性を損なう要因となり、コンプライアンスリスクを高める結果にもつながります。したがって、機器の状態確認や定期的な点検を行い、記録が正常に保存されているかを常にチェックする体制づくりが重要です。
参考:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html
まとめ
デジタコは、ドライバーの労務管理と安全管理を支える上で欠かせないツールです。特にカード型デジタコは比較的安価で導入しやすく、多くの事業者が利用してきました。
しかし、2024年の改正改善基準告示に伴い、運転時間・休憩時間(例:430休憩)などの稼働時間管理に苦労している事業者の声が増えています。その背景には、カード型デジタコがリアルタイムでドライバーの稼働状況を把握できず、データ確認のためにSDカードを抜き差しする手間が必要になるという課題があります。
一方で、クラウド型デジタコに切り替えればリアルタイム管理が可能になりますが、初期費用やランニングコストが大きな負担となるケースも少なくありません。そこで最近では、既存のカード型デジタコを使いながら、動態管理サービス MOVO Fleet を追加活用し、安価にリアルタイムな管理体制を構築する事例が増えています。

MOVO Fleetの資料は以下からダウンロードいただけます。
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主