荷主勧告制度とは?荷主勧告を受ける荷主の行為、企業に求められる対応などを解説

荷主勧告制度とは、トラック運送事業者(貨物自動車運送事業者)が法令違反を行った際に荷主が主体的に関与していた場合、国土交通省が荷主に当該違反行為の再発防止を図るための措置を執るべきことを勧告する制度です。本記事では、荷主勧告制度の定義、荷主勧告を受ける荷主の行為、荷主に求められる対応などについて物流DXパートナーのHacobuが解説します。
この記事でわかること:
- 荷主勧告制度はますます厳格化されている
- 勧告を受けると荷主名と事案が広く公表される
- 荷主の対象は発荷主だけでなく、着荷主や元請け事業者も含まれる
荷主勧告制度について解説した資料はこちらからダウンロードいただけます。
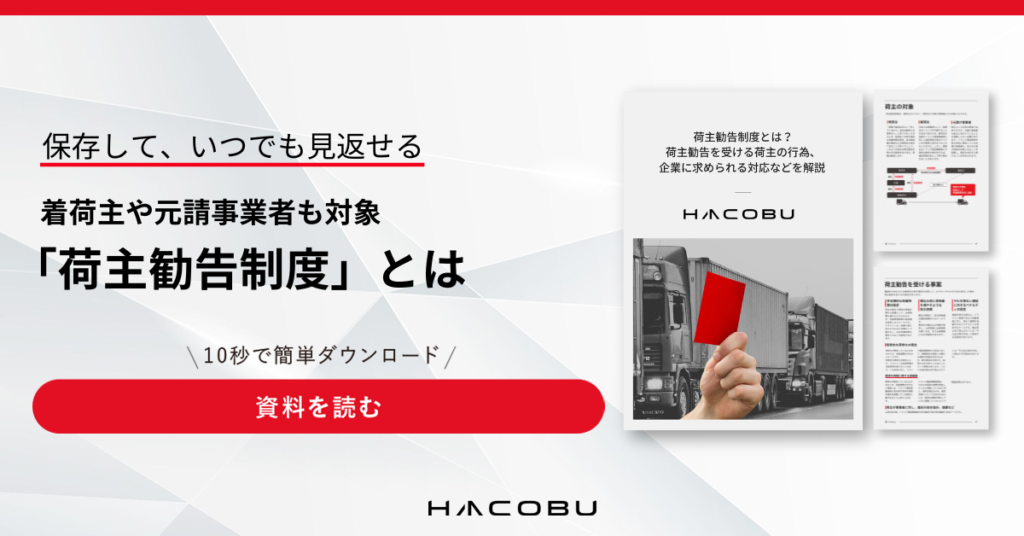
目次
荷主勧告制度とは
荷主勧告制度とは、貨物自動車運送事業法第64条に基づき、トラック運送事業者の法令違反に荷主が主体的に関与していた場合に、国土交通省が荷主に対して当該違反行為の再発防止を図るための措置を執るべきことを勧告できる制度です。この制度は物流業界における法令遵守の徹底を目的として設けられており、荷主の責任を明確化することで、運送業界全体の労働環境改善と安全確保を促進しています。
勧告が行われると、その荷主名と事案の概要が公表されるため、荷主にとっては社会的信用への影響も避けられません。特に近年は「物流の2024年問題」に関連して制度の強化が進み、荷主企業における法令遵守体制の確立がますます重要となっています。
荷主勧告制度の目的
荷主勧告制度は、法律違反の再発防止や安全な運行管理を促すことを目的としています。
法令違反の対象となる行為
貨物自動車運送事業法で定められている以下のような法令違反行為に対し、荷主が影響を与えた場合(違反原因行為)に適用されます。
- 過労運転
- 過積載
- 速度超過
また、トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、公正取引委員会に通知されます。
トラックの過積載とは|リスクや罰則、通報先、最大積載量の確認方法を解説
過積載とは…
2026.02.18
改正改善基準告示の概要と影響
トラック運送事業者は、運転者の過重労働を防ぐため「改善基準告示」に基づき労働時間を管理する義務があります。
2024年4月には、改正改善基準告示が適用され、トラック運送事業者はさらに細かな労働時間の管理が求められています。
改善基準告示とは?荷主として1日13時間ルールを理解し、対策しよう
物流「2024年…
2026.02.25
2014年の貨物自動車運送事業法改正ポイント
2014年の改正以前、荷主勧告の発動には、過去3年以内に協力要請書が発出されていることが要件となっていました。しかし、改正によりこの要件が撤廃され、荷主勧告の要件に該当する場合、協力要請書なしで荷主勧告を発動できるようになりました。また、荷主勧告には至らないものの、荷主の関与が認められる場合には、警告書を発出できるようになり、結果的に荷主勧告が発動されやすくなりました。
2018年改正のポイント
2018年には、さらに以下の改正が行われました。
荷主の配慮義務を新設
荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をする責務規定が新設されました。
荷主の勧告制度を拡充
荷主勧告制度の対象に貨物軽自動車運送事業者が追加され、これまで規制対象外だった小規模業者にも監督が及ぶようになりました。さらに、荷主勧告が発動された場合、荷主名と事案の概要が公表される規定が明記されました。
国土交通大臣による働きかけなど
国土交通大臣は関係省庁と連携して、法令違反の原因となる疑いがある荷主に対し、荷主による配慮への理解を求める「働きかけ」などを行う規定も設けられました。
なお、当初は2024年3月末までの時限措置でしたが、時期を「当面の間」と修正し、2024年10月時点では無期限となりました。
荷主勧告制度について解説した資料はこちらからダウンロードいただけます。
荷主勧告制度の勧告・公表までの流れ
実際に勧告・公表が発動されるまでには、いくつかのステップがあります。以降で解説します。
荷主勧告該当性調査の流れと判断基準
国土交通省は地方支分部局や関係省庁から、荷主の違反原因行為に関する情報を収集します。
トラック運送事業者が過労運転や過積載、速度超過といった法令違反行為や、死亡事故などの重大事故を発生させた場合、かつ荷主の関与が疑われる場合に、その荷主の関与について調査がされます。(荷主勧告該当性調査)
荷主の関与について、「運送契約書」、「運送状(委託書)」、「運送引受書」などの書面の記載内容のほか、運行記録、荷待ち時間記録、事業者からの供述、荷主からのヒアリングなどから調査します。
また荷主勧告該当性調査は、地方運輸局において主体的に実施されます。
荷主への働きかけから勧告・公表までのプロセス
法令違反の原因となる疑いがある荷主に対しては、前述の働きかけを行います。そのうち、違反原因行為を疑うことに相当の理由がある荷主に対しては、「要請」を行います。そして要請をしても改善されない荷主に対し、荷主勧告書を発出し、勧告・公表となります。
違反原因行為に相当な理由がある場合、働きかけを行わずに要請を行う場合もあります。
また前述の通り、トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、公正取引委員会に通知します。

異議申し立ての方法
処分または不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われます。なお、審査請求に費用はかかりません。
参考:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou02.html
直接、勧告・公表になる重大違反事例
荷主勧告の要件に該当する場合、直接、勧告・公表になる可能性もあります。

荷主の対象とは?
荷主勧告制度は、発荷主だけでなく、着荷主や元請け事業者もその対象となります。
発荷主の定義と責任
「保管や輸送は3PLに一任しているから、自社は勧告とは関係ない」と思うかもしれませんが、配送先への非合理的な到着時間の設定、急な輸送量の増加などは発荷主の指示であることが多いでしょう。このような指示は荷主勧告を受ける可能性があります。詳細は後述します。
着荷主の責任と対応
日本では商慣習として、発荷主がトラックを手配することが主流であるため、着荷主は自身がトラック運送事業者に対して違反原因行為を行っている可能性に気付きづらいかもしれません。しかし、着荷主もトラック運送事業者に不適切な要求や指示を行えば、違反原因行為として取り扱われることがあります。
元請け事業者の責任と荷主勧告対象
荷主という名称の制度ではありますが、元請け事業者も荷主に含まれていることを理解しておく必要があります。トラック運送業務を協力会社に委託している元請け事業者も、自らの行為が制度の対象となることを認識し、適切な対応を心掛けることが求められます。

自社が対象かどうかの判断方法
自社が荷主勧告制度の対象となるかは、まず「物流委託契約の内容」「運賃の設定方法」「発注頻度や条件変更の有無」をチェックすることが出発点です。製造業や小売業など、業種ごとに典型的な取引慣行があります。例えば製造業では突発的な発注変更、小売業では短納期指定がリスク要因になりやすい事例です。業種別の基準や過去の行政処分例を参考に、自社の商習慣を点検することが重要です。
荷主勧告を受ける具体的な事案
優越的な地位または継続的な取引関係を利用して、以下のいずれかの行為を該当した場合、荷主勧告を受ける可能性があります。
非合理的な到着時間の設定
荷主の都合で積荷の準備が遅れた結果として、出発時間も遅れたにもかかわらず、到着希望時間や指図書を変更しないケースです。ドライバーは、納期に間に合わせるために休憩なしで運行をし、法定労働時間を遵守できない可能性があります。
積込み前の急な貨物量増加依頼
積込み直前に、急な貨物量の増加依頼をするケースです。
想定外の積み込み作業が発生し、上記同様に出発時間が遅くなる、または過積載になる可能性があります。
やむを得ない遅延に対するペナルティの設定
事故渋滞や災害など、ドライバー起因ではない到着遅延に対し、支払う運賃を減額するなどペナルティを設定するケースです。独占禁止法で禁止されている「不公正な取引方法」に該当する可能性があります。
恒常的な荷待ちの発生と対策
荷待ちが発生しているにもかかわらず、改善措置を行わないケースです。
恒常的な荷待ちの発生により、ドライバーの拘束時間が法定基準を超えることもあり、この状況に対し、トラック運送事業者から荷主に対して、時間設定の見直しや積み込み場所の改善を求めたものの、取引解消を示唆され、結局そのまま従うしかなかったという事例もあります。こちらも独占禁止法で禁止されている「不公正な取引方法」に該当する可能性があります。
荷待ち・荷待ち時間とは|概要や現状、発生する9つの原因、影響、行政の取り組み、改善・削減方法などを解説
荷待ち時間…
2025.12.26
荷主と運送事業者間の荷待ち時間認識の違い
荷待ちが発生しているにもかかわらず、改善措置を行わない理由には、トラック運送事業者側と荷主側で荷待ち時間の発生を認識している割合に差があることも考えられます。
トラック運送事業者側は73.4%が荷待ち時間が発生していると認識しているのに対し、発荷主側は24.0%、着荷主側にいたっては20.6%ほどしか、荷待ち時間が発生していると認識していないという調査結果もあります。
荷主が運送事業者に対し違反行為を指示・強要するケース
上記4点の他、トラック運送事業者の法令違反行為が荷主起因であるケースです。
荷主勧告の内容と公表事項
ここでは、実際に勧告された際の内容、公表事項と方法について解説します。
勧告の内容
勧告は違反原因行為の内容に応じて、個別具体的にその再発防止に必要な内容が示されます。端的に記載すると以下のような勧告が発動されます。
- 法令違反に繋がる貨物の到着時刻の設定を行わない
- やむを得ない事情による遅延にペナルティを課さない
- 積み込み前に貨物量を増やす急な依頼をしない
- 荷待ち時間削減のための措置を講ずる
- 過積載となるような運行を指示しない
以下は荷主勧告書の様式です。

公表事項
- 勧告の年月日
- 荷主の名称(支店や営業所名を含む)
- トラック運送事業者の違反行為の概要
- 荷主勧告の内容
その他、過去3年以内に荷主勧告を受けている場合は、過去3年間のすべての荷主勧告事項も公表されます。
公表方法
公表資料を国土交通省のホームページへ掲載、報道機関への提供、定例記者会見などで広く公表されます。
報道機関へ提供された場合、広く国民の目の止まる形になります。
荷主勧告制度について解説した資料はこちらからダウンロードいただけます。
公表後の影響とリスク
荷主勧告が公表された後の企業への具体的な影響として、社会的信用の低下、取引先からの信頼失墜、株価の下落、新規取引の獲得困難などが挙げられます。
リスク軽減のための対策として、迅速な改善計画の策定と実行、ステークホルダーへの適切な説明と謝罪、再発防止体制の構築と公表、監査の実施などが重要となります。また、平時からの法令遵守体制の整備と定期的な見直しにより、そもそも勧告を受けるリスクを最小化することが最も効果的な対策となります。
国土交通省の荷主対策の強化
国土交通省は荷主勧告制度の実行力を高めるために、悪質な荷主に対する対策を強化しています。
トラック・物流Gメンの創設
国土交通省は、トラック運送業界の不適正な取引を監視・是正するため「トラックGメン」を創設しました。この専門チームは、悪質な荷主や元請け事業者に対して是正指導を行い、運送業者が公正な取引条件で事業を行えるよう支援します。特に過剰な運賃の要求や不当な取引が行われないよう、厳格な監視体制を整えています。
2024年11月には「トラック・物流Gメン」に改組・拡充され、倉庫業者からも情報収集を開始するとともに、担当人員の増員と各都道府県トラック協会が新設する「Gメン調査員」の追加により、総勢約360名規模で対応する体制が整備されました。
トラック・物流Gメンとは?創設の背景や体制、活動実績、勧告・社名公表の実例まで解説
今、話題と…
2025.12.26
悪質な荷主対策として「通報窓口」を設置
国土交通省は、悪質な荷主に関する情報を集めるために通報窓口(目安箱)を設置しました。寄せられた情報は、トラックGメンによる是正指導に活用され、業務の効率化に貢献します。
参考:自動車:悪質な荷主等に関する通報窓口(目安箱) – 国土交通省
荷主に求められる対応
荷主勧告制度が厳格化している中、荷主に求められているのはどのような対応なのでしょうか。
法令遵守のための社内教育と研修体制の強化
労働基準法や道路交通法などの関連法令について社内で教育を徹底し、トラック運送事業者への不適切な指示が出ないようにしましょう。コンプライアンスの強化は、違反リスクを軽減する重要な要素です。
定期的な内部監査の実施
社内で、トラック運送事業者に対する指示や要求に問題がないかを定期的に監査し、改善すべき点を洗い出して是正措置を講じましょう。これにより、不当な要求や指示を未然に防ぎます。
慣習的な業務フローの見直し
トラック運送事業者との取引を円滑に進めるためには、従来の慣習を見直し、合理的な業務フローを構築することが重要でしょう。
無理な到着時間を指定せず、交通状況や作業量を考慮した柔軟なスケジュール設定を行うことで、トラック運送事業者に負担をかけないよう配慮します。また、積込み直前の仕様変更や追加依頼はトラック運送事業者に大きな影響を与えるため、事前計画に基づいた依頼を徹底し、緊急変更は最小限に抑えることが求められます。さらに、やむを得ない遅延に対するペナルティを無くし、契約条項の見直しも必要です。
荷待ち時間の把握・削減
トラック運送事業者にかかる荷待ち・荷役時間を適切に把握し、可能な限り削減する取り組みを行いましょう。
荷主勧告該当性調査では荷待ち時間記録も調査対象になること、またトラック運送事業者側と荷主側で荷待ち時間に関する認識差があることを前述しました。
「自社では荷待ちが発生していないと認識していたが、荷待ちが発生していると通報があった。しかし、荷待ち時間を記録していなかったので、荷主勧告該当性調査で荷待ちが発生していないことを証明できなかった。」このようなことがないようにしましょう。
荷待ち時間の把握・削減ならMOVO Berth
荷待ち時間の把握・削減には、トラック予約受付サービスMOVO Berth(ムーボ・バース)が有効的です。
MOVO Berthの資料は以下からダウンロードいただけます。
荷待ちが発生するのは、一定の時間にトラックの到着が集中してしまうことが要因です。MOVO Berthを活用し、トラック運送事業者に自社の物流拠点への入場を事前に予約いただくことで、トラックの到着を計画的に分散し、荷待ち時間を削減できます。

入退場時間、予約時間、作業時間を集計し、何時頃に何分くらいの荷待ちが発生しているかを把握することも可能です。

さらに複数拠点を横断して、特にリスクのある拠点を可視化することも可能です。

有責待機とは?バースの予約運用で本質的な荷待ち時間削減に取り組もう
目次1 有責待機&…
2025.12.26
このようにMOVO Berthを活用することで、認識していなかった荷待ち時間を把握し、削減に取り組むことが可能になります。長時間の荷待ち時間がないとしても、荷主勧告該当性調査が入った場合に、長時間の荷待ち時間がないことの証明にもなるでしょう。
前述のとおり、勧告を受ける事案は複数あります。いずれの事案を1つでも放置をしていると勧告のリスクは高まります。自社の物流拠点で恒常的な荷待ちが発生していないか、データを元に把握、そして削減していきましょう。
MOVO Berthの資料は以下からダウンロードいただけます。
荷主勧告制度について解説した資料はこちらからダウンロードいただけます。
物流DXとは?課題解決と2024年問題対策、業界特有の成功事例を解説
近年、さま…
2025.12.22
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主





















