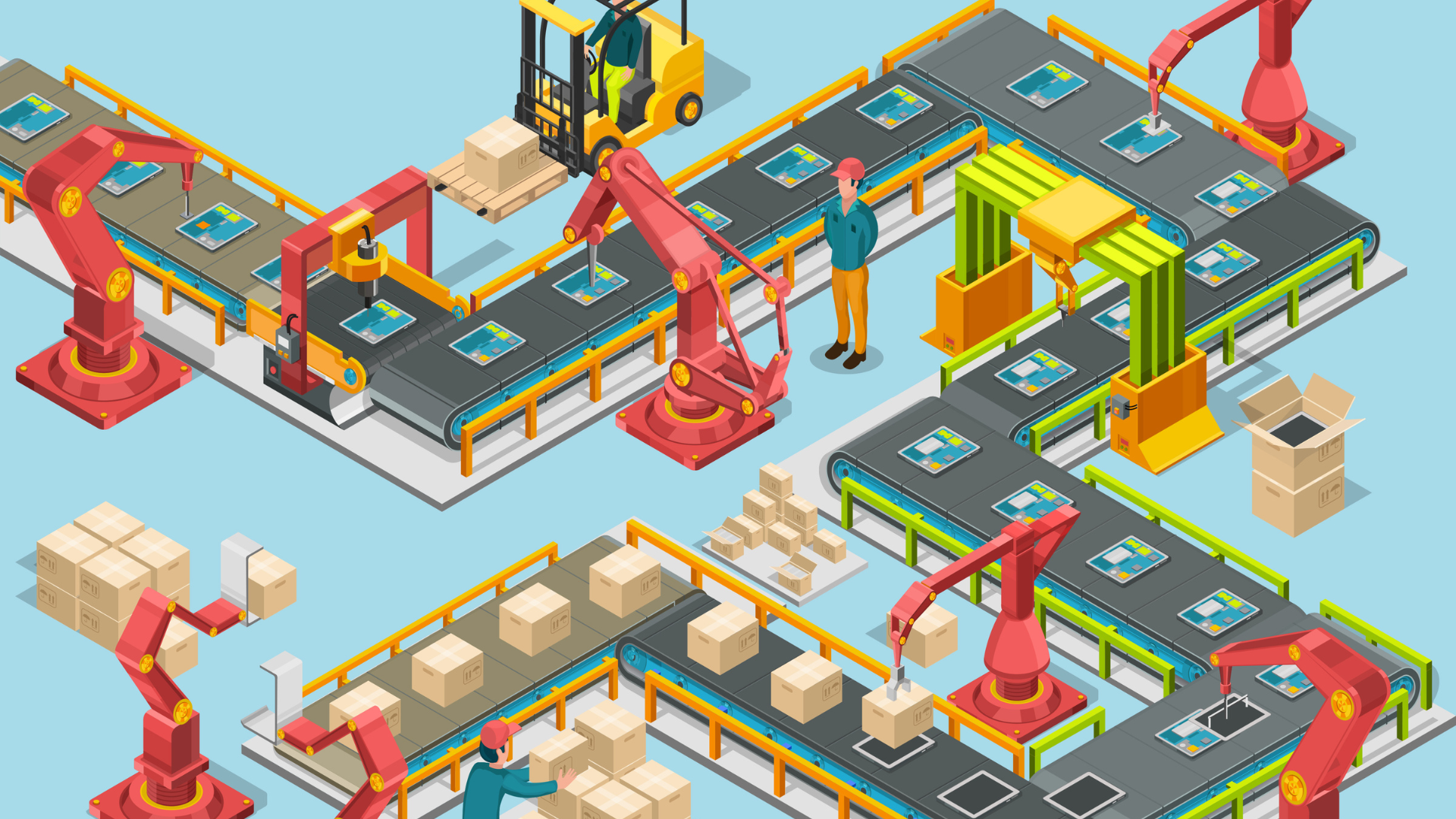有責待機とは?バースの予約運用で本質的な荷待ち時間削減に取り組もう

目次
有責待機とは?
「物流拠点で発生する荷待ち時間のうち、物流拠点が起因の荷待ち時間」を株式会社Hacobuでは「有責待機」と定義し、荷待ち時間の把握・削減のために重要な指標として、その概念を提唱しています。
本記事では、バース予約受付システムを用いて取得できるデータと、それにより可視化できる有責待機について説明します。
荷待ち時間の把握・削減に取り組みたい、しかし具体的にどのように取り組めばいいかわからないとお考えの物流拠点の方はぜひご一読ください。
なお以降ではバース予約受付システムでシェアNo.1* である MOVO Berth をシステムの代表例として説明に用います。MOVO Berthに備わる機能を前提として説明するため、他システムでは難しい運用パターンも考えられますのでご了承ください。
荷待ち・荷待ち時間とは|概要や現状、発生する9つの原因、影響、行政の取り組み、改善・削減方法などを解説
荷待ち時間…
2025.12.26
この記事で分かること
- バース予約受付システムを用いて、予約運用を行うことで有責待機が明確になる
- 予約運用を行い、予実の精度を上げることで有責待機を削減することができる
- 予約運用を正しく行うことで、ドライバーも含めて関係者が皆、効率化できる
有責待機について解説した資料はこちらからダウンロードいただけます。
受付のみの運用と、予約まで行う運用では取得できるデータが異なる
物流拠点において、車両の入退場を管理するパターンは大きく以下3つあります。
- 紙の受付簿で入退場を記入するパターン
- システムを用いて受付運用のみをするパターン
- システムを用いて予約・受付運用をするパターン
以降でそれぞれを説明します。
紙の受付簿で入退場を記入するパターン
まず、紙の受付簿で入退場の時間を記入しているパターンです。この場合、Excelなどの表計算ソフトに転記作業を行わない限り、入退場の時間は電子データとして保持できていません。つまり入退場時間を後から確認・分析することは困難でしょう。
電子データとして保持し、確認したとしても入場から退場までの合計時間しか分からず、その間にそれぞれ荷待ち・荷役が何時間かかっていたかはわかりません。
システムを用いて受付運用のみをするパターン
次に、MOVO Berthなどのシステムを用いて入退場の受付のみを行う運用パターンを説明します。

MOVO Berthの場合、事務所の受付などにタブレット端末を設置し、受付画面を表示しておきます。そしてドライバーが物流拠点に入場、そして退場する際にタブレットで受付をしていただきます。ドライバーが入退場を受付した時間をMOVO Berth上で取得でき、電子データとして保持している状態になります。
物流拠点側は、荷役の準備ができた段階でドライバーをバースに呼び、荷役を開始、そして終了します。入退場時間と同様にこれらの時間はMOVO Berth上に保持されます。


これらの時間の差分により、入場から退場までの時間において、荷待ち・荷役それぞれの時間が把握できます。

システムを用いて予約運用をするパターン
荷待ち時間の把握は重要ですが、次はこの荷待ち時間をどう削減していくかを考えていかなくてはなりません。
荷待ち時間を削減するためには、まずこの荷待ち時間をさらに分解し、なぜ荷待ちが発生しているのかを把握していく必要があります。把握する方法として「予約運用」を行うパターンがあります。「荷待ち時間」という尺を、予約時間を起点として二分割するのです。
予約運用の流れとして、まず、配送手配事業者やドライバーは事前にMOVO Berth上で荷役の予約をします。そして物流拠点側がこの予約を確認し、確定します。これによりドライバーは「早い者勝ち」ではなく、この予約時間までに入場することになります。入場以降は受付のみの運用と同様です。
予約運用を行うと有責待機が明確になる
予約時間を起点として、それより早くドライバーが入場した場合は「物流拠点が指定したよりも早く入場した」といえます。つまり物流拠点が荷待ち時間を発生させたとはいえません。一方で、予約時間よりも車両をバースに呼び出した時間が遅くなった場合は「物流拠点が待たせた」といえます。この時間が有責待機です。
受付のみの運用では把握できなかった、有責待機とドライバー都合による荷待ち時間が明確になります。

有責待機について解説した資料はこちらからダウンロードいただけます。
有責待機の削減に向けて、物流拠点がすべきこと
物流拠点としては、有責待機の削減に取り組むことで、入場から退場までの総時間を削減することができます。
そのために以降で、まず入場から退場までの目安時間である「2時間以内ルール/1時間以内努力目標」について説明し、そして入場から退場までの時間をどのように削減していくべきかについて説明します。
2時間以内ルール/1時間以内努力目標
経済産業省、農林水産省、国土交通省が策定した「物流の適正化・生産性向上に向けた 荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」において、発荷主・着荷主は以下について実施が必要な事項として明記されました。
- 荷待ち時間・荷役作業等に係る時間の把握
- 荷待ち・荷役作業等時間の2時間以内ルール/1時間以内努力目標
つまり全ての発荷主・着荷主は、まず荷待ち・荷役の時間を把握したうえで、入場から退場まで2時間以内にすべきであり、可能であれば1時間以内に収めることが望ましいという提言がされました。
なお、例えば重い貨物を取り扱うために荷役時間が長くなる業界では、2時間以内ルール/1時間以内努力目標への対応が難しい場合もあります。このような場合は業界としての自主行動計画を策定し、業界として定めた最適な時間が努力目標になります。
また、2024年5月時点で有責待機については、どのくらいの時間に収めるべきかといった目標は行政としても明確な発信はありません。
しかし、いずれにしても業界特性が考慮されるのは荷役時間です。荷役時間と、荷待ち時間・有責待機は切り分けて考えるべきです。まずは有責待機の削減に努めることが、2時間以内ルール/1時間以内努力目標への対応として有効となります。
荷役時間を削減する
精緻な作業計画を立てる
そもそもなぜ有責待機が発生するか、それは荷役の計画と実績の乖離に原因があります。
以下のように、同じバースで車両Aの荷役時間以降に、車両Bの荷役の作業計画をしていてもAの作業で遅延が発生すれば、その時間は車両Bにおいては有責待機となります。

つまり精緻な作業計画を立てることで、有責待機の削減ができるわけです。

精緻な作業計画を立てる際には、MOVO Berthの「作業時間の自動反映機能」を使うことも有効です。荷役をしに入場する車両が10トン車なら60分、4トン車なら30分など、予約時の車両情報でバースの作業時間を自動反映でき、精緻な作業計画の策定を支援します。
精緻な作業計画は一朝一夕では立てられず、MOVO Berthで予実管理をしながら精度を上げていきましょう。
荷役時間を効率化する
またMOVO Berth上で事前に取得した入出荷情報を物流拠点内に共有することで、荷揃えや伝票突合作業などを事前に済ますことが可能になります。ドライバー入場以前にこれらの作業を行うことで、荷役時間を効率化できるかもしれません。
バラ積みではなくパレット積みにすることで、荷役作業の大幅削減も期待できます。自身の物流拠点だけではなく発荷主・着荷主も巻き込み、物流領域全体で効率化を図っていきましょう。
いかなる業界特性があったとしても、少しでも荷役時間を削減できる方法を考える必要があります。
ドライバー都合の荷待ちに対して、物流拠点がすべきこと
前述の通りで2024年5月時点では、大枠では「2時間以内ルール/1時間以内努力目標」が個社に課せられた努力目標であり、有責待機以外の荷待ち時間をどう削減すべきかについても行政としての明確な発信はありません。しかしこの努力目標を達成するには、荷役、有責待機、ドライバー都合の荷待ち、いずれかの時間を削減する必要があります。荷役時間、有責待機をどのように削減すべきかは前述したとおりです。

本章ではドライバー都合の荷待ちに対して、物流拠点がすべきことを説明します。
有責待機ではないと証明できるようにする
2時間以内ルールは入場から退場までの合計時間のため、ドライバー都合の荷待ちもこの時間内に含まれます。
トラックGメンなどは長時間の荷待ちが発生している物流拠点に立ち入り、実態調査を行うこともあるようです。そして立ち入りの目的は、荷主(物流拠点)が起因の違反原因行為を取り締まることです。
つまりまずは、発生している荷待ち時間が有責待機ではないと証明できることが重要です。
ドライバーの業務効率化に協力する
ドライバーは「走りやすい時間帯に走っておきたい」など自身の労働スタンスにより、予約時間より早く入場することも多いでしょう。このようなケースは物流拠点として対策を取りづらいかもしれません。
しかし自身の物流拠点でドライバーが休憩を取っている時間(休憩時間)も、基本的にはドライバーの拘束時間内であるということを物流拠点側も意識しましょう。
「物流拠点側としては、予約時間までは荷役ができないため、ドライバーにはその時間より前に入場いただく必要はない」と配送手配事業者(や実運送会社)に共有すれば、実運送会社が配送ルートを見直し、ドライバーは1件多く配送できる可能性があります。
また、ドライバーはより長い休息期間を確保し、より遅く業務を開始することができるかもしれません。
その理由を説明する前に、まず拘束時間や休憩時間、休息期間について整理します。
拘束時間や休憩時間、休息期間とは
拘束時間とは、ドライバーの労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻まで、ドライバーが使用者に拘束される全ての時間を指します。
休息期間とは、勤務と次の勤務との間にあって、睡眠時間を含む生活時間として、ドライバーが使用者の拘束を受けない期間のことをいいます。
以下は、ドライバーが予約時間より早めに入場する場合と、ちょうどに入場する場合を比較したイメージ図です。

前者について、入場から予約時間までドライバーは例えば1時間の休憩を取るとします。この1時間の休憩は、取らなくてはいけない休憩ではなく、予約時間まで待つために仕方なく取っている休憩です。
後者のように、ドライバーが予約時間ちょうどに入場できれば仕方なく取っている休憩はなくなり、その分出発時間を遅らせることができます。出発時間を遅らせられれば業務開始時間も遅くでき、結果としてドライバーの休息期間は増えます。
(上記の説明及び、イメージ図は概念的に伝えているものであり、ドライバーの休憩時間を不要に削減する趣旨ではありません。)
また休憩時間は拘束時間に含まれますので、「待つための休憩」が増えればドライバーが輸配送をする労働時間も減っていきます。改善基準告示の改正によりドライバーの拘束時間がさらに制限されたことを踏まえ、「ドライバーの貴重な拘束時間をどのように活用して輸配送を行なっていくか」という視点を持つことが重要です。
改善基準告示についてはこちらの記事でも詳細に説明しています。
ドライバーのことを考え、物流拠点として配送手配事業者(や実運送会社)と連携して何かできることはないか検討しましょう。
ドライバーが健全に休憩できる環境を維持する
ドライバーが荷待ちする環境は快適に保たれているかを確認しましょう。長時間、順番待ちで列に並び車両から離れづらい場合、安心して休憩できていないかもしれません。
物流拠点の駐車スペースが狭いなど、物理的な限界はあるかもしれませんが、それでもドライバーのためにできることはないか、物流拠点の従業員の中で話し合うことは素晴らしいことだと考えます。
延着のペナルティを見直す
延着に対するペナルティが科せられている場合、ドライバーには予約時間よりも早く到着しておきたい心理が働きます。つまりこのペナルティが、ドライバー都合による荷待ちを発生させているといえます。そのため延着のペナルティを見直すことは重要です。
そもそも今後は荷主と物流事業者のパワーバランスは変わっていき、「物流事業者が荷主を選ぶ」時代になるかもしれません。そうなれば、このペナルティという仕組み自体が古い考えになっていくと考えます。
有責待機について解説した資料はこちらからダウンロードいただけます。
ケース別の有責待機に関する考え方
ここからは例を用いながら、有責待機となるか否か、そして当該事例における有責待機の削減に向けた対応策をご紹介します。
予約必須の物流拠点において、予約せずにドライバーが入場した場合
まずは予約運用をしている物流拠点において、予約していないドライバーが入場したケースです。この場合、「ドライバー予約機能」を用いてその場でドライバーに予約を入れていただくことを当社は推奨します。物流拠点側で最短の荷役開始時間を確認し、その時間を予約時間として入れていただきます。予約が完了後、タブレットにて入場受付をお願いしましょう。
物流拠点に入場したのちに予約時間が合意されることになります。この予約時間まではドライバー都合の荷待ち、予約時間を過ぎて荷役開始した場合は、有責待機となります。
以下の例では、AM8時時点でAM10時という予約時間が確定されます。AM10時までは有責待機とはいえません。

ドライバー予約が難しい場合、タブレットで「予約なし」を選択し、入場受付をしていただき、バース割当して、呼出、荷役開始の流れになります。その場でドライバー予約をしていただく際と同じく、AM8時時点でAM10時という予約時間が確定され、AM10時まではドライバー都合の荷待ちです。
ここで重要な点が3つあります。
ドライバーに改めて予約運用を周知する
改めてドライバーには予約運用の周知を行い、予約をしないことでAM8時に入場してもAM10時までドライバー都合の荷待ちが発生してしまうことをご理解いただきましょう。そして次回以降は予約いただくようにお伝えしましょう。また何かしらの理由で予約が難しい可能性も考えられますので、ヒアリングを行って原因を深掘り、運用改善できる点がないかを確認しましょう。
有責待機を少しでも削減する
繰り返しですが、有責待機が発生している場合は削減に取り組みましょう。
予約なしのドライバーを前倒ししない
また「2時間以内ルール」を無理やり遵守するために、予約をしなかったドライバーを前倒しで荷役、予約しているドライバーを後ろ倒しにすることは当社は推奨していません。
以下のような場合でも、車両AのドライバーにはAM10時にその場で予約を入れていただきましょう。

前述のとおり、予約運用をしている物流拠点においてAM10時に予約を確定させた場合、AM8時からAM10時までの時間は有責待機ではなくドライバー都合による荷待ちとなります。ドライバー都合による荷待ちが発生したために、車両Aが入場から退場まで2時間を越えることより、予約時間までに受付をした車両B・車両Cでそれぞれ1時間の有責待機が発生してしまうことの方が問題です。
MOVO Berthでは車両の入退場実績をデータとして見返し、事前に予約があったか、予約なしで入場受付したのかを車両単位で確認できます。車両単位で入場時間と呼び出し時間の差分を計算することで、「呼び出しまでに2時間以上かかった車両Aは予約なしで入場した」と特定できます。トラックGメンなどから指摘が入った際も、有責待機ではないとデータで証明できます。
すべてのドライバーに公平な運用をすることが重要です。
荷役時間は未定だが、早めに呼び出した場合
具体的な荷役時間はまだ未定にもかかわらず、物流拠点側の作業に穴を開けたくないなどの理由で車両を早めに呼び出すことを当社は推奨していません。
この場合には、入場時間から呼び出し時間まで全てが有責待機です。

AM8時のように具体的な時間を指定せずに「最短」とした場合も、事前に合意した明確な時間がないため入場した時間を予約時間として入れていただく必要があります。その予約時間から呼び出しまでが有責待機です。
荷役時間は未定だが、早めに呼び出し、その場で予約を入れていただく場合
前日予約が難しく直前にならないと作業時間が確定できないなどの理由で、前項と同様に早めに入場してもらい、その場でドライバーに予約いただく運用は推奨しません。
事実として物流拠点側の有責待機にもかかわらず、データ上はドライバー都合の荷待ちになってしまうだけでなく、根本的にドライバーの荷待ち削減の解決になりません。事実に基づくデータが取得できる運用にしましょう。

まずは少しずつでも予約運用の定着を
以上で説明したとおり、予約運用を行うことで有責待機を把握するだけでなく、入場から退場までの滞在時間を削減していく方法が見えてきます。有責待機については少しでも削減できるように努め、さらにドライバーの拘束時間を効率化することで「運べなくなるリスク」を一緒に回避していきましょう。
MOVO Berthの導入で多くの物流拠点で荷待ち時間の削減に成功していますが、すべてのお客様が初めから順調だったわけではありません。予約運用の周知や運用ルールの試行錯誤を繰り返しながら、予約率を高めていっていらっしゃいます。
MOVO Berthをご検討のお客様につきましても、導入から運用定着までHacobuのカスタマーサクセス部門が伴走しますのでご安心ください。
*:出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア
有責待機について解説した資料はこちらからダウンロードいただけます。
物流DXとは?課題解決と2024年問題対策、業界特有の成功事例を解説
近年、さま…
2025.12.22
関連記事
-
 COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!
COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!更新日 2026.02.03
-
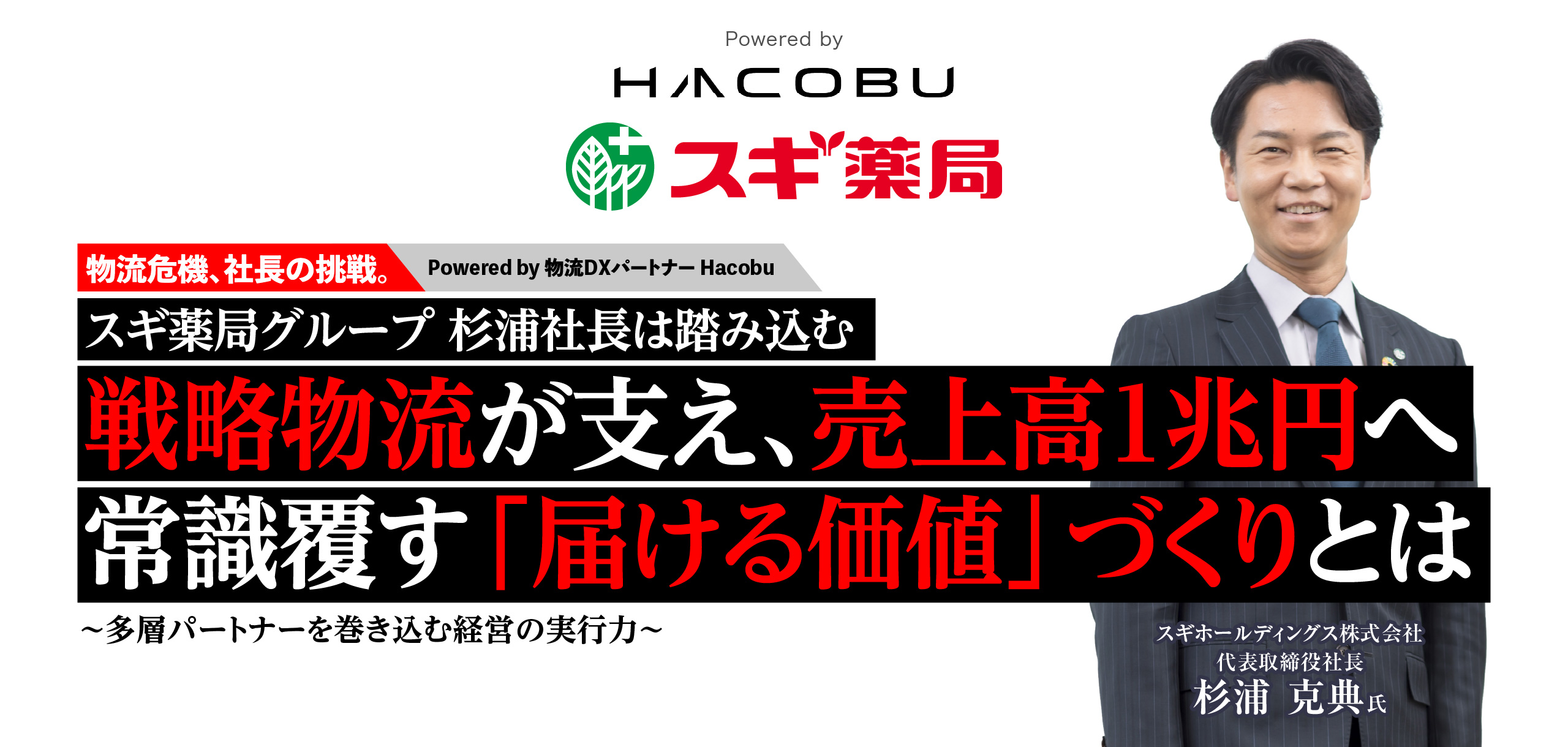 COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~
COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~更新日 2025.11.28
-
 COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?
COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?更新日 2026.01.26
-
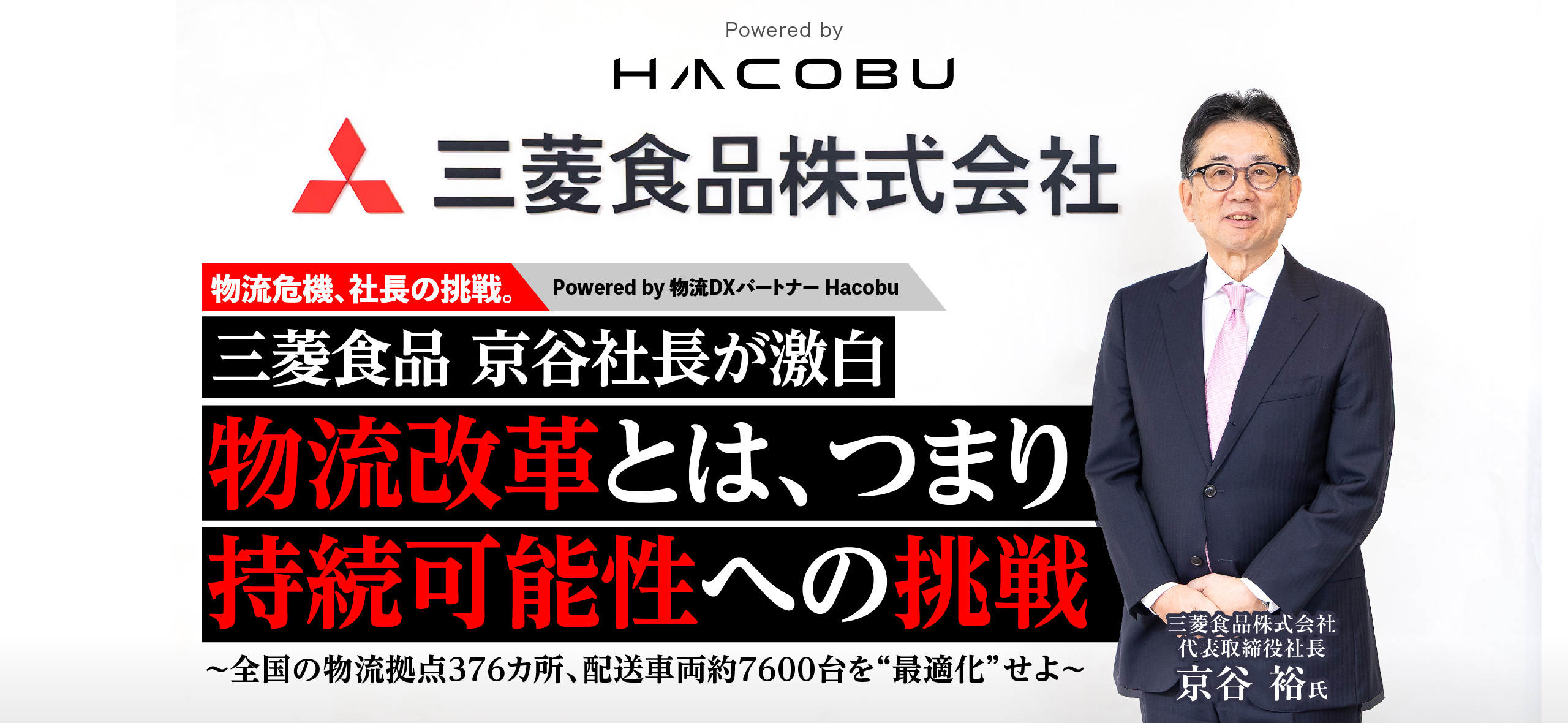 COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~
COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~更新日 2025.11.28
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主