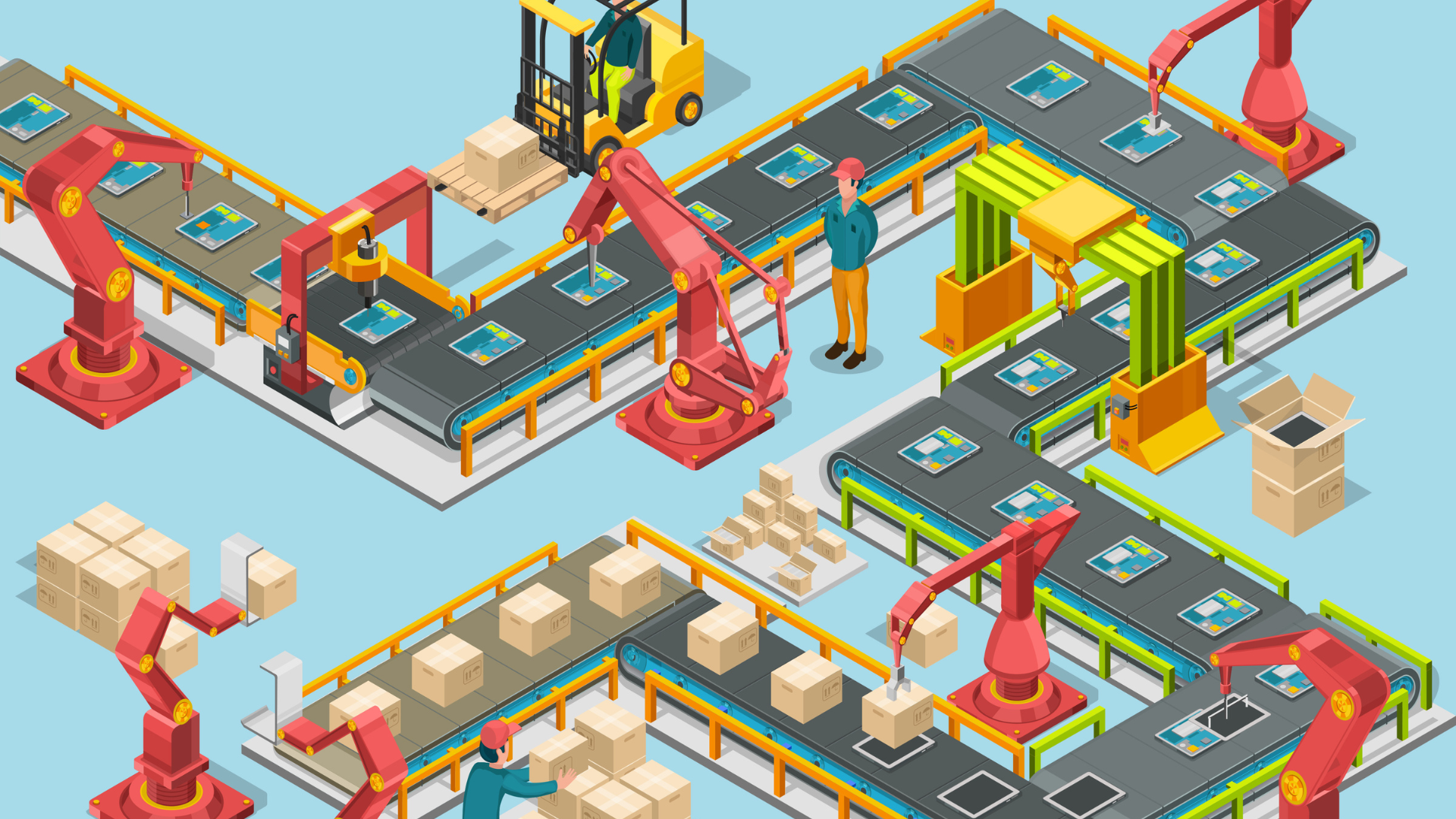業界のイノベーターでありたい〜Hacobuの新ブランドに込めた思い【Hacobu CEO佐々木太郎】

Hacobuがサービスを展開する企業間物流の領域では、トラックドライバーや倉庫内作業者の不足など慢性的な人材不足が課題となっています。加えて、目前に迫る「物流の2024年問題」への対応が急務となる中、2023年5月22日、コーポレート・アイデンティティ(CI)を刷新しました。
新ブランドに込めた思いと、私たちが描く未来構想について、Hacobu代表取締役社長CEO の佐々木太郎が胸の内を語ります。
株式会社Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流管理ソリューション「MOVO」と、物流DXコンサルティングサービスの「Hacobu Strategy」を提供しています。
目次
物流の“これまで”と“今”
物流というと、一般家庭に荷物を届ける宅配便を思い浮かべる人がほとんどではないでしょうか。このラストワンマイルの世界は、3兆円規模と言われています。
物流の多くを占めているのは、メーカーの工場で製造された食品を倉庫へ、倉庫から食品卸のセンターへ運ぶ企業間物流で、30兆円(*)とも言われる大きなマーケットが広がっています。
今、この重要なインフラが、世界的な危機に瀕しています。2021年、イギリスでは物流がうまく機能せず、スーパーの棚が空っぽになるということが起こりました。そして2022年には、スペインでも同じようにスーパーの棚が空っぽになりました。
このままでは、日本でも同じような現象が起こるかもしれないことが危惧されています。
日本におけるドライバー不足
物流インフラで何が起こっているのでしょうか。まず一番深刻なのが人手不足の問題です。
あらゆる産業で人手不足問題になっていますが、物流領域は他の産業と比較して20%も労働者が不足している(※1)状況にあります。
また、働き手が不足しているにもかかわらず、トラックの積載率が40%を切っている(※2)と言われています。積み荷の60%以上は空気を運んでいるという状態になってしまっています。
なぜこれだけ人手が不足しているのかというと、ドライバーの労働環境に問題があるからです。
まず一つは、労働時間がとても長いという点です。全産業と比較して、平均よりも2割長い(※3)という統計が出ています。その理由として、ドライバーの待機時間があげられます。
物流センターに納品に行くと、たくさんの車列が並びます。センターに到着してから荷下ろしできるまでに、平均すると1時間半の待機が発生している(※4)と言われています。場合によっては、4、5時間待つこともあります。
このまま人手不足が続けば、2030年には日本全国で約35%の荷物が運べなくなる(※5)と言われています。イギリスやスペインで起こったことが、まさに日本でも起こってしまうのです。
ドライバー不足に追い打ちをかける「物流の2024年問題」
この労働力不足に追い打ちをかけるように、「物流の2024年問題」が、来年に迫っています。
これまでは、残業によってドライバー不足を何とかカバーしてきましたが、2024年4月に働き方改革関連法案が施行されることで、時間外労働が規制されます。
2023年2月にHacobuで実施したアンケートでは、実に企業の9割以上が、物流の2024年問題を非常に重要な問題と捉えているという結果が出ました。しかし、何とかしなければいけないと意識しているものの、4社に1社はまだ対策を行っていないことも明らかになりました。
このような状況に対して、国土交通省や経済産業省が中心となって法改正を行い、物流の効率化を荷主に義務付けるということが、最近のニュースで話題となっています。国も本腰を上げて、この物流というインフラを何とかして守ろうと動いている現状があります。
何十年と続く物流の非効率
物流領域において、このような課題が顕在化したのは最近のことではありません。何十年も前から、物流インフラは非常に非効率だと言われてきました。それにもかかわらず、なぜ解決されないのでしょうか。
企業間物流には、様々なステークホルダーが存在します。原材料メーカーから完成品メーカーの工場へ、そこからメーカーの倉庫に荷物が届き、さらに卸事業者、流通事業者の物流センターに荷物が運ばれます。そして最終的には小売事業者の店舗へと荷物が運ばれていきます。このような物流業務を3PL事業者が担いますが、実際に荷物を運ぶのは運送会社です。
様々なステークホルダーが介在しながら、最終的に消費者がスーパーで手に取れるところまで荷物がたどり着きます。この間に行われるステークホルダー同士の情報のやり取りが、基本的にはアナログなコミュニケーションで行われているという現状があります。紙やFAX、電話でのコミュニケーションが中心となっているのです。
物流に関する情報がアナログであるが故に、各社内に留まってしまい、データが繋がりません。それぞれの工場や倉庫、物流センターでは最適化されるものの、全体が繋がった形で最適化されないことが、最も重要な課題と言えます。
これが原因となって、様々な非効率が生じ、ドライバーの労働時間が長くなり、ドライバーが不足し、さらには積載率が低下するなどの問題にも発展していると考えられます。
Hacobu創業のきっかけ
物流の非効率という大きな課題を解決するために、各ステークホルダーの持つ物流情報を繋ぐためのプラットフォームを構築することが必要であると考えました。
そのきっかけとなったのは、Hacobuを起業する前に、大手乳業メーカーのコンサルティングプロジェクトに参画する機会があり、企業間物流の現場で、物流のアナログかつ非効率な現場を目の当たりにしたことです。
“運ぶ”ことがビジネスのボトルネックになっていると痛感した私は、Hacobuを創業し、物流に特化した事業をスタートしました。社会の骨格となり得るデジタル物流インフラを作ることが、“私たちがやるべき事業”であり、そこに大義があると考えています。
Hacobuが開発・提供するSaaS型の物流管理ソリューション「MOVO(ムーボ)」は、複雑な物流現場の課題を解決する複数のアプリケーションで、日本を代表するメーカー、卸、小売、物流事業者等を含む約1万の事業所でご利用(*1)いただいています。
中でも、トラック予約受付サービスでシェアNo.1(*)の「MOVO Berth」は、累計利用ドライバー数(*2)は46万人を突破しました。これは、国内ドライバー数の約半数に相当(*3)し、ネットワークが広がってきていると実感しています。
なぜ我々のようなスタートアップが、このプラットフォームを広げることができているかというと、我々の企業努力に加えて、様々な企業の皆様にバックアップをしていただいていることが非常に大きいと考えています。資金面でも、ビジネスの観点からもバックアップをしていただいているからこそ、我々のようなスタートアップが、この壮大な物流領域においてプラットフォームを広げるという事業に挑むことができています。
業界のイノベーターでありたい
創業8周年を迎える今年、これらの社会課題解決に向けた革新への覚悟をより強固に宣言し、自らも非連続な成長を目指すとともに、業界の変革へも踏み込んでいく意志を表明するために、CI(コーポレート・アイデンティティー)を刷新しました。
きっかけは、社名であるHacobuと、プロダクトであるMOVOを統合しようかという話からでした。その話し合いの過程で、やはり統合はせず、Hacobuは一つのブランドでその中にMOVOというプロダクトがあると定義しました。また、2035年さらに2045年といった先を考えたときに我々はどうありたいのかというところを考えました。
そのときに「運ぶを最適化する」ために必要な、あらゆる事業を手がけていたいという思いがありました。その器としてHacobuがあって、MOVOはSaaS事業、そしてプラットフォームのブランドとして定義づけました。
そして、Hacobuというブランドをどうしたいのか。Hacobuという名前を言ったり見たりした時に、どういうことを想起して欲しいのかを突き詰めていくと、「物流インフラをアップデートする革新者(イノベーター)」だと思っていただけるブランドを作っていきたいという思いが明確になりました。
Hacobuの新しいロゴには、矢印のモチーフを使い、アップデートをイメージできるような意味を込めました。
もう一つはMOVOというプロダクトのブランドについてです。MOVOと聞いてどういうふうに思ってほしいのかを考えた時に、物流現場の救世主であって、ヒーローでありたいという思いがありました。物流現場の苦痛を解消してくれそうな、力強いブランドになりたい。これまでのMOVOは、どちらかというと、親しみやすい、かわいらしいそういう雰囲気をまとっていましたが、情熱的で、そのパワフルなプロダクトへと進化していきたいと考えています。そんな思いを込めて、力強い赤色を採用し、矢印が上を向いた翼が開くようなモチーフにしました。
なぜ今、ブランドを刷新したのか

「物流の2024年問題」が目の前に迫っています。しかし、その対策はまだまだ十分とは言えません。私たちHacobuは、創業以来、イノベーションを起こそうと思って取り組んできたものの、それに沿ったブランディングをしてこなかったと感じていました。
物流インフラをアップデートするイノベーターとして、変わりたい。そんな思いから、リブランディングに取り組みました。ブランドを考えることは、単なるデザインだけの話ではなくて、会社の経営を考えることだと思っています。
運ぶを最適化するために、他にもやれることはたくさんあります。インフラをアップデートするために必要なことは、全部やっていきたい。そんな思いを新しいブランドに込めました。
物流ビッグデータを活用して社会課題の解決に挑む
「MOVO」の導入企業の広がりとともに物流ビッグデータの蓄積が進んでいます。私たちは、この個社の枠を越えた物流ビッグデータを分析・活用し、物流領域に還元することでサプライチェーン全体の最適化を図っていきたいと考えています。
データに基づいた議論が行われる事によって、業界や会社の枠を超えた物流の協調が大きく進むことはもちろん、データが存在することで、事実を共有し、事実を見つめなおし、建設的な解決策を考え、新しいロジスティクスの在り方を考えることが可能になります。
プラットフォームによって、物流に関するデータを集めることができれば、物流領域全体で最適化に取り組めるようになります。このような世界を「Data-Driven Logistics®(データドリブン・ロジスティクス)」と定義し、Hacobuはその実現を目指しています。
今回、リブランディングを経て、我々の存在意義について再確認できたことで、存在意義が拡大したような気がしています。運ぶを最適化するというミッションは根幹に置きつつも、イノベーターとしてSaaSの開発・提供や、物流DXのコンサルティング事業にとどまらず、新しい取り組みにも挑戦していきたいですね。
私たちが取り組んでいるビッグデータの活用によって、新たな課題解決や、物流領域以外でも革新を起こすことができるのではないかと考えています。
現状が当たり前だと思わず、当たり前を疑って、最適な形は何なのかと、常に考えて動ける、そういう組織でありたいです。そのためにも、刷新したブランドビジョンを組織に浸透し続けていきたいですね。
そして、「Data-Driven Logistics®(データドリブン・ロジスティクス)」を、あらゆる人に浸透していきたい。前に進んでいくためには、慣習も打破もしていかなければなりません。
我々はイノベーターとして、データの力で挑戦し続けたいと考えています。
\Hacobuについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください/
(※1)出典:経済産業省・国土交通省・農林水産省「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」(2022),8頁
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001514680.pdf
(※2)出典:経済産業省・国土交通省・農林水産省「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」(2022),12頁
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001514680.pdf
(※3)出典:経済産業省・国土交通省・農林水産省「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」(2022),8頁
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001514680.pdf
輸送とは?定義や役割、種類、業界別の特徴、課題などを解説
輸送は現代…
2025.10.06
(※5)出典:野村総合研究所「トラックドライバー不足の地域別将来推計と地域でまとめる輸配送」(2023)
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2023/cc/mediaforum/forum351
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主