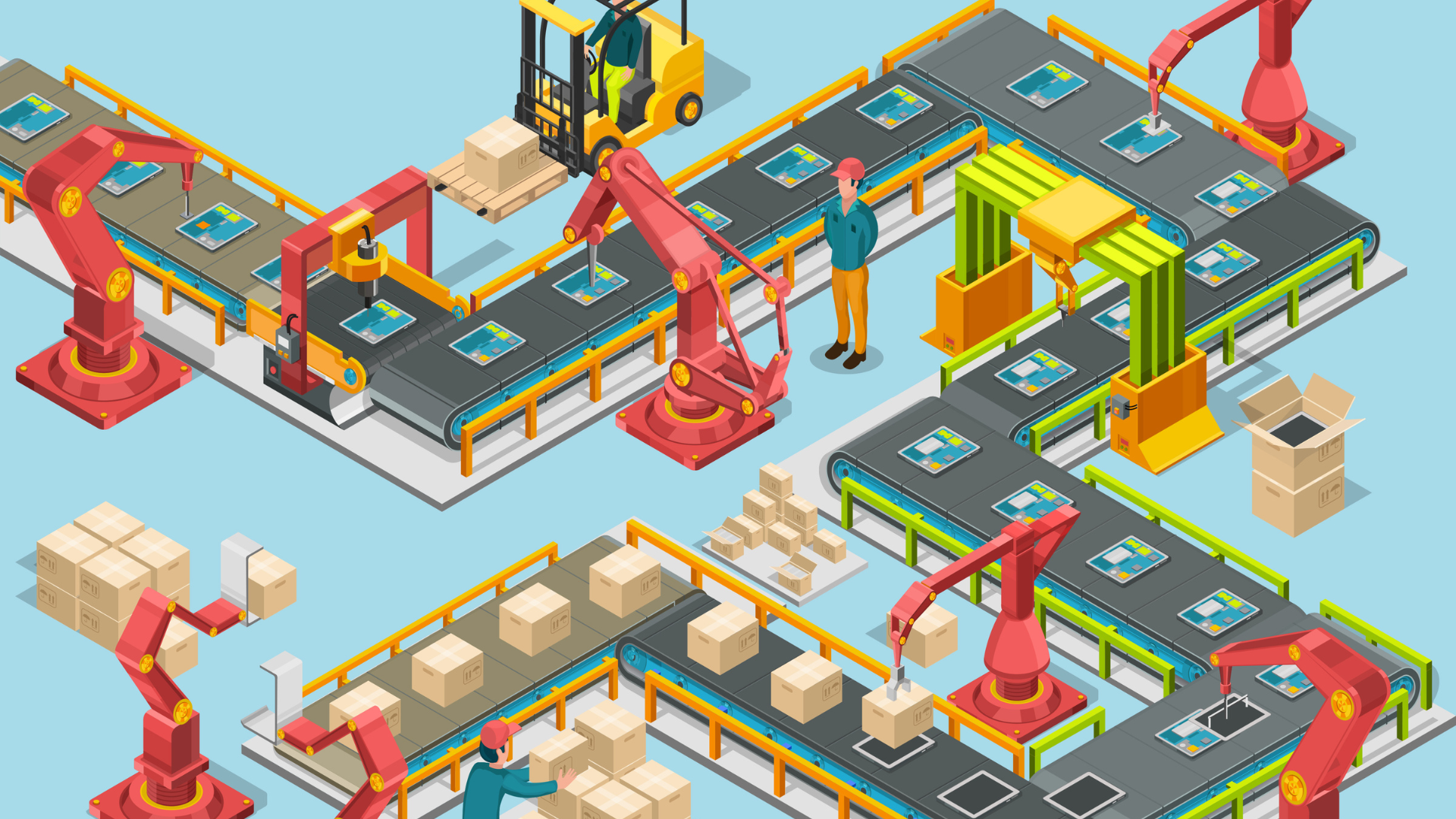ムダをなくす!倉庫のロケーション管理|基本から効率化の方法まで紹介

「商品がどこにあるか分からず、探すのに時間がかかっている」
「ピッキングミスや誤出荷が減らない」
物流倉庫の管理者には、こうした課題をお持ちの方も多いのではないでしょうか。また、本社の物流部門の方は、委託先や自社拠点の現場から同様の悩みを耳にすることも少なくないはずです。
置き場所が曖昧な「ムダ」は、倉庫全体の生産性を低下させ、見えないコストとして事業を圧迫します。この根本的な課題解決の鍵が、商品の「住所」を定める「ロケーション管理」です。
本記事では、ロケーション管理の基本・メリット、主要な3つの管理方法、そして精度と効率を上げる具体的な改善方法まで、物流現場を18年以上経験した筆者が網羅的に解説します。貴社の倉庫のムダをなくし、コスト削減と生産性向上を実現するためにお役立てください。
なお、倉庫のロケーション管理にお悩みなら、物流DXコンサルティングのHacobu Strategyがご支援できます。Hacobu Strategyの概要は以下ページをご覧ください。
目次
倉庫内ロケーション管理の基本と目的
まずは、ロケーション管理の基本と目的を、以下の流れで解説します。
- 【前提】ロケーションは商品の「住所」
- 【目的】入庫作業の効率化と在庫管理の精度向上
- 【基本】ロケーション(番号)の基本的な付け方
【前提】ロケーションは商品の「住所」
保管スペースの「住所」にあたる固有の番号を「ロケーション」と呼びます。私たちが「〇〇県〇〇市△△町1-2-3」という住所で郵便物を受け取るのと同様に、倉庫内でも「Aエリア-4番通路-3番棚-2段目」といったロケーション(住所)をすべての保管場所に割り振ることです。
そして、そのロケーション(住所)と、そこに保管されている商品を紐づけて管理・運用する仕組み全体を「ロケーション管理」と呼びます。
【目的】入庫作業の効率化と在庫管理の精度向上
ロケーション管理の主な目的は「作業の効率化」と「在庫管理の精度向上」です。ロケーション管理でルールが明確になれば、作業員は迷わず最短距離で動け、入出庫効率が向上します。
筆者がいた倉庫では、数十種類の泡盛を「ラックが空いていれば収納する」というルールのみで管理し、属人化していました。担当者不在時はピッキングや在庫確認ができず、作業効率が非常に悪かったのです。まさに、ロケーション管理による効率化が不可欠な例だと言えるでしょう。
また、全商品の住所がデータ管理されると在庫精度が飛躍的に向上し、「データ上(帳簿上)はあるが、モノが見つからない」といった機会損失や過剰在庫のリスクを減らせます。
【基本】ロケーション(番号)の基本的な付け方
番号付けの基本は「誰でも同じ場所を特定できる」ルール作りです。一般的には「エリア、通路-棚の番号(連)-棚の段数(段)-間口」などで決めましょう。
【ロケーション番号の例】A04-03-02
これは「Aエリア4番目の通路」の「入り口から3番目の棚(連)」の「下から2段目(段)」といった意味です。必要に応じて「A04-03-02-05(左から5番目のマス目)」のように枝番を加えます。重要なのは、倉庫レイアウトに合わせ、シンプルで変更しないルールを定め、徹底することです。
ここまでの解説で「ロケーション管理でどんな効果が得られる?」と気になった方も多いのではないでしょうか。次の章では、ロケーション管理を徹底することで得られるメリットについて解説します。
倉庫のロケーション管理で得られる3つのメリット
ロケーション管理で得られる主なメリットは、以下の3点です。
- どこ?をなくし、入出庫作業を「効率化」できる
- 脱属人化!入出庫作業を「標準化」できる
- 新人でもわかりやすく、教育コストを削減できる
どこ?をなくし、入出庫作業を「効率化」できる
最大のメリットは、ピッキング(商品を取り出す作業)や入庫(商品を棚に入れる作業)の効率が劇的に向上することです。管理が不十分だと、作業員が曖昧な記憶で商品を探し回る「探す時間」がムダになってしまいます。
ロケーション管理導入後は、作業指示書やハンディターミナルに表示された「A04-03-02」といった番号通りに最短距離で作業できます。「探すムダ」がゼロになるだけで作業時間が短縮され、より多くの出荷に対応可能です。
脱属人化!入出庫作業を「標準化」できる
ロケーション管理は、特定の作業員しか場所を知らない「属人化」を解消します。「この場所はAさんしか分からない」という状況では、Aさん不在時に作業が止まってしまい非効率です。
商品の「住所」がルール化・データ化されれば、作業員の経験や勘に頼る必要がなくなります。誰でも同じ情報で作業できるため、業務全体の「標準化」が実現します。
新人でもわかりやすく、教育コストを削減できる
ロケーション管理が徹底されることで、新人やパートへの教育コストも大幅に削減できます。
悪い例として、筆者がいた泡盛を保管する倉庫では、ロケーション管理がされていなかったため、商品を暗記する必要があり、新人とベテランの生産性に大きな差がありました。
全商品の場所を暗記するのは非現実的です。しかし、ロケーション管理を導入すれば、新人が覚えるのは「商品の顔」ではなく、「ロケーション番号の読み方・ルール」だけで済みます。結果、指導役の負担も減り、倉庫全体の生産性向上にもつながります。
なお、出荷業務を効率化する方法について、以下の記事で詳しく解説しています。
【倉庫管理者必見】出荷業務の効率化マニュアル|改善の手順や方法、成功事例を紹介
「出荷業務…
2025.12.18
ここで解説したように、ロケーション管理を徹底することは大きなメリットがあります。ただ、これだけでは「ロケーション管理の方法にはどんなものがあるの?」という疑問が生まれるのではないでしょうか。次の章ではロケーション管理の種類や特徴について詳しく解説します。

倉庫内ロケーション管理の主な3つの種類と特徴
ロケーション管理には種類があり、自社の倉庫や扱う商品の特性に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。主な管理方法は、以下の3種類です。
- 固定ロケーション|覚えやすいがスペース利用が非効率
- フリーロケーション|スペースを効率的に使えるが在庫管理が複雑
- ダブルトランザクション|エリアごとで固定とフリーを使い分け
固定ロケーション|覚えやすいがスペース利用が非効率
商品ごとに保管場所を固定する方法です。「商品Aは、必ずA04-03-02の棚に保管する」というように、専用の「指定席」を決めるイメージです。
| 項目 | 詳細 |
| メリット | ・作業員が商品の場所を覚えやすい。 ・システムがなくても運用しやすい。 ・在庫の増減を感覚的に把握しやすい。 |
| デメリット | ・保管効率が悪い(指定席が空いたままになる)。 ・商品の種類(SKU)が増えると、スペースを圧迫する。 |
| おすすめシーン | ・取扱SKUが少なく、商品ごとの在庫量が多い場合。 ・定番品を長期間取り扱う場合。 |
フリーロケーション|スペースを効率的に使えるが在庫管理が複雑
保管場所を定めず、空いている棚に入荷した商品から順に保管する方法。「自由席」のイメージで、どの商品がどのロケーションにあるかは、基本システム(WMSなど)上で紐づけて管理します。
| 項目 | 詳細 |
| メリット | ・保管効率が非常に高い(スペースをムダなく活用)。 ・SKUの増減や商品の入れ替えに柔軟に対応できる。 |
| デメリット | ・システム(WMSなど)無しでの把握は難しく、導入がほぼ欠かせない。 ・作業員が商品の場所を覚えることはできない。 |
| おすすめシーン | ・取扱SKUが非常に多い(多品種少量)場合。 ・商品の入れ替えが頻繁で、在庫変動が激しい場合。 |
ダブルトランザクション|エリアごとで固定とフリーを使い分け
上記2つを組み合わせたハイブリッドな方法です。 倉庫内をピッキングエリア(出荷用)とストックエリア(保管用)で物理的に分ける点に特徴があります。
- ピッキングエリア:「固定ロケーション」で管理。出荷頻度の高いバラ(個装)の商品を、決まった棚へ補充・保管。作業効率の最大化を図る。
- ストックエリア:「フリーロケーション」で管理。ケースやパレット単位の予備在庫を、空いているスペースに保管。保管効率の最大化を図る。
| 項目 | 詳細 |
| メリット | ・作業効率と保管効率の両立が可能。 ・出荷頻度が高い倉庫でもスムーズな対応が可能 。 |
| デメリット | ・「ストックエリアからピッキングエリアへの補充」作業が発生する。 ・管理方法が2種になり、運用ルールが複雑になる。 |
| おすすめシーン | ・EC・通販など、多SKUでバラ単位のピッキングが頻繁に発生する場合。 ・WMSなどを導入しており、システム管理ができる倉庫。 |
上記から自社に合った管理方法を選ぶわけですが、「自社に本当に合う管理方法がどれなのかわからない」「導入して失敗したくない」と感じる方もいらっしゃると思います。そんな方には「Hacobu Strategy」がおすすめです。物流DXのプロフェッショナル集団が貴社の課題解決をサポートいたします。Hacobu Strategyの概要は以下ページをご覧ください。
次の章では「ロケーション管理を活用してムダをなくすための具体的な方法は?」という本質的な課題の解決方法を解説していきます。

ロケーション管理の精度と効率を上げるための具体的な方法
次は、実践的な改善ステップに進みます。倉庫のムダをなくし効率を上げるための方法として、以下の5つを解説します。
- 倉庫のレイアウトと作業動線を最適化する
- 商品の出荷頻度を分析し、最適な保管場所を決める
- 誰でもわかる明確なルール作りと情報共有を徹底する
- WMSを導入し、在庫管理の精度を上げる
- さらにWMSやWCSとトラック予約受付システムを連携する
倉庫のレイアウトと作業動線を最適化する
ルール決定前に「倉庫レイアウト」を最適化しましょう。作業動線にムダが多いと、いくらルールを整備しても非効率になってしまいます。
理想は、入荷から出荷まで、モノの流れが「U字型」や「I字型(一方通行)」になるようレイアウトを見直すことです。これは、モノの流れをできるだけ一方通行にし、作業が入り混じることや逆流(ムダな行き来)を防ぐための代表的なレイアウトです。
| レイアウト | 詳細 |
|---|---|
| I字型 | 最もシンプルな動線です。倉庫の「片方の端から入荷」し、保管エリアを通り、「反対側の端から出荷」する流れを指します。モノの行き来が一方通行になるため、作業者同士の衝突やムダな移動がなくなります。 |
| U字型 | 入荷場所と出荷場所が「同じ側」にある場合に有効なレイアウトです。入荷口から入ったモノが倉庫の奥に進み、Uターンするように保管エリアを回って、入荷口の隣にある出荷口から出ていく流れを指します。 |
あわせて、通路幅が狭すぎてすれ違えない、といった物理的なボトルネック解消も有効です。
倉庫のレイアウト最適化の方法についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事を参考にしてみてください。
物流センターの業務改善とレイアウトのポイント
企業の経営…
2025.06.02
商品の出荷頻度を分析し、最適な保管場所を決める
次に「どの商品を、どこに置くか」を戦略的に決めます。この際に役立つのがABC分析です。
ABC分析とは、全商品を「出荷頻度」の高い順に並べ、A(最重要)、B(中程度)、C(低頻度)の3グループにランク分けする管理手法を指します。
- Aグループ(高頻度):出荷口に最も近い、ピッキングしやすい「一等地」に保管します。
- Bグループ(中頻度):Aグループの次にアクセスしやすい場所に保管します。
- Cグループ(低頻度):出荷口から最も遠い場所や、棚の上段などに保管します。
この配置だけで、作業の大部分を占めるAグループ商品のピッキング移動距離が劇的に短縮され、倉庫全体の生産性が向上します。
誰でもわかる明確なルール作りと情報共有を徹底する
先に解説したロケーション番号(A04-03-02など)の付け方を、誰でも直感的に理解できるようシンプルに定め、それを「見える化」して徹底することが重要です。
ルールを決めたらマニュアルにまとめるだけでなく、各通路や棚に大きくロケーション番号を貼りだしましょう。物理的に「見える」状態にすることで、作業員が番号のルールを暗記する必要がなくなり、誤出荷などミスが減り、新人でもすぐに作業に加わることができます。
WMSを導入し、在庫管理の精度を上げる
ここまでの3つは「現場の工夫」ですが、フリーロケーションの採用や、より高レベルな在庫精度の向上を目指す場合、Excelや紙の管理台帳では限界があります。そこで不可欠となるのが、WMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)の導入です。
WMSとは、倉庫内の「モノ」と「場所(ロケーション)」と「状態」をリアルタイムに一元管理する専門のシステムです。ハンディターミナル(バーコード等を読み取る端末)と連携し、入庫・出庫・ピッキング・棚卸といった作業をデジタル化します。
これにより、Excelや手書きの紙での管理で起こりがちな「入力漏れ」「更新の遅れ」などのヒューマンエラーがなくなり、在庫データの精度が大幅に向上します。
WMSについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
WMSとは?基本機能や導入メリット、導入事例をわかりやすく解説
WMSとは倉庫…
2025.12.08
さらにWMSやWCSとトラック予約受付システムを連携する
WMSを導入し、さらにトラック予約システムと連携することで入出荷業務を大きく効率化できます。
トラック予約システムとは?
入出荷のために来場するトラックの受付業務や入場時間などを管理するシステムです。物流センター・工場における車両待機の改善や生産性向上を支援します。
なぜ入出荷作業を効率化できる?
トラック予約受付システムの導入で、トラックの入場時間だけでなく、入荷および出荷する商品の情報も事前に把握できるからです。それにより、前もって商品の出荷準備や保管場所の確保を可能にするため、生産性の向上や残業時間の削減を実現します。
成功事例は?
MOVO Berthと庫内制御システム(WCS)を連携させて入出荷作業を効率化した事例をご紹介します。
花王株式会社 豊橋工場では、トラック予約受付システムのMOVO Berthと庫内制御システム(WCS)を連携させることで、次に出庫すべき貨物を自動的に判断・実行させることを実現しています。
連携の仕組みと効果:
WCSがリアルタイムにMOVO Berth上の到着状況や予約バース情報を把握し、次に出庫すべき貨物を自動的に判断・実行します。荷揃えを開始すると同時に、MOVO Berthからドライバーのスマートフォンに着車するようSMSを送信します。
これにより、車両が指定バースに着車した際には既に貨物を積み込むことが可能な状態となり、トラック滞在時間を1時間から20分に削減することに成功しました。
こちらの成功事例をさらに詳しく知りたい方は、以下のリンクから花王株式会社のインタビュー記事をチェックしてください。
インタビュー記事「完全自動化倉庫×バース予約システムで実現するホワイト物流 〜API連携で実現する、トラックの場内時間の最小化〜」をチェックする
まとめ:ロケーション管理を最適化し倉庫作業を効率化しよう
本記事では、倉庫作業のムダをなくすための「ロケーション管理」について、その基本から具体的な効率化の方法までを詳しく解説しました。自社に最適なロケーション管理の方法を選び、運用ルールを整備・徹底することが、倉庫業務全体の効率化とコスト削減を実現する鍵となります。そのロケーション管理の効果を最大化するための方法は以下の5つです。
- 倉庫のレイアウトと作業動線を最適化する
- 商品の出荷頻度を分析し、最適な保管場所を決める
- 誰でもわかる明確なルール作りと情報共有を徹底する
- WMSを導入し、在庫管理の精度を上げる
- さらにWMSやWCSとトラック予約受付システムを連携する
倉庫のロケーション管理にお悩みなら、物流DXコンサルティングのHacobu Strategyがご支援できます。Hacobu Strategyの概要は以下ページをご覧ください。
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主