キリンビバレッジ 井上社長の挑戦 データ活用と共同配送で効率的な輸配送を ~競合他社・異業種とタッグを組み、挑む物流改革~

将来人口推計が、非情な未来を突き付ける。2023年推計では、2030年の総人口は最悪、1億1819万人。2020年の総人口に比べ、約800万人の減少だ。最新値によれば、東北6県がすっぽり抜け落ちるほどの幅を見せる。
危機感を募らせるのは、清涼飲料メーカーのキリンビバレッジで代表取締役社長を務める井上一弘氏だ。「将来人口推計は大きく外れません。人口が加速度的に減るのは、間違いない。どうしようもない世界が、確実に訪れます」。
危惧するのは、国内市場の縮小だけではない。「今後、財政上などさまざまな制約から、居住エリアと非居住エリアが鮮明に分かれていく。つまり、製品を届けられる場所とそうでない場所が出てくる。安穏としてはいられません」(井上氏)。
届けるべき場所に製品を効率的に輸配送するにはどうすればいいか――。将来課題には、いまから取り組む必要がある、と井上氏は意欲的だ。将来課題を真正面から捉え、それをチャンスに変えようとする、攻めの発想に立つ。
過去の反省の上にも立つ。2018年夏、列島全体は猛暑に見舞われ、西日本を中心に豪雨の被害を受けた。清涼飲料への需要が押し上げられる一方、受託製造企業の一部は出荷調整を迫られる。物流現場には、混乱が生じた。
「どんな状況下でも製品を消費者に届けられるように、メーカーとしてサプライチェーンを整えておく必要があります」。将来のリスクまで見極め、その回避・低減に向けた準備を怠らないことの重要性を、井上氏は改めて説く。
足元では、原材料やエネルギーの価格がジリジリと上がる。2024年度は、2688億円の売上収益、183億円の事業利益を上げたが、先行きは楽観できない。「コストアップ要因が控えています。物流コストも、その一つ。リスクの回避・低減に向けた準備は、『喫緊の課題』を超えるほどの経営アジェンダです」(井上氏)。
準備はいま、着々と進む。追い求めてきたのは、主に輸配送の効率化だ。非競争領域での協業が、その推進を後押しする。具体の取り組みを追う。

いのうえ・かずひろ 1966年生まれ、埼玉県出身。青山学院大学経済学部卒業後、1988年キリンビール入社。営業部門で経験を積み、2007年キリンヤクルトネクストステージ営業部長、2009年キリン・ディアジオ執行役員、2013年キリンビールマーケティング部企画担当主幹、2015年同部の部部長を歴任。2016年執行役員広域流通統括本部長、2021年常務執行役員流通営業本部長として全国統括。2024年より現職。
サプライチェーン上に潜む「ムリ・ムダ・ムラ」。効率化を追求する背景には、その存在がある。ターゲットは、いくつか上がる。
一つは、需要変動の増幅である。小売業者での需要増は、卸売業者を経由しメーカーに伝わる過程で、膨れ上がる傾向にある。商機の損失につながる欠品を可能な限り防ぎたいという考えからだ。とりわけ清涼飲料は、その傾向が強い。季節や天候による需要の変動が大きいため、流通事業者は欠品リスクを避けようと、多め多めに発注する。
これでは余剰在庫が膨らむばかり。「経営上の理想は、最小の数量を最小の回数で納品し、在庫を最小限に抑えることです」と井上氏は正論を説く。その理想を貫くには、サプライチェーンを構成する流通事業者との協業が不可欠だ。
それを可能にしたのが、Hacobuが提供する生産・販売・在庫管理の情報プラットフォーム「MOVO PSI」である。メーカー、卸、小売りの情報を基に独自の計算モデルで輸送量の平準化や在庫量の最適化を実現する。
この情報プラットフォームをいよいよ5月から、キリンビバレッジ側で在庫管理を受け持つVMI拠点を対象に実装する。
事の始まりは、「持続可能な物流インフラを創る」をビジョンに掲げるHacobuとともに2021年度から取り組んできた「輸送量平準化 共同プロジェクト」だ。「従来は、販売動向に合わせて製品の供給計画を立てるとき、もっぱら肌感覚に基づいていました。今後はそれを、データやロジックに改めていく必要がある。そこでHacobuと手を組み、プロジェクトに乗り出すことを決めたのです」(井上氏)。
競合もプロジェクト参画 実証実験では同様の結果
2023年10月から11月までの間は、キリンビバレッジ側で在庫管理を受け持つ2つの物流拠点を対象に「MOVO PSI」β版を用いて効果を実証。結果、輸送コストは約9.1%の削減、在庫日数は約13.2%の削減につながった。実際のオペレーションを適用しても同程度の効果が得られることも、そこで確認済みだ。
共同プロジェクトには、2023年度から競合メーカーであるアサヒ飲料社も参画。2024年3月から4月までの間、同様の実証実験を実施したところ、輸送コストは約6.2%の削減、在庫日数は約6.5%の削減、という結果を得た。

これらの実証実験の結果が、「MOVO PSI」のVMI拠点への展開の決め手になった。「実際に運用してみないと、どの程度の効果が上がるのか、まだ明確には見通せません。実証実験と同程度の効果は期待しています」と井上氏は力を込める。
もう一つのターゲットは、輸送時の空車である。生産拠点から物流拠点まで製品を届けると、戻り便は自ずと空になる。荷を積まず空車のままでは、輸送効率として最悪なばかりか、温室効果ガス(GHG)のムダな排出につながる。
また物流業界では、労働環境の過酷さを背景にトラックドライバーの不足が懸念される中、物流を停滞させずに済む持続的・安定的な体制の構築が求められている。その観点からも、ドライバーにムダを強いるのは避けたい。
そこで取り組み始めたのが、輸配送における協業である。この2月からは、業界を超えた協業にも乗り出す。タッグを組むのは、2024年8月に特定保健用食品のロングセラーブランド「ヘルシア」を譲受した相手先の花王社である。
ともに川崎市内に物流拠点を持つ一方、キリンビバレッジは長野県松本市内に生産拠点を、花王社は同県千曲市内に物流拠点を置く。互いの片道輸送を川崎市内と長野県内でつなげれば、輸送経路をぐるっと一筆書きで描ける。
そこで、花王社の製品を川崎市内の物流拠点から千曲市内の物流拠点まで届けた戻り便を、キリンビバレッジの製品を松本市内の生産拠点から川崎市内の物流拠点まで届けるのに用いる。それによって、輸送トラック台数の年間延べ300台以上の削減と、この輸送区間でのGHG排出量の約15%削減に貢献できる計算だ。

協業のきっかけは、本社間での情報交換。互いに物流の効率化に課題意識を持つ中、川崎市内と長野県内の拠点間の距離の近さから、両社の片道輸送をつなげればトラックを互いに1便減らせるのではないか、と気付いた。
異業種である花王社との協業に踏み出せた背景には、片道輸送の区間をつなげ、戻り便を有効に活用できる、という好条件を両社の拠点が備えていた点のほか、荷主として輸送実績データを保有していたという点もある。データを活用することで、輸送トラックの削減台数やGHG排出の削減量といった協業の成果を一定程度見通せる。
機能共有し学び合う時代 協業こそが、武器になる
各発着地での時間調整や積み込み・荷下ろしの予約、伝票受領まで、さまざまな運用ルールの確認など課題は多くあったが、実証実験の結果、輸配送における協業は可能という判断から本格実施に踏み切った。「まず取り組んでみるという精神です。その結果を基に試行錯誤を重ねれば良いと考えています」(井上氏)。今後、輸送トラック台数やGHG排出量のさらなる削減を追い求める一方、協業対象区間の拡充を検討していく。
協業への眼差しは、人一倍強い。社長就任前、井上氏はキリンビールで流通営業本部長として卸売業者や小売業者とビジネスを展開してきた。「そこでは、相手にモノを売る『取引』だけでなく、機能を共有し学び合う『取り組み』が求められている、と痛感しました。協業こそが、武器になる。物流も、その一つです」。
他社を巻き込む力には自負を持つ。歴史を振り返ると、後発の強みと言える。
創業は1963年。当時麒麟麦酒が製造・販売していたキリンレモンを自動販売機で販売する会社としてスタートした。その後、1991年にキリンビールから清涼飲料事業の譲渡を受け、キリンビバレッジとして第二の創業を迎える。

「清涼飲料の市場では現在5番手です。量販店相手に競争優位を築こうにも、武器がない。競合他社に負けないように、人間関係の構築力に磨きを掛けてきました」と井上氏。それが、他社を巻き込む力として働き始めている、と分析する。
その巻き込み力を生かし、今後、流通業者との連携をさらに深める方針だ。
2024年11月、清涼飲料5社では社会課題対応研究会を立ち上げ、トラック輸送能力不足やGHG排出量削減など社会課題への対応に共同で乗り出した。ただ効率化を追い求める以上、サプライチェーン内の連携も欠かせない、とみる。
そこで頼りにするのが、卸売業者と並ぶ物流情報のプラットフォーマーであるHacobuだ。井上氏はこう期待を寄せる。「将来、メーカーから小売業者までの垂直統合を果たした業界横断の物流会社が生まれたら、Hacobuの持つデータは卸売業者の握るデータとともにデータベースとして有効に活用できるのではないでしょうか」。
キリングループが掲げるCSV経営では、社会課題への取り組みを通じて社会的価値の創造と経済的価値の創造の両立を追求する。その精神からも、持続可能な物流の構築は避けて通れない経営アジェンダだ。非競争領域での協業をどう推し進め、輸配送のさらなる効率化を実現していくのか――。そこでカギを握る「データの力」を後ろ支えする存在として、Hacobuの企業価値が、きらりと光を放つ。

取材を終えて
井上社長の「巻き込み力」と、それを支える卓越した人間関係構築力に強く感銘を受けました。AIが飛躍的に進化するいま、人間のコアコンピタンスは知能よりも“巻き込み力”かもしれません。持続可能な物流の実現には多様なステークホルダーの連携が不可欠です。その挑戦を、Hacobuはデータとテクノロジーで全力サポートしていきます。
株式会社Hacobu 代表取締役社⻑CEO 佐々⽊ 太郎
関連記事
-
 COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!
COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!更新日 2026.02.03
-
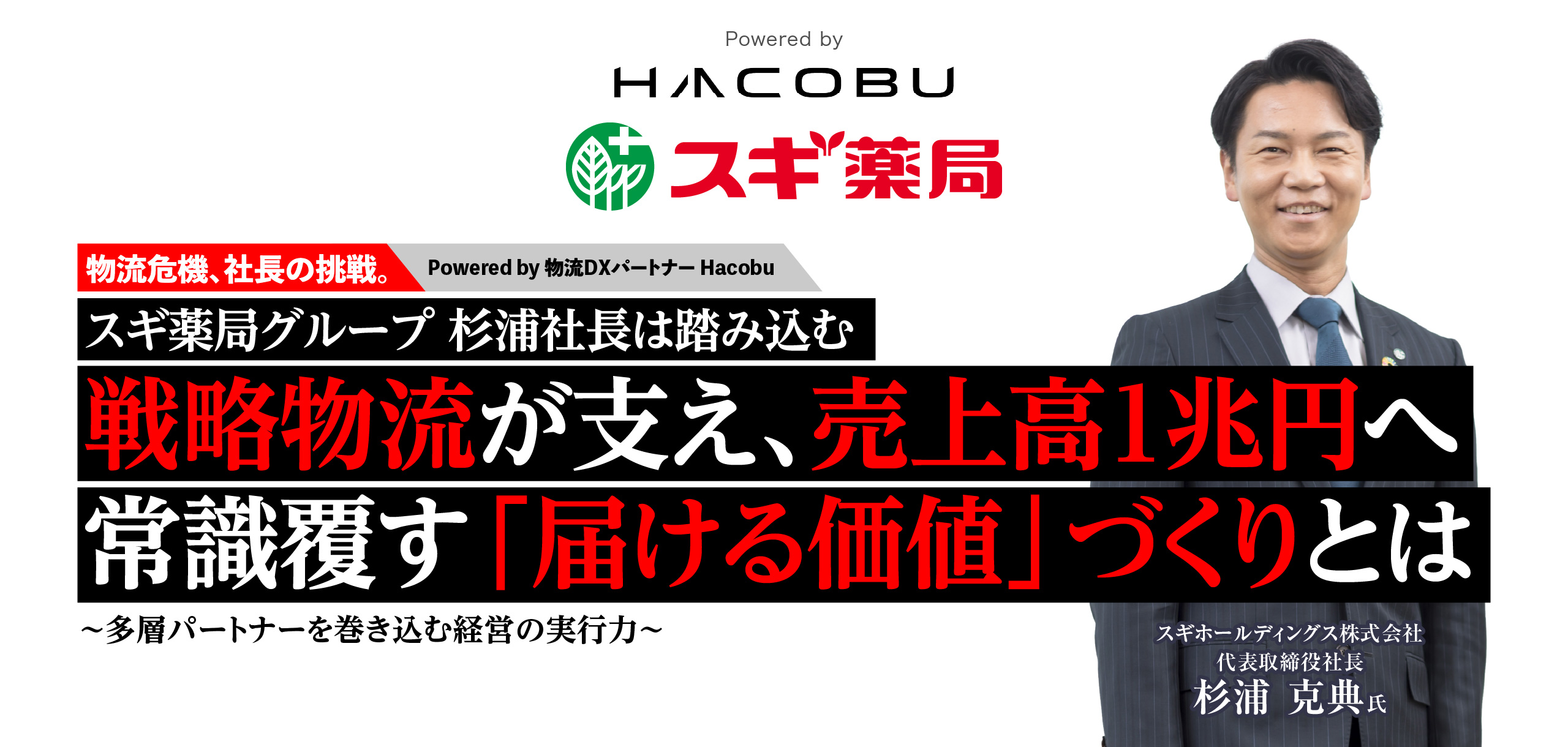 COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~
COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~更新日 2025.11.28
-
 COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?
COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?更新日 2026.01.26
-
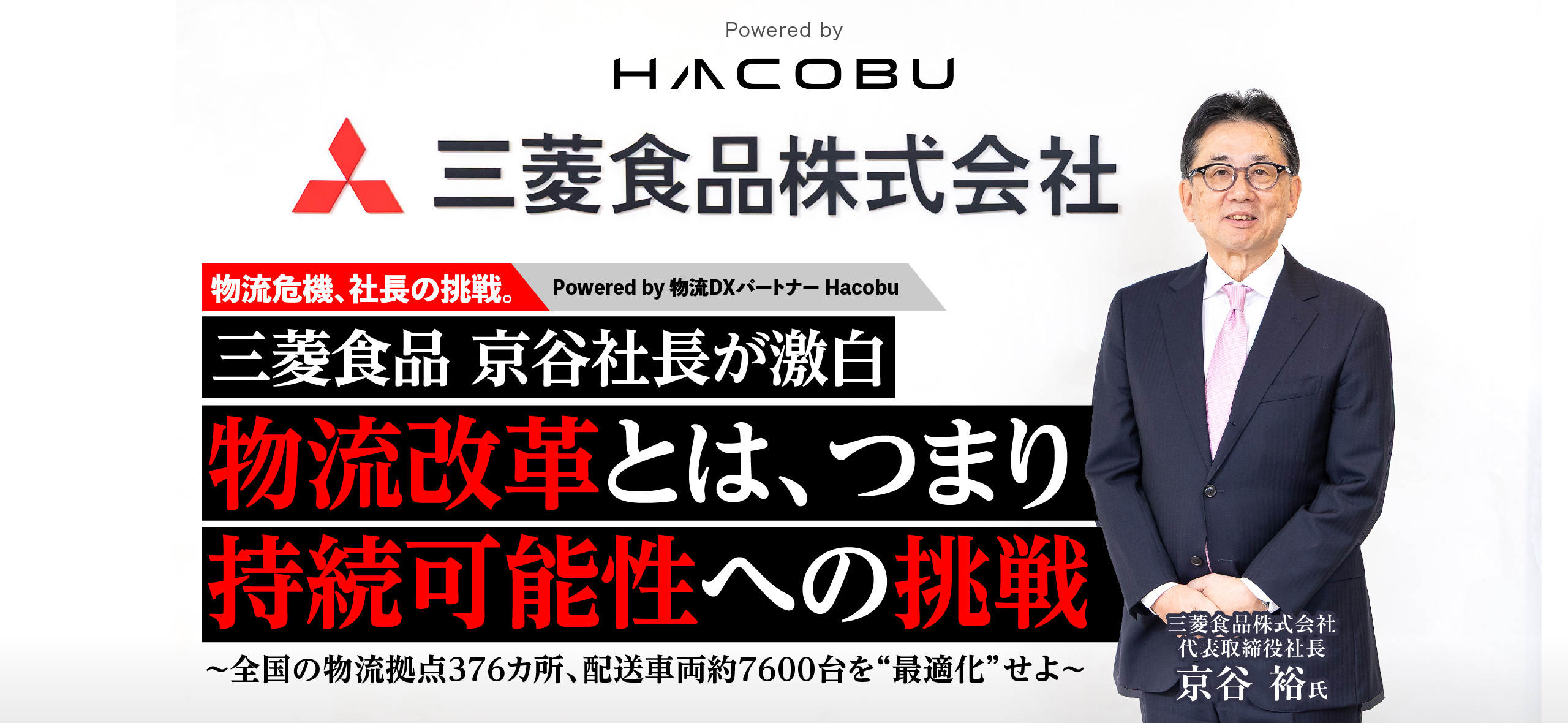 COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~
COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~更新日 2025.11.28
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主



















