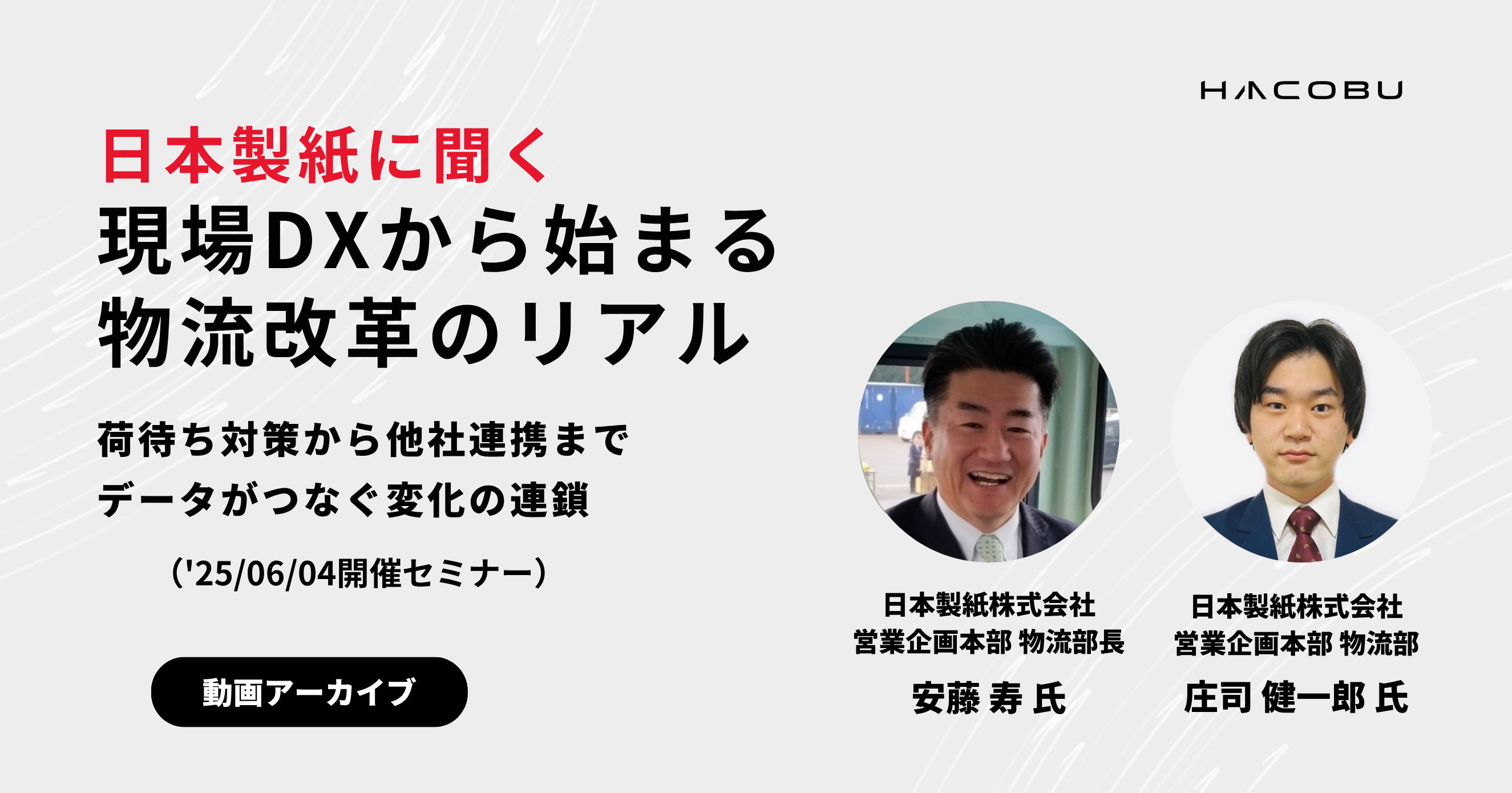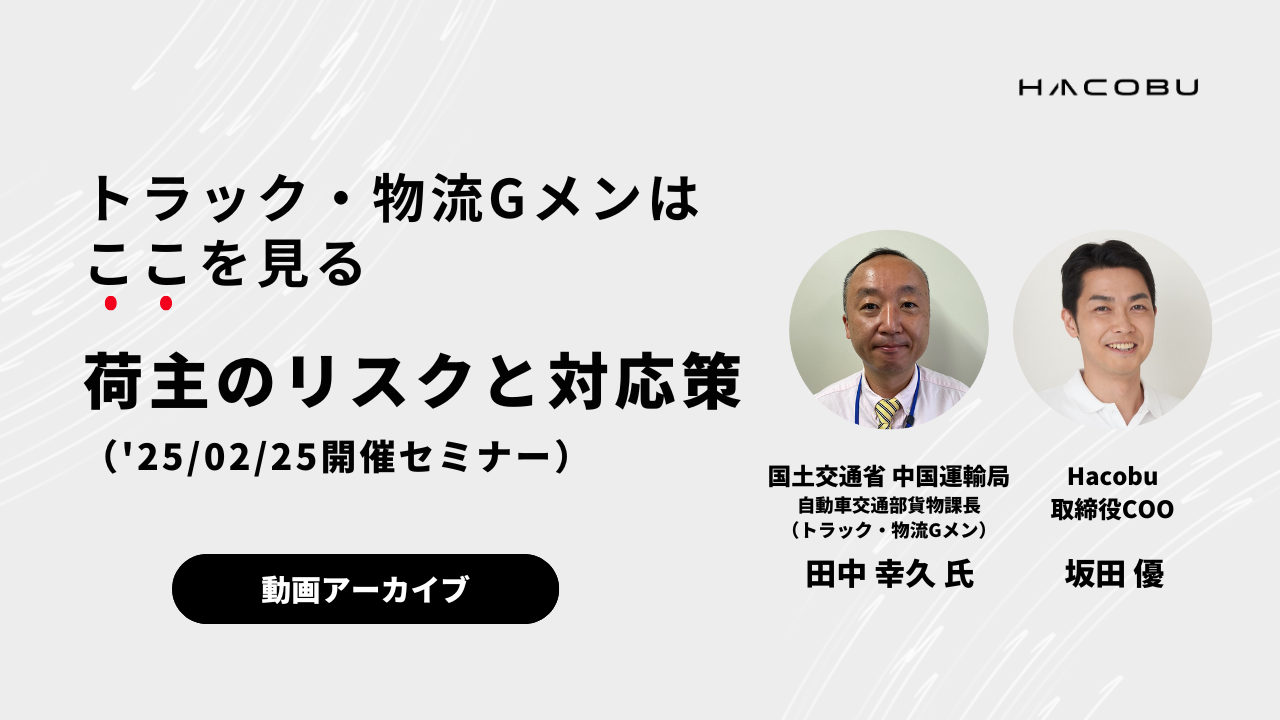【物流 DX 最前線】物流現場におけるデータ活用事例

日本の企業は、物流システムの導入が遅れており、物流情報のデータ化がなかなか進んでいませんでした。しかし、近年では「物流の2024年問題」の解決に向けて、物流システムの導入やIT活用に取り組む企業も増えており、物流の効率化やコスト削減に成功しています。
特に、EC業界においては、顧客の注文から配送までの一連の流れをシームレスに管理するため、物流システムの導入が欠かせない状況にあります。 例えば、サプライヤーの本社住所は認識できているが、「実際にどこからモノを出荷しているか」といったような物流情報を把握できている企業は少なかったといえるでしょう。しかし、デジタル化が進む近年、物流情報が集積されることによって以前は取り組むことができなかったアクションが実現できるようになってきました。
今後も、日本企業が物流システムの導入に取り組むことで、より効率的な物流を実現し、競争力を高めることが期待されます。
本記事では、株式会社Hacobuが提供する「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流管理ソリューション「MOVO」と、物流DXコンサルティングサービスの「Hacobu Strategy」の事例を紹介しています。
目次
配送ルートを可視化したことで、共同配送が実現

大手小売企業A社は、特定カテゴリーの在庫商品に関して売れ行きの波が激しい傾向にあり、サプライヤーへの日々の発注数量も大きく変動してしまうことが課題でした。 そのような状況の中、一部のサプライヤーから「物流費の高騰が続き、ドライバーも不足している。そんな中での毎日の納品作業は限界だ」という声が上がりました。
このサプライヤーからの相談をきっかけに、A社物流担当者は問題解決手段として、物流データの活用に乗り出しました。まず取り組んだのが、配送ルートの可視化です。
A社の物流センターとサプライヤーの出荷拠点を分析してみたところ、6つのサプライヤーから神奈川県にある物流センターまで、6台の車両が毎日バラバラに走行し、納品していたということがわかりました。
調べてみるとこれらのサプライヤーが同一カテゴリーであったことから、サプライヤー6社に対して、A社から共同配送による納品を働きかけました。 共同配送による納品に切り替えた結果、輸送コスト削減を実現。さらに、商品別の納品頻度を下げずに安定供給を持続することが可能となりました。
帰り便活用による積載率の向上
大手食品メーカーB社は、近年の物流費高騰の影響を受け、生産拠点を消費地の近くへと再配置することを進めていました。 しかし検討を進める中で、さまざまな制約から「一部の地域において近くに生産拠点を設置できない」ことが判明し、「一部地域においては、商品の販売そのものを停止する」ことも可能性として考えていました。
その時立ち上がったのが、B社の物流部門でした。彼らがポイントと考えたのは帰り便の積載率の向上です。
たとえ長距離を走ったとしても、配送の帰り便の積載率を上げれば、その地域のお客様へ、今まで通りの商品ラインナップを供給できるのではないか?という仮説のもと、Hacobuとの共同分析が始まりました。 分析の結果、課題地域は全部で3つありました。そのうち2つの地域では他社との共同配送協業によって積載効率を大幅に向上できる可能性があることがわかりました。さらに分析を進めると、データ化されていないものの、B社では現場の工夫によって共同配送を行っている地域があるということも判明しました。
Hacobuの物流に関する知見を生かしてデータ分析に取り組んだことで、「自社の物流に関する全体像を可視化する必要性」という新たな課題を見つけることにもつながりました。 現在B社では、各地域への商品供給を続けながら、自社物流関連の全体像を把握し、更なる効果を創出するための大規模なデジタル化を推進しています。
バックホール活用を他業種に

小売企業の物流部門内では、古くからバックホールという手法があることは知られていました。 バックホールとは、二次物流である店舗配送の車両の帰り便を、一次物流であるサプライヤーからの納品に活用するという手法です。 近年、トラックの積載効率は約40%まで低下しているといわれており、このバックホールを活用することによって、往路及び復路の積載率である「積載効率」を上げることが可能になります。 ここでの「積載効率」とは、積載率に運行の概念をプラスした考え方です。往路の積載率が80%であったとしても、復路の積載率が0%であれば、運行全体の積載効率としては40%ということになります。 積載率を向上するためには、運行全体を見渡し、積載率向上を図って行くことが重要なポイントです。
日本においては、工場の所在地が明確である一部のプライベートブランドでの活用は一部行われていたようですが、小売業者から見て出荷拠点が確認できないナショナルブランドでの活用は、ほとんど進んでいない状況にありました。
物流のデジタル化が推進されている現在、バックホールの手法がナショナルブランドにまで拡大傾向にあり、Hacobuでもそのサポートをしています。 店舗の帰り便は、かご車・パレット・オリコン等の回収便も兼ねているため、一筋縄には行かないのが現状です。しかし、回収便を一部にまとめる等、データを見ながら分析し、全体のネットワークを設計して行くことが、バックホール活用において重要なのです。
ドライバーの付加価値を30%向上〜首都圏市場向け青果物の物流効率化実証実験〜

2021年・22年度、秋田県において、「首都圏市場向け青果物の物流効率化実証実験」を支援しました。 通常、秋田県から首都圏に向けての配送は、15時間以上の長距離輸送が必要です。労働環境がよいとはいえず、ドライバー不足の問題が顕在化しつつありました。そこで、秋田県トラック協会の発案から「秋田の未来の物流を考える協議会」が始まりました。 秋田県の青果物の売価は、首都圏と比較すると2倍近くの開きがあります。そのため物流が滞ることで、秋田県の青果物生産者の収入も低減してしまうリスクが考えられます。
ドライバーの不足は、物流における問題だけでなく、青果物生産者にとっても大きな影響を及ぼします。 そこでこの問題を解決するべく、トラック協会のみならず、県庁やJAなどの多くの方が参加し、協議を進めることになりました。
行った実証実験は、具体的に以下の2点です。
• 幹線便と集荷便を分ける・・・ドライバーの労働時間削減が目的 • プロセスのデータ化・・・サステナブルな状況にするための必要事項を確認することが目的
結果、2021年の実証実験において「長距離トラックドライバーの労働時間が約15%程度改善できる」ということが確認できました。 秋田県はそれに留まらず、実証実験中に集めたデータを活用し、改善案を関係者全体で議論することも行いました。 議論の結果、以下の3点を向上できることを確認することができました。
- 長距離トラックの労働時間:25%程度
- トラックドライバーの総活動時間:22%程度
- ドライバーの生み出す付加価値(時間当たりの売上):30%程度

秋田県は2022年度も実験を実施し、「物流2024年問題」への対応策を継続して推進しています。 この事例を通して、実証実験とは、従来のようにただ実験の結果を追求するだけではないということがわかります。昨今のDXの流れを取り入れ、実験後の分析も考えてデータを集めることで、さらに一歩上の結論を出せるのではないでしょうか。
日本の未来のために物流の最適化を推進する
地理的な消費バランスの変化に合わせて、物流は柔軟にネットワークを変更していくことが求められます。また、遠隔地を管理していくための監視やコントロール機能の重要性も一段と強まると想定しています。そのために変化を敏感にとらえる目(データ)を持ち、柔軟に物流ネットワーク・ルート変更をしなければなりません。 ただ物流センターの設立や縮小を簡単にできるような資金力をもつ企業は少ないのが現実です。だからこそ、自社内だけではなく、他社の力(共同物流など)も用いて最適化を繰り返すことも重要です。日本全体としてとしてみた場合、トラックの積載率は現在、40%という低い水準にあります。結果として、日本が米国に比べ国土が狭いにも関わらず、日本の物流費比率が米国より高いという統計データもあります。
空いているキャパシティを活用し、コスト増加を抑えながら、物流を最適化することが重要と言えます。
「DX化を実現したいがどのように進めたら良いのかわからない」、「自社に最適なソリューションがわからない」といったお悩みをお持ちでしたら、Hacobuが物流DXを一気通貫でサポートします。
人手不足、高齢化、物流コストの上昇といった物流領域の課題の解決するソリューションを提供しています。
\物流DXコンサルティング〜Hacobu Strategy〜/
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主