CLO・物流リーダーの物流改革への”熱量”が交差する「第4回未来の物流共創会議」イベントリポート

2025年6月、第4回となる「未来の物流共創会議」を開催しました。
本会議は、荷主企業のChief Logistics Officer(以降、CLO)・物流リーダーが、日本の持続可能な物流の実現を目的に、企業の枠を超えた具体的かつ実効性のある取り組みを推進する場として2022年から開催しています。
今回は、CLO・物流リーダー21名が一堂に会し、物流の転換期を迎える各社がどのように物流に向き合っているのか、その課題と期待を率直に語り合うとともに、未来に向け、持続可能な物流を創造するための協調の在り方を議論する場となりました。
※掲載内容は全て「第4回未来の物流共創会議」開催時(2025年6月)現在の情報に基づいています。
目次
物流の労働生産性革命があらゆる産業の成長エンジンに

オープニングセッションでは、Hacobu代表の佐々木太郎が登壇し、創業10周年の節目にあたり、これまでの取り組みを振り返りながら「これからの物流が目指すべき姿」について語りました。
佐々木:Hacobuは一貫して「企業間物流」に特化し、分断された情報をつなぐ「物流情報のプラットフォーム」を構築してきました。マルチテナント型のクラウド基盤とID連携を通じて、現場のデータを可視化・集約し、業界全体の最適化に取り組んできた結果、現在では国内主要物流拠点の約27%(*1)がIDを保有し、ドライバーの4人に1人(*2)が毎月利用するまでに成長しています。
今後は、パッケージ型のソフトに加え、企業の個別ニーズに応える物流DXシステムインテグレーションを展開する他、ファイナンス支援、輸配送パートナーとのマッチング、物流人材の人材紹介など、「運ぶ」を革新するための新規事業を加速します。
「労働生産性革命」の時代に突入した今、物流の生産性を高めることが、あらゆる産業の成長を支える鍵になると考えます。本日は、物流の労働生産性を高めるためには何をすべきか、物流課題に前向きに取り組む皆さんと、本音のディスカッションを重ねたいと思います。
セッション1:経営層の意識改革と組織体制の模索
セッション1では、Hacobu COO坂田のファシリテートのもと、物流の生産性向上の阻害要因の中から「経営陣の物流への理解」「ITシステムの整備」の2テーマについて、各社の状況が共有され、率直な意見が交わされました。

経営層の「意識改革」──変化のきっかけ
物流に対する経営層の理解が乏しいことは、多くの企業から挙がった課題です。
小売業の現場では「販売」が最優先され、物流は店舗作業の負担軽減という“後方支援”の役割にとどまりがちであり、組織全体で物流の重要性を共有する難しさや、「CLO」という役職が浸透していない現状が語られました。
また別の企業からも、物流が「当たり前の存在」として扱われ、経営層から本質的な関心を引くのが難しいという課題が指摘されました。
各社の発表を通して再認識されたのは、「問題が起きなければ注目されにくい物流」という難しさです。問題を機に経営層の目が物流に向く現実は、皮肉でありながら、改革の大きな契機でもあります。
ある企業では、在庫があふれ、倉庫通路が商品で埋め尽くされた「衝撃的な現場の実態」により、物流キャパシティ(入荷・保管・出荷)の統合管理ができていない課題が認識され、経営にも物流への問題意識が芽生えたと言います。
また別の企業では、災害により発生した「運べない危機」を経て、物流が「当たり前の存在」から「ブランド価値の最終接点」として見直される転機となりました。
物流が中期経営計画のテーマにあがったことを機に物流改革が進めやすくなったとの意見もあり、経営層の「意識改革」は最重要テーマとして再認識されました。
組織体制の在り方──ガバナンスと評価の再設計
物流改革を進めるための組織体制にも議論が及びました。
ある企業からは、事業部制の組織ではCLOのような横断的な概念が馴染みにくいとの指摘がありました。それに対し、組織横断型のプロジェクトとして体制を組んでいる事例が共有されました。
別の企業からは、自社の組織体制を例に、構造的な改善と全体最適化のため、各部門の自立性と企業としての統率力をどう両立させるかが鍵だと強調されました。
また、グループの物流人材を戦略的資源と位置付け、その配置を一元的に担う機能を有する体制がとられている事例が紹介され、注目を集めました。
ITシステム整備──標準化か、柔軟なカスタムか
システム面においても、課題とあるべき姿について議論されました。
ある企業は、事業構造の変化にあわせてシステムを個別に調整してきたものの、「都度変えることの負担」と「標準化による効率性」の狭間で揺れていると語ります。
また、「日本では業務に合わせてシステムを組む傾向が強いが、海外ではシステムに合わせ業務を標準化するのが当たり前」といった比較と考察から、グローバル視点でのIT整備の在り方にも議論が広がりました。
同志との議論から生まれる新たな価値
セッション1では、物流課題に対し”熱量”高く取り組む参加者同士が、自社の課題や取組みをオープンに共有。単なる情報交換にとどまらず、異業種の視点を交えた活発な議論から他にはない実践的な学びが得られる場となりました。
同じ業界や取引関係にある企業であっても、物流リーダーたちの接点は限定的と言います。「自社の立ち位置の再認識できる場」「悩みを相談できる場」としての機能も果たし、ある参加者からは「仲間ができた」と語られました。
セッション2:1対1からN対Nへ──共同輸配送の拡大に向けて
セッション2では、物流の共同化をテーマに、従来の個社同士の1対1による共同配送から、より多対多(N対N)へ拡張の実現に向けた議論が行われました。
冒頭、Hacobu執行役員の佐藤から、物流の標準化に関する国際的な動向を示しました。日本としては、より早くN対Nの世界を実現することで、世界の議論をリードすべきではないかという問題意識が共有されました。
また、1対1の共同配送からN対Nを実現するために、「協業が当たり前の時代」への移行の必要性を強調しました。

共同輸配送の取り組みの実態と挑戦
まず、参加者からの「N対Nに向けた共同輸配送」の事例紹介により、取り組み実態や具体的な挑戦課題が共有されました。
日本製紙株式会社からは、物流ビッグデータラボの活動について共有されました。
日本製紙は巨大な紙の原反をロール状で輸送しており、積み降ろしの作業はドライバーではなく倉庫側の担当者が行います。積載方法によっては専門性が求められ、協業のハードルになります。パレットの標準化が難しく、各製品に合わせた木製パレットを用いる必要があるなど特殊事情がある業界です。
それでも供給制約が進む中、物流効率化と物流子会社の連結利益貢献の視点から、輸送の協業余地を模索しています。MOVOのデータを活用することで、輸送ルートのプロットと潜在的な協業機会の抽出を行い、既に数社と逆方向輸送のマッチングの具体的な検討を進めています。
続いて、トライアルグループの物流子会社株式会社MLSからは、九州の小売り企業が中心となり活動する九州物流研究会の取り組みが紹介されました。
研究会では、メーカーとの「相互配車」、他小売との「相互配車」、さらには「物流センターの共用化」という3つのアプローチを進め、地域単位での物流生産性向上を目指しています。2022年8月の発足直後には、イオン九州とTRIALの共同配送プロジェクトにて2台で回していた便を1台に削減し「1対1」の共同配送を実現しました。
その後着手したのが、「1対N」の相互配車の取り組みです。これまで主流だった「1対1」のマッチングには路線数に限界があることから、対象を「1対N」に拡大させました。今後はさらなる規模拡大に向け「N対N」に挑みます。
株式会社MLSからの講演の最後には「物流の未来は、エリアを超えて業界を超えて、協業が自然な選択肢となる世界だ」との力強いメッセージが発せられました。単なるコスト削減ではなく、社会全体の持続性、競争力、そして地域経済の発展を支える仕組みとしての共同化。その実現には、今この場に集まる企業や行政、テクノロジー企業が一体となった「共創」が必要不可欠であることが再確認されました。
N:Nの共同輸配送実現──その課題の多面性と複雑性
その後のグループディスカッションでは、「共同輸配送の実現に向けた課題」と「それぞれの立場で何をすべきか」について議論しました。
荷主目線に偏りがちな意識の転換、人材育成、共同化による利益の分配方法、商流と物流の分離の問題など、物流リーダーの皆さんが直面する問題から、さまざまな視点で本質的な課題が抽出されました。
特に、共同輸配送への「参加者拡大」「ルールの共通化」についての課題が多く挙げられました。「ルールの共通化」については、貨物の外形規格の統一や出荷期限など流通ルールの共通化、また商物分離の推進などの商慣行をどう打破していくのか、また持続的なものとするためにどのように情報共有していくべきかの議論が多くなされました。技術活用と合わせ、関係者間の合意形成の重要性が指摘された他、行政に支援を求める声も聞かれました。
また、小さくても効果を出すこと、その効果を適切に分配することも重要課題として挙げられました。あるグループからは、「熱量の高い企業同士」が小規模な協業を重ねて成功体験を積み重ねることが、広範囲な共同輸配送の実現に向けた鍵であるとの見解が述べられ、参加者からの共感を得ていました。
各グループから挙がった課題は、企業や業界が主体的に対応するもの、行政が主導するもの、技術的に解決するものと整理し提示され、あらためて個社を超えた協業の必要性を再認識しました。
物流リーダーの「熱量」とともに物流に革新を
今回の「未来の物流共創会議」では、各社が抱える課題やこれからの物流に求められる役割が多角的に共有されました。特に共通して強調されたのは、物流課題に向き合う「熱量」の存在でした。
実際、新たな仲間との出会いと熱のこもった議論を通じ、場の熱気は高まりを増していました。
持続可能な物流の実現には、個社を超えた協業が欠かせません。そこには、経営の理解、現場の理解、商習慣、システム…さまざまな課題がある。
この課題に向き合う物流リーダーの皆さんとともに、Hacobuはこの「熱量」を原動力に、日本の物流を革新していく決意を新たにしました。
▼関連プレスリリース:https://hacobu.jp/news/16445/

*1: 弊社集計による。全国の物流関連拠点数を約116,500拠点と推計(物流センター、輸送拠点、工場等を含む)
*2:「MOVO Berth」を利用したドライバーの電話番号に紐づくIDを集計。2024年5月から2025年4月における月間平均の利用ID数を算出。令和2年国勢調査(総務省)における「道路貨物輸送業」の「自動車運転従事者」の総数77.9万人より試算
関連記事
-
 COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!
COLUMNトラックバースの課題を解決するトラック予約受付システムの特徴を解説!更新日 2026.02.03
-
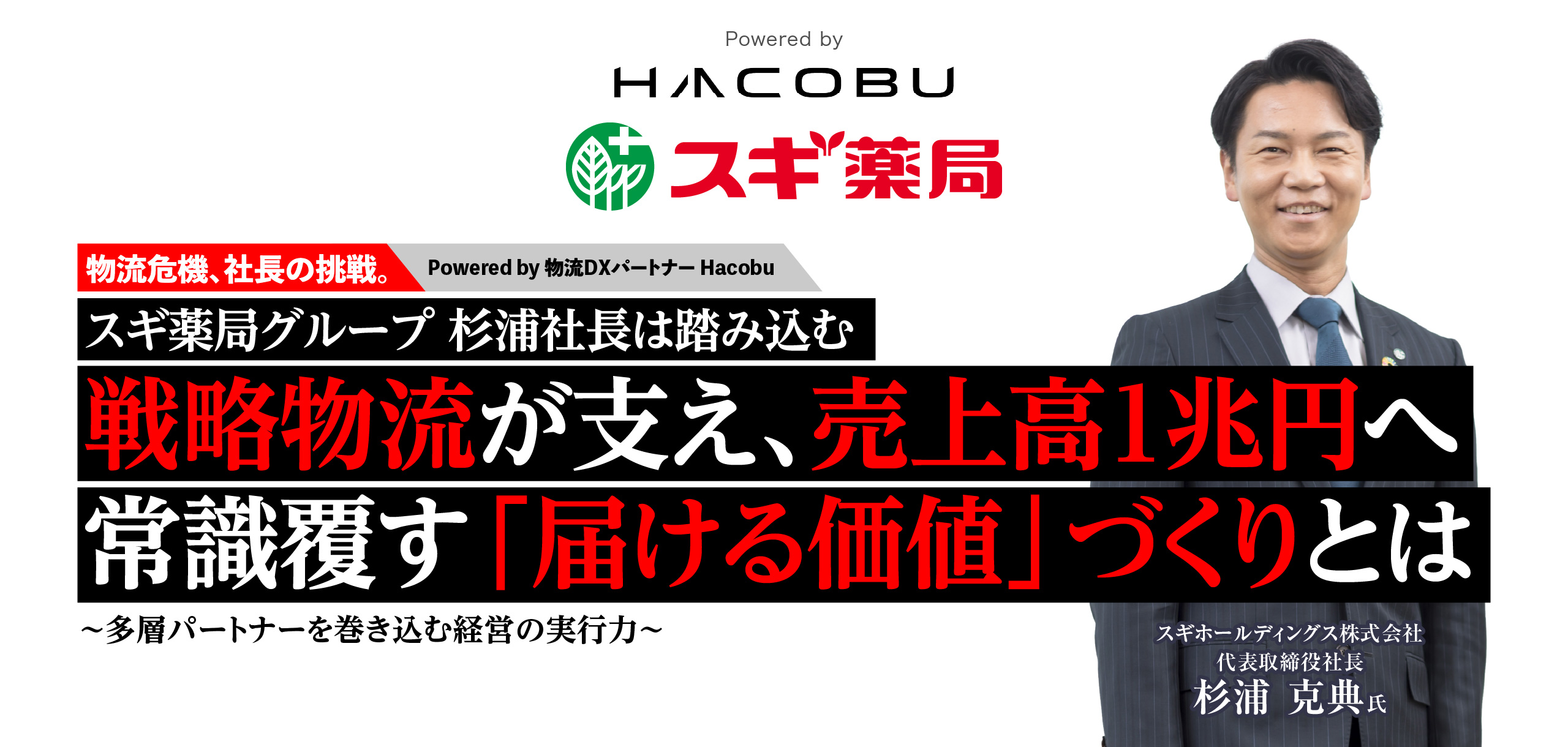 COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~
COLUMNスギ薬局グループ 杉浦社長は踏み込む 戦略物流が支え、売上高1兆円へ 常識覆す「届ける価値」づくりとは ~多層パートナーを巻き込む経営の実行力~更新日 2025.11.28
-
 COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?
COLUMNGPSでトラックの車両位置情報をリアルタイムに把握できる『動態管理システム』とは?更新日 2026.01.26
-
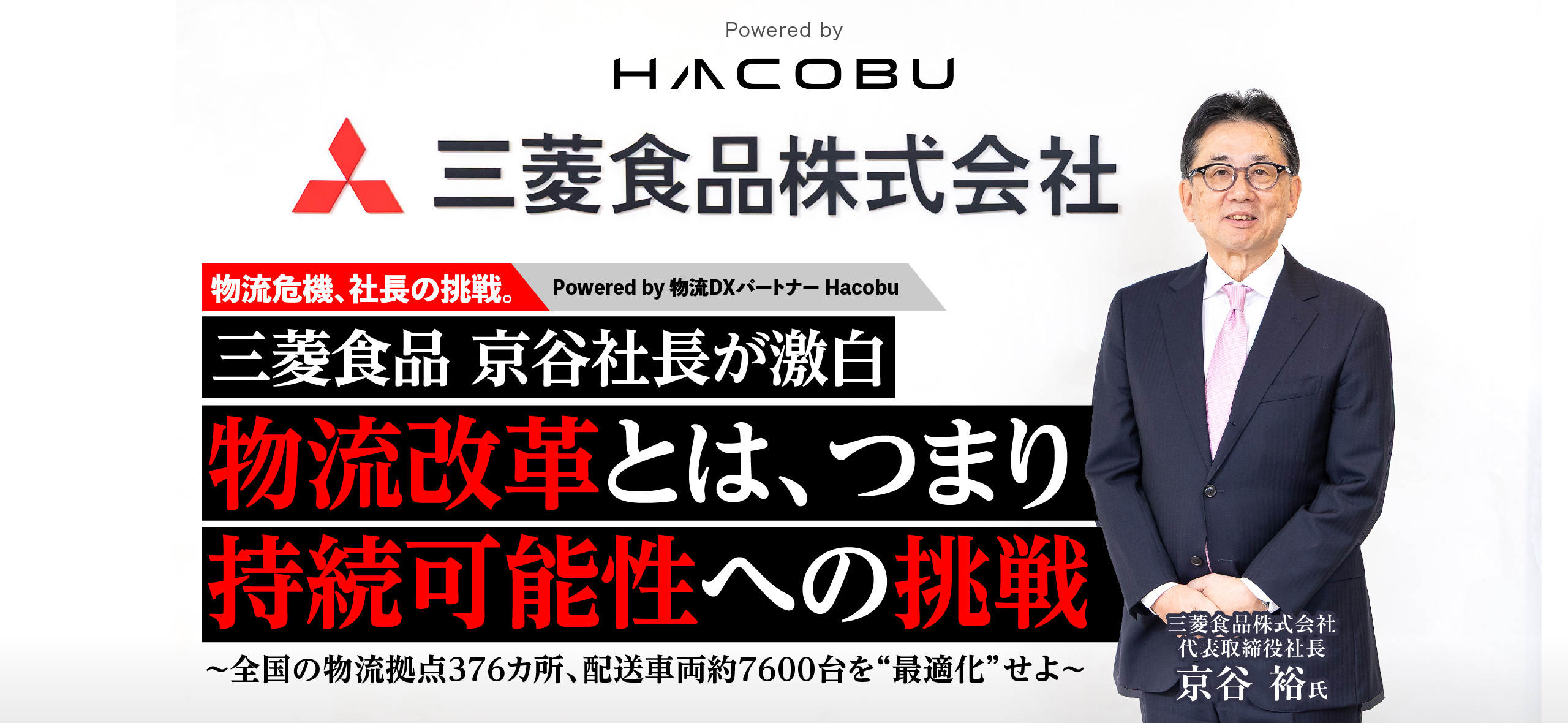 COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~
COLUMN三菱食品 京谷社長が激白 物流改革とは、つまり持続可能性への挑戦 ~全国の物流拠点376カ所、配送車両約7600台を“最適化”せよ~更新日 2025.11.28
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主



















