コールドチェーンとは?重要な理由やメリット・課題などを徹底解説

コールドチェーンとは低温保管が必要な商品を、生産から消費まで適切な温度を維持しながら流通させる一連のプロセスです。本記事では、コールドチェーンが重要な理由、メリット・課題などを物流DXパートナーのHacobuが解説します。
目次
コールドチェーンとは
先ほど述べたとおり、コールドチェーンとは、低温保管が必要な商品を、生産から消費まで適切な温度を維持しながら流通させる一連のプロセスを指します。この名称は、流通の各段階において低温(コールド)での管理を、切れ目のない鎖(チェーン)のようにつなげることに由来しています。主に生鮮食品や冷凍食品などの食品類で活用されていますが、近年では医薬品など、温度管理が必要な様々な商品の流通にも不可欠なシステムとして注目されています。
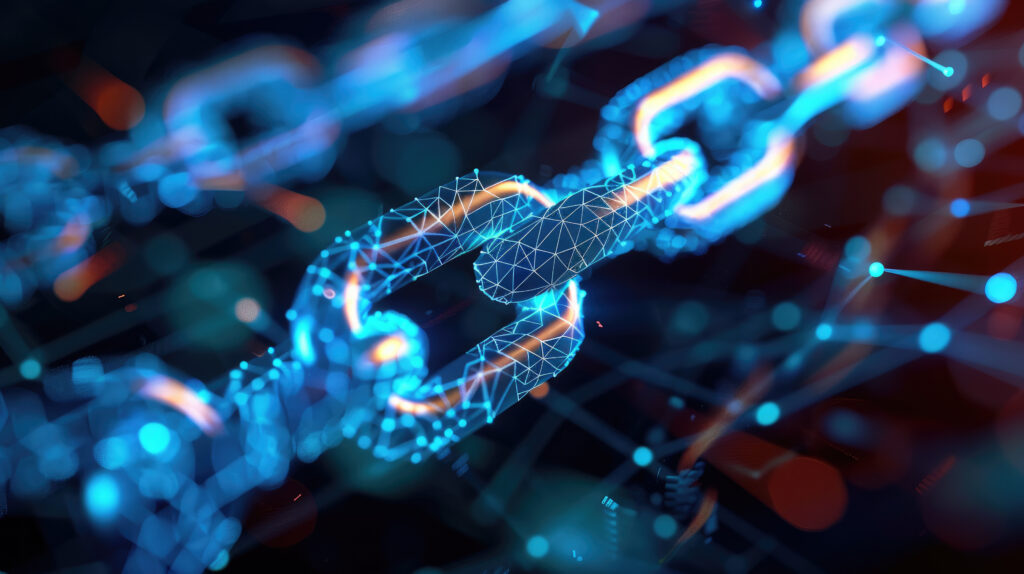
コールドチェーンが必要な理由
本章では、コールドチェーンが必要な理由について述べていきます。
生鮮食品・冷凍食品の安定供給
コールドチェーンは、温度に敏感な生鮮食品や冷凍食品を、品質を損なうことなく広範囲に輸送するための重要な技術システムです。これらの食品は、温度管理が適切でないと品質が急速に劣化してしまうため、生産地から消費地までの輸送過程における温度管理が極めて重要となります。コールドチェーンの導入により、食品の鮮度と品質を最適な状態に保ちながら、遠隔地へ輸送することが可能になりました。
医薬品の安定供給
バイオ医薬品やワクチンは、極めて繊細な温度管理を必要とする医療製品です。コロナ禍ではワクチンがコールドチェーンによって輸配送されたことが記憶に新しいでしょう。医薬品の温度管理が徹底されることで、日本全国の医療現場へ高品質な医薬品を安定的に供給することが可能になります。もし、このコールドチェーンが機能不全に陥れば、患者の治療に必要不可欠な医薬品の供給が阻害され、深刻な医療サービスの中断につながる可能性があるのです。
小口保冷配送サービスに関する国際標準
アジア諸国で需要が高まる小口保冷配送サービスにおいて、適切な温度管理を実現するための国際標準が2020年5月に発行されました。これにより、日本の物流事業者のサービスの質が適切に評価され、国際競争力が強化されるとともに、各国において市場の健全な育成と拡大に寄与することが期待されています。
今回発行された国際標準 ISO 23412*1(小口保冷配送サービス)では、保冷荷物の陸送において、適切な温度管理を実現するための、サービスの定義、事業所、保冷車両、保冷庫、冷却剤の条件、作業指示書とマニュアルなどの基準が設けられました。

コールドチェーンのメリット
本章では、コールドチェーン導入のメリットについて解説します。
食品ロスを削減できる
精密な温度管理により、農産物や加工食品の劣化を抑制することができるようになります。食品を新鮮な状態で維持できるので、販売可能期間を大幅に延長できる場合があります。これにより、食品廃棄ロスの削減に大きく貢献し、食料資源の有効活用を実現します。
販路を拡大できる
コールドチェーン普及以前の物流は、品質保持のために中継地点に細かな物流拠点を設置する必要があり、配送ルートが非常に制限されていました。しかし、コールドチェーン技術の発展により、商品の温度を一定に保ちながら長距離輸送が可能となり、従来は地理的制約により販売できなかった遠隔地への販路拡大が実現しました。これにより、生産者は従来よりもはるかに広範囲のマーケットに商品を届けることができるようになり、ビジネスチャンスの拡大につながります。
コールドチェーンの課題
本章では、コールドチェーンの課題について解説します。
コスト負担が大きい
コールドチェーンの運用において、最も大きな課題の一つとなっているのがコストの問題です。常温での物流と比較すると、温度管理に必要な特殊な設備や機器の導入により、輸送・保管にかかる費用が大幅に増加します。たとえば、温度管理機能を備えたトラックや冷蔵・冷凍倉庫などの設備投資には、多額の初期費用が必要となります。 さらに、これらの設備を維持・管理していくためには、電気代や定期的なメンテナンス費用など、継続的なランニングコストも発生します。また、温度管理システムの故障や不具合を防ぐための予防保守作業も欠かせません。このように、コールドチェーンの運用には、導入時の一時的な投資だけでなく、長期的な視点での財務計画が必要不可欠です。
管理に手間がかかる
コールドチェーンは、食品や医薬品の品質を保つために、製造から配送、保管までのすべての段階で適切な温度を維持する必要があります。この温度管理は手間がかかるだけでなく、非常に精密な調整が求められます。また、低温環境での作業は、従業員の身体に負担をかけることが多く、長時間作業を行うと生産性の低下や健康被害のリスクも生じます。そのため、効率的かつ安全に管理を行う仕組みが欠かせません。

コールドチェーンの3つのシステム
本章では、コールドチェーンの3つのシステムについて解説します。
1.生産・加工
生産・加工の工程は商品によって異なり、それぞれに適した処理を行う必要があります。例えば、青果では鮮度を保つために出荷前の「予冷処理」が必須です。この工程では青果を低温状態にし、輸送中の品質劣化を防ぎます。一方、肉や魚のような生鮮食品では、細胞の破壊を抑え品質を維持するために「急速冷凍」が行われます。また、これらの低温処理後は、商品ごとに適した冷蔵庫での保管が重要です。適切な温度管理を徹底することで、商品価値を最大限に引き出し、消費者に高品質な製品を届けることができます。生産・加工の各工程は、物流の効率化と商品の価値維持を支える重要な要素です。
2. 流通
流通とは、商品が工場からユーザーのもとへ届くまでのプロセスを指します。この工程は、特にコールドチェーンにおいて非常に重要で、商品の品質に直接影響します。 遠方への配送では中継地点として一時的に倉庫を利用する場合がありますが、温度管理に対応した倉庫を選ぶ必要があります。こうした倉庫は常温倉庫に比べ配送ルートが限られる可能性があるため、あらかじめ最適な配送ルートを検討することが物流効率や品質管理の観点で重要です。 効率的な流通の設計には、温度管理とルート選定の両方を考慮することが求められます。
3. 消費
品質を維持した商品がユーザーのもとに届いた後、その商品が実際に消費されるまでのプロセスも、コールドチェーンの重要な一環です。特に食品は、家庭用冷蔵庫や冷凍庫での保管期間が長くなり、消費までに時間がかかることが一般的です。このため、消費者が適切に保管できるようにする工夫が欠かせません。 たとえば、保管しやすいパッケージを採用することで、冷蔵庫や冷凍庫内でのスペース効率を高めることが可能です。また、ラベルに「最適な保管温度」や「保存期間」などを明記することで、消費者が正しい保管方法を理解できるようになります。これにより、商品の品質が損なわれるリスクを軽減し、消費者満足度の向上にもつながります。 コールドチェーンの最終段階として、消費プロセスを見据えた施策を検討することが、全体の価値を最大化するポイントとなります。
コールドチェーンとIoTシステム
コールドチェーンの実現のためには、データ・ロガーなどのIoT装置が応用されはじめています。これによりコールドチェーンによる輸送中の温度管理がより正確になります。例えば、輸送中最高気温がどのくらいだったか、推奨温度から逸脱した時間があればどのくらいかといったことも正確にモニタリングできます。

まとめ
ここまで述べてきたように、コールドチェーンとは、低温保管が必要な商品を生産・加工、流通、消費まで適切な温度で管理し、品質を維持する流通プロセスで、生鮮食品や医薬品の安定供給に不可欠であり、食品ロス削減や販路拡大といったメリットを提供します。しかし、運用には高コストや管理の手間といった課題も存在します。技術の発展により、効率的で安全な運用が進む中、さらなる普及が期待されています。
なお、Hacobuでは「運ぶを最適化する」をミッションとして掲げ、物流DXツールMOVO(ムーボ)と、物流DXコンサルティングサービスHacobu Strategy(ハコブ・ストラテジー)を提供しています。
物流現場の課題を解決する物流DXツール「MOVO」の各サービス資料では、導入効果や費用について詳しくご紹介しています。
トラック予約受付サービス(バース予約システム) MOVO Berth
MOVO Berth(ムーボ・バース)は、荷待ち・荷役時間の把握・削減、物流拠点の生産性向上を支援します。
動態管理サービス MOVO Fleet
MOVO Fleet(ムーボ・フリート)は、協力会社も含めて位置情報を一元管理し、取得データの活用で輸配送の課題解決を支援します。
配車受発注・管理サービス MOVO Vista
MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)は、電話・FAXによるアナログな配車業務をデジタル化し、業務効率化と属人化解消を支援します。
物流DXコンサルティング Hacobu Strategy
Hacobu Strategyは、物流DXの戦略、導入、実行まで一気通貫で支援します。
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主
























