下請法 三条書面(新:取適法 四条書面)とは?物流における重要性やメリット、記載事項を解説

三条書面(新:四条書面)とは、下請法(新:取適法)に基づき委託事業者が中小受託事業者へ発注する際に交付が義務付けられている書面です。2026年1月からは法改正により「特定運送委託」が新たに規制対象に追加され、荷主企業から運送業者への運送委託にも三条書面の交付義務が課せられました。
これまで下請法の適用外だった運送委託が規制対象となることで、多くの荷主企業では配車システムの見直しや業務フローの変更が必要となります。本記事では、三条書面の基礎知識から記載すべき12項目、物流領域における重要性、法改正への対応方法などについて、物流DXパートナーのHacobuが解説します。
三条書面に対応した配車システムをお探しであれば、MOVO Vistaがおすすめです。まずは以下よりフォーム入力の上、資料をダウンロードしてご覧ください。
\三条書面(新:四条書面)対応の配車システムの詳細はこちら/
本記事の要点は以下のリンクより、資料としてもダウンロードいただけます。
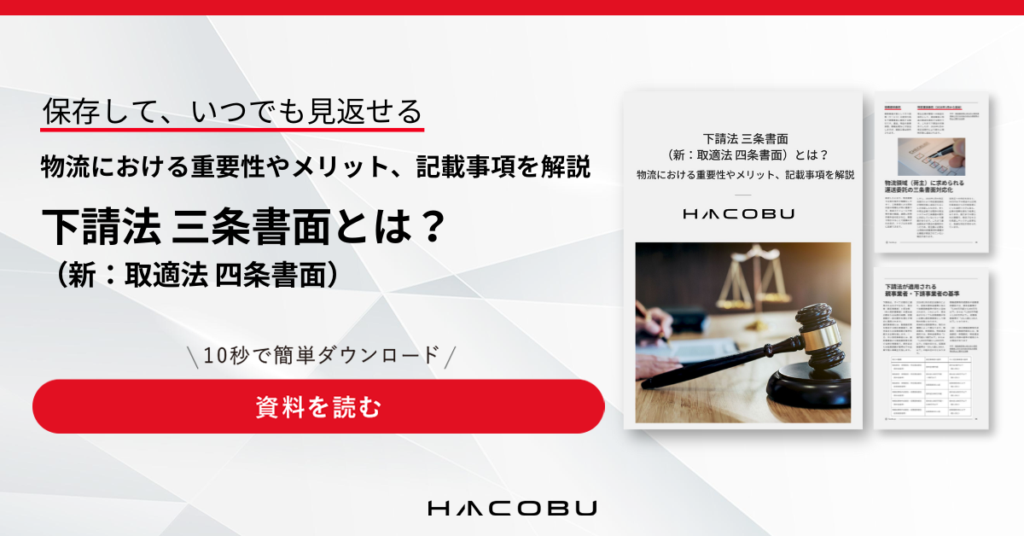
目次
三条書面とは
三条書面とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第三条に基づき、委託事業者が中小受託事業者に発注する際に交付しなければならない書面です。発注条件や取引内容を明確にすることで、取引の公正化と中小受託事業者の保護を目的としています。
この書面には、委託事業者および中小受託事業者の名称、委託日、給付内容、納期、納品場所、検査完了期日、代金の額と支払期日など、法律で定められた具体的な記載事項をすべて含める必要があります。委託事業者は、発注と同時に直ちに三条書面を交付する義務があり、この義務を怠ると法律違反となります。
2026年1月の法改正による名称変更
2026年1月から、下請代金支払遅延等防止法(下請法)は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に正式名称が変更され、通称は「中小受託取引適正化法(取適法)」となりました。
この法改正に伴い、従来「親事業者」と呼ばれていた発注側の事業者は「委託事業者」に、「下請事業者」と呼ばれていた受注側の事業者は「中小受託事業者」に呼称が変更されました。また、これまで下請法第三条で規定されていた発注書面の交付義務は、取適法では第四条に規定されることになり、「三条書面」の通称は「四条書面」と呼ばれることになりました。
ただし、本記事では読者の理解を容易にするため、便宜上従来の呼称である「下請法」「三条書面」という用語を使用して解説します。
五条書面との違い
三条書面と五条書面(新:七条書面)は、目的と用途が異なります。三条書面は、発注時の契約条件を明示するために下請事業者へ交付する書面です。一方、五条書面は親事業者が自社で作成し保存する書類で、発注から代金支払いまでの取引全体の記録を残すことが目的です。
三条書面には発注条件が記載されますが、五条書面には給付の受領日、検査結果、代金支払日、支払手段など、取引の経過全体を記録します。五条書面には2年間の保存義務があり、交付先と記載内容が異なる点に注意が必要です。
参考:下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則|公正取引委員会
物流領域(荷主)における三条書面の重要性
物流業務では、複数の配送先やスケジュール調整、附帯作業など、取引条件が複雑になりやすい特徴があります。こうした環境下で契約内容が不明確なままでは、作業範囲の認識違いや支払条件のトラブルが発生しやすくなります。
三条書面を適切に交付することで、発注内容、業務範囲、代金支払条件などを明文化でき、荷主企業と運送事業者の間での認識のずれを防止できます。特に運送業務においては、運賃と附帯作業の料金を区分して記載することで、ドライバーの労働時間管理や適正な対価の支払いにもつながります。
また、三条書面の交付は法的義務であり、これを怠ると行政指導や罰則の対象となるため、コンプライアンスの観点からも重要です。
「運送業務、その他一切の付帯業務」の記載は違反行為のおそれと見解
2025年12月、公正取引委員会は「運送業務、その他一切の付帯業務」といった包括的な記載は取適法違反のおそれがあるとの見解を示したことが大きな話題となりました。すべての荷主や物流事業者は、運送とそのほか業務を分離した書面交付に対応しないと下請法違反の可能性が高まりますので注意が必要です。
三条書面を交付しない場合の罰則
委託事業者が三条書面を交付しなかった場合、下請法第十条(新:第十四条)に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、公正取引委員会から勧告を受けるなど、行政指導の対象となります。法令違反は企業の信頼を損なうため、必ず交付義務を遵守する必要があります。
参考:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
取適法(旧:下請法)とは?改正事項や物流領域への影響、独占禁止法・物流特殊指定との関係を解説
2026年1月に施…
2026.02.04
三条書面の記載事項
委託事業者は、発注の際に下請法および公正取引委員会規則で定められた具体的記載事項をすべて記載した書面(三条書面)を、直ちに下請事業者へ交付する義務があります。「直ちに」とは時間的な遅延を認めないことを意味し、発注と同時に交付しなければなりません。
ただし、発注時点で正当な理由により内容が確定せず記載できない事項がある場合は、確定した段階で速やかに書面を追加交付することで対応できます。たとえば、下請代金の具体的な金額が確定していない場合は、算定方法を記載することも認められています。
三条書面の作成に際しては、公正取引委員会と中小企業庁が共同で公表している「下請取引適正化推進講習会テキスト」に記載例が掲載されていますので、参考にすることができます。
参考:下請取引適正化推進講習会テキスト|公正取引委員会・中小企業庁
三条書面に記載すべき具体的事項
三条書面には、以下の12項目をすべて記載する必要があります。
(1) 親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
(2) 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
(3) 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう、明確に記載する)
(4) 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)
(5) 下請事業者の給付を受領する場所
(6) 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日
(7) 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが、算定方法による記載も可)
(8) 下請代金の支払期日
(9) 手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
(10) 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
(11) 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
(12) 原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法
下請法の対象となる5つの取引
下請法が適用される取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つが従来から定められていましたが、2026年1月からは「特定運送委託」が新たに追加され、計5つの取引類型が規制対象となります。
製造委託
親事業者が業として販売または製造を請け負う物品、自ら使用する物品、これらの半製品・部品・附属品・原材料などの製造を下請事業者に委託する取引です。
修理委託
親事業者が業として修理を請け負う物品、または自ら使用する物品の修理行為の全部または一部を下請事業者に委託する取引です。
情報成果物作成委託
親事業者が業として提供または作成を請け負う情報成果物(プログラム、映像コンテンツ、設計図など)、または自ら使用する情報成果物の作成行為を下請事業者に委託する取引です。
役務提供委託
親事業者が業として行う役務(サービス)の提供行為を下請事業者に委託する取引です。運送、物品の倉庫保管、情報処理などが該当しますが、建設工事は除外されます。
特定運送委託(2026年1月から追加)
荷主企業が顧客への納品を目的として、運送業者に物品の配送を委託する取引です。これまで下請法の対象外でしたが、2026年1月の改正法施行により新たに規制対象に追加されました。
参考:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

物流領域(荷主)に求められる運送委託の三条書面対応化
前述したとおり、物流業務では取引条件が複雑化しやすく、三条書面による契約内容の明確化が特に重要です。配送スケジュールや附帯作業の範囲、運賃と附帯作業料金の区分など、書面で明示することで認識のずれを防ぎ、トラブルを未然に回避できます。
しかし、2026年1月の改正法施行により特定運送委託が規制対象に追加されたものの、多くの荷主企業では既存の発注システムが三条書面の要件に対応していないという課題があります。これまで運送委託は下請法の適用外だったため、発注書に必要な12項目の記載事項を網羅する機能が実装されていない場合があります。
法改正への対応を怠ると、50万円以下の罰金や公正取引委員会からの行政指導といった法的リスクに加え、企業の信頼を損なう結果となります。施行までの限られた期間で、発注プロセスの見直しやシステム改修など、急速な対応が求められています。
下請法が適用される親事業者・下請事業者の基準
下請法は、すべての取引に適用されるわけではなく、発注側(委託事業者)と受注側(中小受託事業者)の資本金の額または出資の総額、従業員数が一定の要件を満たす場合に適用されます。
委託事業者とは、製造委託等を発注する側の事業者で、資本金または従業員数が基準を超える企業を指します。一方、中小受託事業者とは、委託事業者から製造委託等を受ける側の事業者で、資本金または従業員数が基準以下の企業や個人事業主を指します。
2026年1月の改正法施行により、従来の資本金基準に加えて従業員数基準が新たに追加されました。これにより、資本金が少なくても従業員数が多い企業も委託事業者として規制の対象となります。
具体的な適用基準は、取引の種類によって異なります。製造委託、修理委託、特定運送委託では、資本金基準は「3億円超と3億円以下」または「1,000万円超と1,000万円以下」の組み合わせ、従業員数基準は「301人超と300人以下」の組み合わせとなります。
情報成果物作成委託や役務提供委託では、資本金基準が「5,000万円超と5,000万円以下」または「1,000万円超と1,000万円以下」、従業員数基準が「101人超と100人以下」となります。
| 取引の種類 | 委託事業者の基準 | 中小受託事業者の基準 |
|---|---|---|
| 製造委託・修理委託・特定運送委託(資本金基準) | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 (個人含む) |
| 製造委託・修理委託・特定運送委託(資本金基準) | 資本金1,000万円超 〜3億円以下 | 資本金1,000万円以下(個人含む) |
| 製造委託・修理委託・特定運送委託(従業員数基準) | 従業員数301人超 | 従業員数300人以下 (個人含む) |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託(資本金基準) | 資本金5,000万円超 | 資本金5,000万円以下(個人含む) |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託(資本金基準) | 資本金1,000万円超〜5,000万円以下 | 資本金1,000万円以下(個人含む) |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託(従業員数基準) | 従業員数101人超 | 従業員数100人以下 (個人含む) |
(注)一部の情報成果物作成委託・役務提供委託には、製造委託・修理委託・特定運送委託と同様の基準が適用される場合があります
参考:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
\三条書面(新:四条書面)対応の配車システムの詳細はこちら/
三条書面を交付するメリット
三条書面を適切に交付することは、法令遵守にとどまらず、取引の安定化や企業の信頼性向上にもつながります。ここでは、三条書面を交付する具体的なメリットを解説します。
下請取引における透明性の確保
三条書面によって発注内容や代金支払条件を書面で明示することで、取引の透明性が高まります。口頭でのやり取りのみでは記録が残らず、後から「言った・言わない」の争いが生じるリスクがありますが、書面で契約内容を明確にすることで、双方が共通の認識を持つことができます。
特に物流業務では、配送スケジュールや附帯作業の範囲など、複雑な条件が絡むため、書面による明確化が重要です。三条書面があることで、委託事業者と中小受託事業者の双方が取引内容を正確に把握でき、認識のずれを未然に防ぐことができます。
支払いトラブルの未然防止
三条書面には委託代金の額と支払期日を明記する必要があるため、支払いに関するトラブルを未然に防ぐことができます。取引開始時に支払条件が曖昧なままでは、支払期日の遅延や代金の減額といった問題が発生しやすくなります。
口頭での合意のみでは記録として残らないため、後から条件について認識の食い違いが生じるケースも少なくありません。三条書面に支払条件を具体的に記載することで、代金の支払いに関する約束が明確になり、委託事業者と中小受託事業者の双方にとって安心できる取引環境が構築されます。
法令遵守による信頼関係の構築
三条書面を適切に交付することで、法令を遵守した取引を行っていることが中小受託事業者に伝わり、企業としての信頼性が向上します。下請法に則った公正な取引条件を示すことで、中小受託事業者の立場を保護し、長期的な信頼関係の構築につながります。
また、法令遵守を徹底することで、公正取引委員会からの行政指導や罰則を回避できるため、企業のコンプライアンス体制を強化できます。適正な取引慣行を実践する企業として社会的な信用を獲得でき、健全な事業運営の基盤となります。
三条書面ならMOVO Vista
運送委託における三条書面対応には、当社の配車システム「MOVO Vista(ムーボ・ヴィスタ)」が有効です。MOVO Vistaは物品の運送委託取引に特化した発注システムで、基幹システムから取り込んだ貨物情報をもとに配車組を行うと、配送依頼書(発注書)が自動生成されます。
依頼書には配送内容、荷物情報、数量、納品場所などが正確に記載されるため、三条書面に求められる要件を満たした形で取引を進めることができます。運賃、附帯業務料、燃料サーチャージといった金額を明示できるほか、支払期日や支払方法についても協力会社ごとに設定可能です。これにより、従来曖昧になりがちであった条件を明記でき、発注者・受注者双方が事前に条件を確認できます。
さらに、システム上で「承諾する」ボタンを押下すると、その記録がログとして保存され、合意のプロセスを客観的に証明できます。電話やメールでは残りにくかった記録を可視化することで、運送委託のブラックボックス解消に貢献します。
自動生成された依頼書は電子データとして保存され、法令に沿った交付記録を保持できるため、紙ベースの管理と比較して法令遵守と業務効率化を同時に実現します。また、附帯作業などを運賃と分けて管理・請求できる機能により、物流事業者にとっても実務的なメリットがあります。発注履歴がMOVO Vista上に一元的に蓄積されることで、価格決定プロセスや協議内容の文書化も可能となり、取引の透明性を確実に担保できます。
三条書面に対応した配車システムをお探しであれば、MOVO Vistaがおすすめです。まずは以下よりフォーム入力の上、資料をダウンロードしてご覧ください。
\三条書面(新:四条書面)対応の配車システムの詳細はこちら/
まとめ
三条書面は、下請法に基づき委託事業者が中小受託事業者に発注する際に交付が義務付けられた書面で、取引の透明性確保と下請事業者の保護を目的としています。2026年1月からは特定運送委託が新たに規制対象に追加され、荷主企業には急速な対応が求められています。
三条書面には12項目の記載事項が必要であり、適切に交付することで取引の透明性向上、支払いトラブルの防止、信頼関係の構築といったメリットが得られます。物流領域では既存システムが対応していないケースが多く、MOVO Vistaのような三条書面に対応した発注システムの活用が有効です。
本記事の要点は以下のリンクより、資料としてもダウンロードいただけます。
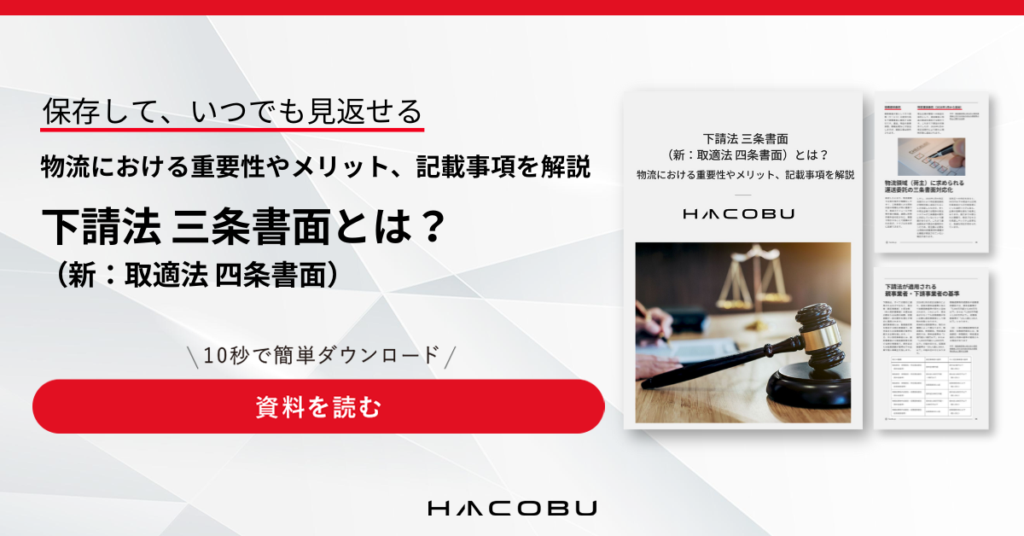
関連記事
お役立ち資料/ホワイトペーパー
記事検索
-
物流関連2法
-
特定荷主




















